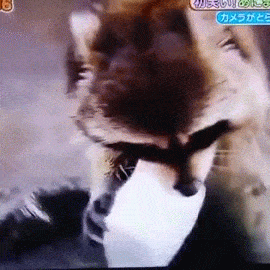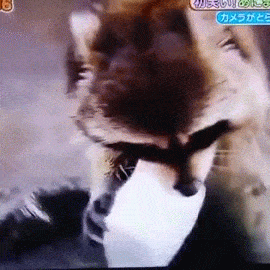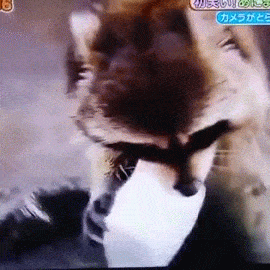◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
レコードのクリーニング 20 YouTube動画>6本 ->画像>8枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/pav/1596457688/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
う~ん、あれからレコードの落札、次々やってるのに、レコードのクリーニングやってない。
システマブラッシングと、精製水噴霧&針通し、中性洗剤洗浄と精製水洗浄でかなりクリーニング出来る感じだけど、
色々やるべき事があってクリーニングできてないのが残念。
結論から、微細振動ブラッシングも使えば、そうとうノイズは減らせることはわかった。
あとは実践。
RIAAの標準カーブとは異なりハイ上がりに録音セッティングされる根拠となるグラフ
://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Pre-RIAA_LP_replay_equalization_curves.svg/510px-Pre-RIAA_LP_replay_equalization_curves.svg.png
解説:RCA1950再生RIAA特性イコライザーで
Columba録音RIAA特性のレコードを聴くと
ベース音は約+6dB強調されシンバル音は約+6dB強調される
Chris Rea - On The Beach 1986 Video Sound HQ
://youtube.com/embed/L_Wa7Q7dMxo?list=UUYMEOGcvav3gCgImK2J07CQ
ボンドパックしてボソボソノイズがでて困っている人へ
中性洗剤で下洗いが終わってる前提で話をする
V溝とV溝の間の平面部分に可塑剤が残っている可能性は?
ボンドパック剥がした後や何かか触れた時にV溝の領域に侵入しかかっている可能性
これが針に触れボソボソノイズを出すかも?
この対策は以前にも言ったが、コットンパフに薄めていないアルコールを含ませV溝とV溝の間の平面部分を丁寧にこする事
V溝へ入り込むがボンドパックして取るので問題はない
あと考えられるのは何度も言っているが、薄めていないアルコールを可塑剤に含ませてボンドパックして剥がす事
再生針の先端はV溝の底には当たらずに空間ができるのが正解
V溝の底にまだ取り切れていない可塑剤があればボソボソノイズを出す
溶解パラメーター、SP値、HSP値って、ご存じないですよね。
化学専門の大学でも授業では教わらないし、私は卒論研究の時、研究室内で初めて教わりました。
詳しいことは、ググれば様々なところから理論的な説明がありますが、
要点をいうと溶媒、溶質のSP値が近ければ混ざり合うことです。
これが目安となります。
では、レコードのクリーニングに使われている溶媒やポリマーは以下の通りです。
http://www.diced.jp/~KAZU/sp3.htm
水 23.4
メタノール 14.5
エタノール 12.7
イソプロピルアルコール 11.5
https://www.plastics-material.com/%E3%83%9B%E3%83%A2%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%BB%E6%A8%B9%E8%84%82%E3%81%AE%E6%BA%B6%E8%A7%A3%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BFsp%E5%80%A4/
ポリ塩化ビニル(PVC) 9.4~10.8
ポリ酢酸ビニル 9.4~9.6
http://www2s.biglobe.ne.jp/~kesaomu/bu_sp_atai.html
酢酸ビニル樹脂 9.2
塩化ビニル樹脂 9.3
https://www.packing.co.jp/GOMU/taiyu1.htm
ポリビニルアルコール 12.6
つづく つづき
引用文献でばらつきがありますが、極性の大きい順に並べると、
水>メタノール>エタノール≒ポリビニルアルコール>イソプロピルアルコール>ポリ塩化ビニル≒ポリ酢酸ビニル
となります。
水とポリビニルアルコールは水に溶けます(正確に言えばお湯に溶ける)。
また、ポリビニルアルコールの水溶液、つまり糊にエタノールを入れるとまあまあ溶けますが、
イソプロピルアルコールだと最初はゲル化し、長時間撹拌すると溶解して透明になります。
これらの溶媒やポリマーは、レコードの主成分であるポリ塩化ビニルのSP値からかけ離れているので、
乾燥後は剥離しやすい。
ポリ酢酸ビニルはポリビニルアルコールよりもSP値が低く、水との混合溶液は作れませんが、エマルジョンになります。
また、ポリ塩化ビニルと比較するとポリビニルアルコールと違い、SP値はほとんど同じなので、接着しやすくなります。
だから、剥離後でも溝内に残りやすい。
アルコールを入れ過ぎると、見かけ上のSP値がポリ塩化ビニルに近づくので、より一層接着してしまうものと思います。
つづく
つづき
そこで改めて特開63-263601を読むと、
木工ボンドの酢酸ビニルエマルジョンは接着してしまうという欠点を補うためにポリビニルアルコールを添加して剥離しやすくしています。
実施例-1には酢酸ビニルエマルジョン(樹脂固形分40%) 90重量部、
ポリビニルアルコール(固体、けん化度88%、重合度1000) 10重量部
を40℃で撹拌混合したものを書いています。
酢酸ビニルエマルジョンは市販の木工ボンドでいいでしょうが(樹脂固形分製造元のWebで要確認)
固体のポリビニルアルコールはさすがに家庭内では扱いにくいのでポリビニルアルコール糊を使用します。
アラビックヤマトは高価なのでポリビニルアルコールの洗濯糊を使用していかがでしょうか。
おおよそ洗濯糊の固形分は8~10%と考えたほうがいいでしょう。
ただし、この特許ではアルコール添加のことは一切触れておりません。
木工ボンドと洗濯糊、アルコールの最適比率を検討したほうがいいでしょう。
例
コニシボンド CH18を固形分42%、洗濯糊の固形分8%として1:1で混ぜれば固形分25%
これを
45(CH18):45(糊):10(アルコール)
40(CH18):40(糊):20(アルコール)
30(CH18):30(糊):30(アルコール)
20(CH18):20(糊):40(アルコール)
と実験計画を立ててみました。
間違い。訂正
30(CH18):30(糊):30(アルコール)→30(CH18):30(糊):40(アルコール)
20(CH18):20(糊):40(アルコール)→薄すぎるので粘度が低くてやりにくいと思うので削除。
ざっくりと実験の方法として、
DIY店や100円ショップに行って目盛付きの容器を買います。
レコード片面はだいたい30mlあればいいのですが、粘い液体なので容器に付く分量も考えて100mlがいいかもしれません。
最初にPVA(ポリビニルアルコール)45mlくらい、木工ボンド45ml入れて、無水のエタノールか、無水のイソプロピルアルコールを入れて均一になるまで撹拌すればいいでしょう。
撹拌後は、一日置くといいみたいです。気泡が無くなります。
だいたい100mlの容器でレコード両面がパック可能となりますから、
組成検討にもいいと思います。
特許での考えは、木工ボンドのエマルジョンの周りにPVAが覆い、コロイド状になります。
レコード面に展開する場合は、極性の大きなPVA面がレコード面に接して剥離が可能になるということです。
しかし、アルコールが添加されるとこのコロイドがどのようになるかわかりませんが、
アルコール木工ボンドパックの欠点である、溝内の剥離取り残しが低減されると期待されます。
もちろん、アルコール添加した効果も狙えるでしょう。
Q: ヘッドフォン出力にデジタルアンプの性能は関係あるか?
A: 音は出口が8割
なかなか来てますね。
>>12 なかなか良い情報だね。
ちょっと使ってみるよ。
>>13 理学部卒?
詳しいね。
相当専門的だね。
そう言うの、参考になるよ。
アルコール・ボンドパックで表面に残留するモノを除去するため、界面活性剤洗浄をやって見た。
ただ、1度だけで無く3度繰り返しやって見た。
モゾモゾする膜を張ったような音が相当スッキリした。
多分表面に酢酸系の異物が膜を形成し、それがモゾモゾに関係していたと見られる。
この除去に弱アルカリ界面活性剤は有効に機能する。
ただ、繰り返し洗浄しなければ十分除去出来ないようである。
アルコール・ボンドパックをやってる。
どうもアルコールを盤に広げてその後に木工ボンドを塗布してアルコールと混ぜる方法だと、最善では無いようだ。
無水エタノールを使用するとゲル化して柔軟性が失われ、消毒用エタノールを使用すると、粘着度が低くなる。
以前やっていた、予め消毒用エタノールを木工ボンドに混ぜたモノを使用する方法の如何をやって見るつもりだ。
>>22 ビニ焼け除去で、
どうもボンドや糊に含まれる不純物の酢酸が作用しているように思える。
木工ボンドに無水エタノールを混ぜないクリーニング
【用意するもの】
無水エタノール
ガラス空き瓶(ニッスイ 焼さけあらほぐしの空き瓶なwシリコンパッキン付きの蓋だから便利)
使い捨てコットンパフ
超音波洗浄機(ボルト締めランジュバン型振動子50ワットが3発入った合計150ワット、水槽6リットルのもの、水の温度は常温)
6リットルの水道水(マイクロバブルシャワーヘッドまたはアスピレーターを通った事により水に含まれる余分な空気を抜き超音波洗浄の効果をあげる(ディガス))
木工ボンド
レコード盤を中性洗剤で下洗い済みの前提で話す(バキュームで水分は除去しておく)
無水エタノール100%をガラス容器に注ぎ、半分にカットしたコットンパフを入れ十分に含ませる
コットンパフを半分に切る理由は無水エタノールの節約のため、半分に切ったコットンパフは片面一回用で使ったら捨てる
レコード盤の片面にコットンパフで無水エタノールを塗布(塗布の仕方は
>>12の方法でV溝とV溝の平面部分を50ミリの円を描くようにする)
続いて裏面も同様に塗布(レーベル面に無水エタノールが付着しないよう十分注意)
3分ほど待って無水エタノールが半乾きになったら超音波洗浄で可塑剤をさらに柔らかくする
超音波洗浄機でレコードの回転数は1分間に1回転程度(レコードの回転に水がついてこない速度、最初はゆっくり回しても水がまったりと付いてくるが3分ほどではじくようになってくる)
アルコール分を含んだ可塑剤の表面がキャビテーションの衝撃波で破れ、水にアルコール分が溶け出すのを期待
と同時に可塑剤もある程度は柔らかくなり量も減るみたい(針に付着物が少なくなる理由から)
ただ水に界面活性剤を入れていてないので汚れの再付着は目立つしプチノイズは出るが、バキューム後に木工ボンドパックをするので問題ないとする
で、無水エタノール→レコード盤に塗布→超音波洗浄→バキューム(バキュームが面倒なら人工セーム皮で水分吸収でも可)を2回行うことによって残留する可塑剤は減るようだ
この時点でレコード再生するとプチプチ音は出るが、音の艶や明るさや周波数帯域は良い線いってる
仕上げで木工ボンドでトドメさしてプチ音除去でとても良い感じになった
なぜ木工ボンドに無水エタノールを混ぜないかについて
他の人が言っていたように「乾かない」のと「残留した剥がし残しがある」からだ
無水エタノールを混ぜるとどうしても木工ボンドの粘度が柔らかくなってしまってひっくり返して裏面にボンドを塗ると最初に塗った面の木工ボンドがツララのように垂れてくるw
混ぜる無水エタノールの量を少なくすれば、木工ボンドの粘度はある程度粘り腰は確保できるが、可塑剤に無水エタノールを染み込ませる量も減ってしまうのが難点
なので無水エタノール塗布と木工ボンド塗布をきっちり分けることによってそれぞれが能力を発揮して、また超音波洗浄の力を借りる事でより確実に可塑剤の除去が可能なのではと
1、無水エタノール100%→可塑剤にアルコールをたっぷり吸わせ柔らかくすることに専念してもらう
2、超音波洗浄→アルコールをたっぷり吸った可塑剤を粉砕(しているのか?w)しつつ、さらに柔らかくする
(1と2を2回ないし3回行う)
3、素のままの木工ボンド→デフォルトの粘度で保持力もあるし、続けて裏面も塗布できるし、無水エタノールで薄めていないのでちゃんと乾くし、ボンドパックの能力も健在
ちなみに超音波洗浄の水にドライウェルを数滴混ぜて汚れの再付着防止でプチ音を減らす事はできた
で、木工ボンドパックは省けるかなと期待したが、ドライウェルがアルコールの水中溶け出し具合を妨げてるようで、音の鮮度は後退してしまった。
もうちっと研究したいところ
【ディガスについて】
水に溶け込んだ空気を抜く事を指す
超音波洗浄で上位機種にはディガス機能がある
超音波を照射すると水に含まれている空気が集まって目に見える気泡となって出てくる
これがキャビテーション(真空の気泡)とは別物で、空気の気泡が衝撃波を吸収してしまう厄介なもの
目に見える空気の気泡は浮力があるので超音波洗浄機を停止させると水面まで上がってきて抜ける
【ディガス機能が付いていなくても、手動で可能】
10秒超音波を照射→空気の気泡がだんだん成長して目で見えるようになってくる→超音波を停止→空気の気泡は浮力があるので水面まで上がってきて消える
さらに超音波を照射しながらシリコンヘラ等でゆっくりかき混ぜる→空気の気泡がまた出てくる
これを20回ほど繰り返すのだが、マイクロバブルシャワーヘッドやアスピレーターを用い、水道水に含まれる空気を強制的に露出させるとディガス処理は半分以上終わったも同然。
マイクロバブルの小さな目に見えない空気の気泡はわずかながら浮力はあるので30分ほど放置しておけば水面まで上がってきて消える(ナノバブルだと浮力はもっと少ないので消えるまでに時間かかる)
マイクロバブルシャワーヘッドやアスピレーターを通った水なら、手動ディガスは10回以下で済むようになるよ
夏場の気温は水道水に含まれる空気は少なく、気温が低い冬は空気を多く含んでいるからこれからの時期は超音波洗浄を行うならディガスは必須
>>25 そう思う。
酢酸は物質の上で広がる性質が有り、これが酢酸の除去を困難にしている。
昨日ボンドパックを剥がしたあと、3度ほど弱アルカリ界面活性剤での洗浄を行った。
これは相当効果があり、ボンドパック後に発生するモゾモゾ感がかなり減少する。
アルコール・ボンドパックと超音波洗浄の組み合わせによるレコードのクリーニングでは、間に界面活性剤洗浄を挟む必要がある。
その理由は以下のとおり。
〇アルコール・ボンドパックでは、パック剥離後に、盤上におそらく酢酸系の異物の異物が残留する。
この残留物を放置すると、パックの度に残留物が増加して雑音を大きくする。
〇超音波洗浄では、超音波振動で盤表面の異物が浮き上がるが、この除去をしなければ再び盤表面に付着する。
この付着物を放置すると、サウンドが鈍り、本来の切れの良いサウンドを再生できなくする。
アルコール・ボンドパックによって、レコードのクリーニングの最終段階手前の状態のLPが次々増えている。
ビニ焼け盤の症状の軽い物は、これからも最終段階手前の状態に成っていくだろう。
問題は、音質改善効果があまり見られない重篤なビニ焼け盤のクリーニングである。
今問題にしているのは、講談社のステレオ世界音楽全集ビニ焼け盤の中のチャイコフスキー「悲愴交響曲」マゼール/VPO盤。
A面の最初から中頃までボボボボッと低周波のノイズがかなり大きめで、何度もボンドパックしてもなかなか小さくならない。
アルコール洗浄でも効果がわからず、手を焼いている。
その他の盤は、順調にノイズが減少し、大半の盤は一応しっかり鑑賞出来るレベルに成っている。
ビニ焼け盤特有のあのザリッザリッと言うノイズは殆どの盤でかなり小さくなっている。
講談社のステレオ世界音楽全集ビニ焼け盤の中のチャイコフスキー「悲愴交響曲」マゼール/VPO盤。
ボボボボッと言う低周波のノイズは、おそらくある程度の厚みの異物が盤表面を覆っている事から発生しているだろう。
この異物の存在が、本来の録音のサウンドの読み取りを阻害している。
針を落として効いても音が小さく、力強さが無い。
この異物の除去に、これまで繰り返しのアルコール・ボンドパックを行ったが、ノイズは大きくなるばかり。
おそらくパックによる残留物が次々と増えて雑音増加に繋がっているのだろう。
対応として次の流れを考えた。
〇超音波洗浄による衝撃で残留物を破壊あるいは軟化させる。
↓
〇その残留物を界面活性剤洗浄で除去する。
↓
〇アルコール・ボンドパックによって、その下の異物を除去する。
この繰り返しによって、盤上の異物は少しずつでも少なくなっていくはず。
>>25 さすがに糊には酢酸は含まれないだろうww
これだけやって聴くのはノイズ有無と再生時の音なんだね。
音楽は聴いてるの?
>>34 糊っていうのはポリビニルアルコールのことだが、
そのポリビニルアルコ―ルの原料は何かと考えると当然の帰着であり、
事実存在する。
臭いでもわかるのだがね。
>>37 あなたにとっては、音楽とは何ですか。
あなたは演奏会やライブ、CDを聞いていればいいのですよ。
あなたにとっては、音楽とは何ですか。
いつも思うのですが、
なぜこのスレに書き込むのですか。
こんどこそ答えてほしい。
>>33 せっかく残留物が残らないようにするため、
木工ボンドだけではなく、ポリビニルアルコールの選択糊を混合する実験を提案しました。
特許もダウンロードできるようにしました。
ご参考にしてください。
>>37 ソノリティって知ってる?
ノイズ除去でソノリティは上がる。
講談社のステレオ世界音楽全集には、素晴らしい演奏、素晴らしい録音があって、他で入手が困難な物が多い。
それらを蘇らせたい。
それと、レコードのクリーニングの限界を確認したい。
>>23 弱アルカリ界面活性剤は使わないほうがいいと思います。
なぜなら、不溶性の金属石鹸ができるからです。
アルカリ性にこだわり、酢酸を中和というのなら、
重曹はアルカリ性なのでこちらが、石鹸カスである不溶性金属石鹸はできませんし、
酢酸ナトリウムは水に溶けます。
>>42 サンキュー!
買ってやって見る。
ただ、ビニ焼けクリーニングは順調に進んでいるよw
超音波洗浄とその後の界面活性剤洗浄(3度ほど必要)で、少しずつだけど確実に雑音は減少している。
ビニ焼け盤のクリーニングの可能性として
超音波洗浄→界面活性剤洗浄あるいは重曹による洗浄→超音波洗浄→界面活性剤洗浄あるいは重曹による洗浄→・・・
でもビニ焼け盤のクリーニングが可能かも知れない。
アルコール・ボンドパックの場合
盤面へのアルコール塗布後の木工ボンド塗布は、
無水エタノールを使用した場合は良く貼り付くが残留物の量が多すぎて、剥がしたあとの処理が手間。
消毒用エタノールを使用した場合は貼り付き力がイマイチ。
次に、消毒用エタノールを予め木工ボンドと混合したモノで効果を見るつもり。
それから木工ボンドをそのまま使用した場合には、ボンド自体の濃度が濃い過ぎるかも知れない。
水で2倍くらいに薄めたボンドを使用した方が良いかも知れない。
>>44 ポリビニルアルコールと木工ボンドとアルコールの混合物でどうぞ。
せっかく特許を探し出してきましたから、もったいないですよ。
HumminGuru 届いた。
思っていた以上にコンパクトで収納楽々。
土曜日にクリーニング→プレーヤーで試聴予定。
無水エタノールをレコードに塗布してから糊や木工ボンド
糊や木工ボンドにアルコールを混ぜたもの
共に「アルコールの湿布」とするならば、レコードからにじみ出たものの軟化はより良く進むね。
8時間程度乾燥して剥がして除去、更に超音波洗浄処理のダブル効果で、高確率でレコードからにじみ出たものが効率よく取れるね。
>>42 重曹使ってみた。
たしかに酢酸などの除去効果はかなり大きい。
ただ、あとにナトリウムが残留する。
この除去にも一手間いるね。
>>45 >13,14,15の事?
ちょっと確認してから試してみる。
ポリビニルアルコールは注文して届いた。
HumminGuru 初使用してみました。
Mtコンディションで購入した中古LP
Autoで超音波洗浄5分+自動乾燥
マニュアル通りに精製水400ml使用
見た目はかなり綺麗に洗浄出来ている
同じく見た感じではシッカリ乾燥している
HumminGuruを1回使用しただけなので完璧な無音とまではいかないけれど、聴いていて気になるような雑音はほぼ落とせていると思う。使用後の排水にも埃が浮いていたから洗浄効果は間違い無くあると思います。
何より手間がかからないので、これからは洗浄してから聴くっていうルーチンも悪くないかもw
使い込んで気になることが出てきたらまたレポします。
>>50 ポリビニルアルコールの洗濯糊。150円以下で買える。
>>49 そういうことだから、
重曹で中和して、中性洗剤と超音波、
または中和せずに中性洗剤で超音波かけた後、水道水で超音波、そして大量の水道素手すすいで、
イオン交換水で水道水を洗い流すという手順がいいと思う。
クラウド・ファンディングに投資してれば安く手に入ったのに
>>54 ナトリウム粉末は中性洗剤ではダメだろう。
ここは再びアルコール・ボンドパック。
これで除去したあと、盤上に残留する酢酸等を洗剤で洗い落とすのが良いかと。
いずれにせよ、アルコール・ボンドパックでビニ焼け盤を鑑賞に堪えるレベルまで雑音減少させることが可能なのは確かだ。
手持ちの35枚のビニ焼け盤が楽しめるようになるので、大変嬉しい。
これはVPIでは無理な話だろうと思う。
>>51 製品としての完成度は高そうだね。
汚れの少ない盤ならそれで十分洗浄効果ありそう。
汚れがヘビーな場合は、浮き上がった汚れの再付着の問題が発生しそう。
超音波水槽の排水容器がプラのようだし薬品に弱そうなのが心配だね
マニュアルには精製水の使用とだけ記載なので、アルコール投入を想定してない時点で、クリーニングは浅い
HumminGuruは手軽さに引かれてクラウドファンディングで購入しました。精製水も400mlですむし全自動だからいつでも気軽に洗浄する気になれますw
どぶ漬け出来る超音波洗浄機も持ってますが、大量に精製水使うし場所もとるし手間もかかるしで、まとまった時間がある時じゃ無いと洗浄する気になれなかったんですよ。
状態の悪い盤は、気合入れてガッツリ洗ってから仕上げに使います。
>>62
君の住処はこっちだろ。ここを覗くなよ。
http://2chb.net/r/pav/1633345583/l50 ブラシ、アルコール水溶液などのクリーニングは、方法が確立されていて発展の余地が少ない。
パック方式は多種の添加剤が入れられるので発展の余地がある。
>>57 中性洗剤はナトリウムイオンを流すためではなく、
水に不溶性の石鹸カス生成防止のため。
中性洗剤での洗浄後は、ナトリウムイオン除去のため多量の水道水で洗い流して、
イオン交換水でトリートメントというのが望ましい。
ピアノの先生から大量のレコードをいただいた。
一枚ジャケットを開けてみると、内袋に液体状の物がついていた。
盤面に白いビニ焼けは見えなかったが、カビのようなものがついていた。
これは数回パックすれば簡単に取れるが、
収納に新品の内袋を買わないといけいない。
PP(ポリプロピレン)製がほとんどが、
グラシン紙の物は高価ですねえ。
グラシン紙 W508×H380mmの大きさを購入しようと思いますが、
どうやって作ろうかな。
>>63 アホが
ボンドははるか昔からダメだという事は確立されてるんだからお前1人が頑張ったところで意味がない
消えろカス
>>66 ヒス汚君、君のオーディオシステムを聞きたい。
さらに、ここは君のいる場所ではない。
>>66 一応アルコール・ボンドパックでビニ焼け盤が使えるようになっている。
他の方法ではダメだろう。
現在、アルコール・ボンドパックの効果の上限を確認中な訳で。
ヒス夫は実験しないから信頼性がない。
ボンドパックdion君、ワッチョイスレで自演できなくなってここで1人芝居ww
馬鹿は消えろ
自分のことを消えろと言っている。
本当の馬鹿はコイツだろう。
>>69 ヒス夫はヒストラーと呼んだ方がいいのかな?
>>66にヒス汚が書いてあるが、ダメだと確立されている文献などを紹介してほしいし、
現にここではボンドOKという事例と改良を書いているのだが、
過去に縛られていて恥ずかしい人だね。
総重量300キロ超! これが 4,500万円のレコードプレーヤーだ!! techdas air force zero
ダウンロード&関連動画>> ブラジルの古本屋さんで高額買取レコード探し!/ Cacando Vinis raros em sebos do Brasil
ダウンロード&関連動画>> >>66 Cleaning Your Old Records with Paper or Wood Glue
ダウンロード&関連動画>> これが証拠だ。一聴にしてわかる。
>>66 Does Wood Glue REALLY Clean Vinyl Records?
ダウンロード&関連動画>> >>78 なんの証拠だ馬鹿がw
お前みたいな馬鹿なだけなのを証拠だとかマジ笑えるわ
これにレスすると別スレの二の舞になるんでやめようね
ワッチョイを毛嫌いしてる以上このボンド馬鹿は一人で自演してるだけだからw
広島のdion君だとバレてるしw
>>78 そうだよなぁ。
ボンドパックなら、それくらいの効果は簡単に出せる。
オレのやってるビニ焼け盤のクリーニングでも、他の方法では効果が見られなかった効果をボンドパックなら出せる。
>>85 クリーニング新参かな?
1970年半ばぐらいからレコード好きの上司に木工ボンドパック行っていたと聞いたよ
俺は2000年ごろにこの上司に教えてもらってから木工ボンドパックをしている
>>80 ヒス汚は、なんと!、
耳なし芳一か?
あんた、オーディオをやめた方がいい。
だめだこりゃ
こいつらがセットで来ると場所変えようがどこでも荒れるわ
>>86 1975年の少坊の頃からオーディオやってるけど
当時オーディオ雑誌にボンドパックやら何やら
いろんな奇々怪々なクリーニング方が紹介されてたよ
それらを真似て何枚の大切なLPをダメにしたかw
当時は洋楽でも国内盤で2,500円したから
少坊の俺には宝物だった
それ以来オーディオ雑誌を信用していないよ
でも当時は専用の製品も売られてたんじゃないか?
俺もボンドパックは昔から知ってたが一度もやった事ないな
>>90 >ダメにしたかw
もうこれで解りますよ、不器用でコツを掴む前に結論をだす人物とねw
俺もボンドパックは結構やってるけど、それが原因でダメにしたレコードなんて・・
覚えてる限り一枚もないけどなw
荒らしてるのはボンドパックとか言ってる広島のdion君だけだw
>>91 今でもオーストラリアで製品があるけどね。
私も中学校の時はがせなくなったけど、今持っている技術で、残ったボンドをはがせたと思う。
レコードは捨ててはいけないね。
>>93 レンタルレコードには必須でした今も持ってますよ
ボンドで失敗しちゃったブキッチョさん乙乙
諦めないで捨てレコで練習練習
逆にどうやって失敗に至るのか
具体的な手順を教えて欲しい
先日、ヤフオクで落札したLPを洗浄した。
LPはキングレコードGT1018「展覧会の絵」「シェエラザード」の徳用盤。
110円で落札、値段に見合って汚れがかなりあった。
カビが彼方此方にあって外袋もよれよれ、「展覧会の絵」をプレーすると雷のごとくノイズが出てくる。
弱アルカリ界面活性剤洗浄をするとドンドンノイズが減る。
3度の洗浄でほぼ新品並みに成る。
指揮者が、ウラディミール・ゴルシュマンとマリオ・ロッシと言うマイナーな存在。
その為に前の持ち主はあまり使用せずに放置したらしい。
演奏はザッハリッヒな印象。「展覧会の絵」は30分22秒、「シェエラザード」は40分26秒と、快速演奏。
ただサウンドはCDでの空虚感とは縁の無い中身の詰まった物。
やはり音楽芸術を楽しむならアナログで無ければ。
当然内袋も外袋も新品に交換。
レコードのクリーニングのスレに通って良かったと思う。
こんな痛んだLPも蘇らせることができるのだから。
>ノイズがとれたから良しと
ノイズ除去のためのクリーニングスレぢゃないですか
いけませんか
>>107 アルコールを使わないクリーニングなんて、ノイズばかりに気を取られている初心者ですよ
比較する対象が
汚れたレコード
洗剤で洗ったレコード
これがそもそも間違っているんですよ
正しくは
元々の音質(レコード以外の音源でカセットテープやCD等)
〇〇で洗浄したレコードが元の音質にどれだけ近づけるか
この比較をしないとダメなんですよ。
サシスセソやタチツテト等音声波形に汚れが詰まった部分を取り除いてこそ真のクリーニングになるわけです
プチプチ音の有無だけに注目しているようじゃ初心者と言う事です
壮大な勘違いしくじり先生
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
キタキタキタキタ━━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━━━キタキタキタキタ━━━━!!
>>114 >元々の音質(レコード以外の音源でカセットテープやCD等)
>〇〇で洗浄したレコードが元の音質にどれだけ近づけるか
これもねえ、難しいよ。
カセットに録音したものは音質が変化しているし、
CDはリマスタリングしていますからね。
リファレンスにするのは考えものですよ。
>>117 80年代のCDもミュージックテープも所有している側からすれば問題無いのです
その人はね
そゆうのどーでもいい、つか
近づいたとかまだ違うとかで一喜一憂
メディア変われば音ガラッと変わって当たり前
ちうことのわからない人みたいです
おっと
そのわかってない人
>>114,118ID:T1tjS+kj ね
>>119 >>120 リマスタリングした音源は、その時点のメディアなら同じ音なのを知らないようですな
ちなみに80年代の音源はレコードもCDも同じものがやたらと多いんですよ
ミュージックテープもね
いつの間にか音源の話にすり替えちゃってんじゃんよシレットと
>>114 >元々の音質(レコード以外の音源でカセットテープやCD等)
誤解している。
CDには元々の音質は入らない。
カセットテープは、どうやら入る音に限界があるようだ。
元々の音質を確認したけりゃ、そりゃ綺麗でノイズの無い未使用のLPかオープンリールテープでしょw
CDの音は、元々のサウンドの基本音が出たりでなかったりで、空虚な音になっている。
カセットテープは特性がフラットでは無く、デジタルサウンドよりかなりマシだが、入りにくい音があるらしく、少しけばけばした音になるようだ。
ただ、これはマクセルのUR-60Mでの確認なので、その他のより性能の高いカセットテープがどうなるかは未確認。
因みにUR-60Mは音楽・講習・語学学習用となっている。
音楽用カセットテープや、ハイポジでどうなのかは、近いうちに確認するつもり。
かなり以前、バルビローリ/VPOのブラームス第三シンフォニーのLPが気に入ったので、カセットテープも購入したけど、
カセットにはLP並のしなやかなサウンドが入っていなかった記憶がある。
>>124 その件はよくわかりますよ
ただね器に入る入らないの話ではなく、サシスセソやタチツテト等音声波形に汚れが詰まったレコードと全く無縁なCDやカセットとの比較の話ですからね、勘違いは困りますよ
アルコールを使わないクリーニングなんて、ノイズばかりに気を取られている初心者ですよ
比較する対象が
汚れたレコード
洗剤で洗ったレコード
これがそもそも間違っているんですよ
正しくは
元々の音質(レコード以外の音源でカセットテープやCD等)
〇〇で洗浄したレコードが元の音質にどれだけ近づけるか
この比較をしないとダメなんですよ。
サシスセソやタチツテト等音声波形に汚れが詰まった部分を取り除いてこそ真のクリーニングになるわけです
プチプチ音の有無だけに注目しているようじゃ初心者と言う事です
よく読んでない人がいるようなので再送しておきます
>>127 どんなシステムで音楽聞いてるの?
使用してるのがコンパクトスピーカーなら、話にならないんだけど。
>>127 それって、トレーシング歪や内周歪なのでは?
トーンアームの微調整や、針先の摩耗、
もしくは、カートリッジを変えるとか、
丸針、楕円針、ラインコンタクトでも結構変わるから、
ピックアップ関係などを再検討してみるとかした方がいいのじゃないの?
その前にタ―ンテーブルが水平になっているかも再確認してみた方がいいと思いますよ。
>>133 で、どんなシステムで音楽聞いてるの?
10cmフルレンジスピーカーで聴いてるなら、ヤフオクで大きなスピーカーを落札することをお勧めします。
>>133 洗剤ではだめだとかでは、
あなたはクリーニング方法を書いていないから、
返答は別方向になるのですが。
全然クリーニング方法を書いていないのに「低レベルの話」に片づけられても困ります。
ID:T1tjS+kj
人の話を聞いてない、というか
すり替えてる、というか
知らんぷりなので再掲
壮大な勘違いしくじり先生
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! >ID:T1tjS+kj
キタキタキタキタ━━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━━━キタキタキタキタ━━━━!!
わけワカメの自論を書きちらかして他者を低レベル呼ばわり
結局コソコソ逃げちゃったの?
T1tjS+kj
>>128 ほか
自分の方法が最高で他はダメみたいなことを言う人が多いんだよねここ
>>139 にもかかわらず、方法を開示しない人が多い。
>>139 そうでもないよ。
自分がやってるクリーニング方法は、ただ、今やってるだけで、自分自身から離れられない属性ではない。
今やってる方法より優れたものがあれば、そっちに乗っかるよ。
>>42 重曹の使い方だけど、そのまま水に溶かすと、盤に広がらない。
界面活性剤を少し混ぜるべきだと思う。
>>143 レコードをそのまま重曹水に漬けるというのを想定しています。
私は、提案しているお相手に重曹を使う中和の方法を教えただけであって、
私自身は重曹を使わない。
中和は水酸化ナトリウムが一般家庭では入手しずらいので重曹を提案しただけです。
やるとしたら中性洗剤+重曹に漬けて水洗いですね。中性洗剤は界面活性剤ですから。
まだ実験はしていないけれども、
文献を漁った結果、ビニ焼けの物質が可塑剤だけではないとわかったので、
化学的見地から別の方法が有効とわかったのでそちらをテストする所存です。
>>144 漬け置きかぁ?
これまでは重曹+弱アルカリ界面活性剤を盤に塗ってブラッシングをしていた。
これでもかなりの効果はあるよ。
重曹を利用すると、界面活性剤では除去出来ないモノが除去できたりする。
ただ、今取り組んでいるビニ焼け盤だと、重曹でも除去出来ない雑音がある。
おそらく重曹水に漬け置きしても変わらないはず。
ピンローみたいな高周波発振器を
浅くした湯船のぬるま湯で使ってますが
湯の量はかんけいあるんでしょうか発振器
>>146 漬け置きと言っても、超音波洗浄です。
ビニ焼けは重曹などでは物性上落ちません。
>>147 あります。
超音波振動子ならば、電力は一定ですので、相手の媒質量が多くなると超音波の量が小さくなります。
お前らようオーディオマニアなのに定在波って知らないのぉ?w
超音波にだって定在波はある、ていうか洗浄解説してるようなところには
ちゃんと書いてあるはずだ
>>152 33cmの金属製たらいか、ボウルを買ったよ。
ちょうどよい大きさ。
金属製ということが大事なのでしょうか
ダイソーとかではプラならありそうなんですが
>>154 プラでも構わないけれど、超音波を吸収するよ。
金属製だったら超音波を吸収しないし、反射するから効率的。
金属製は高価だもんね。2500円以上はする。
近所のDIY店にいったら33cmのステンレスのボウルが850円で売っていたから買ったけどね。
昨日もビニ焼け盤のクリーニングを行った。
アルコール・ボンドパックで大まかなノイズ除去が終了した段階で、最後の背景ノイズの除去に取り組んでいる盤がいくつかある。
背景ノイズの除去は、パックでは無理かな?
弱アルカリ界面活性剤洗浄を繰り返すとノイズが減少した。
背景ノイズの原因は、おそらく溝の側面に可塑剤とされる異物が小さな粒子状態で分布して付着しているのだろう。
この除去には、界面活性剤洗浄が効果を上げるだろう。
ただ、超音波洗浄で、異物を浮き上がらせてから界面活性剤洗浄をすればより容易に除去出来るはず。
今日はそれにチャレンジするつもり。
盤は講談社のステレオ世界音楽全集ビニ焼け盤の中のメンデルスゾーン「イタリア交響曲」他、ショルティ/イスラエル・フィル
>>156 モノタロウご紹介ありがとうございます
これに盤を水平に沈めるとして
ピンローのような発振器はどのようにセットすべきでしょうか
私は使っている超音波振動子は
Amazonで
音波洗浄機 Blumway
と検索してください。
ケーブルが邪魔ですけれど。振動子を底に沈めているだけです。
風呂の温度と同じお湯に中性洗剤を入れています。裏表10分ずつ。
レコードスプレイなどの過量に堆積した帯電防止剤を除去しやすくなります。
そのご、多量の水道水で洗剤を洗い流し、イオン交換水でゆすいで感想しています。
くれぐれも50℃以上にはしないでください。
レコードの塩ビ軟化点は約55℃以上です。確実に歪みます。
そうそれです音波洗浄機 Blumway同じやつピンロータイプ
>裏表10分ずつ
ならばもう1個買って両面一気にと考えましたがどうですかね
>>160 タライの方を買って、
ブックスタンドを利用してやるしかないですねえ。
レコードの穴に芯棒を差し込んで
ブックエンド二つに橋渡しをして、芯棒がブックエンドから落ちないように工夫する。
私ならブックエンドに事務用の洗濯ばさみみたいなものを片方2個づつつけて、落っこちないようにし、
その間に芯棒を置く。レコードが簡単に回るようにする。
Amazonで検索
ミニ洗濯機 超音波ミニ洗浄機 小型洗濯機 30分 調整可能 省エネ コンパクト 携帯便利 家庭用 寝室(ホワイト)
この手のタイプを買って、水流を作る。
たしかこれは40kHzでBlumwayは50kHz。2つの周波数が合わさるのでいいかも。
上手に設置すれば水流によって、勝手にレコードが回るとか。
わざわざ、レコードを回転させる機械は作る必要なくなる。
この2タイプの超音波振動子を組み合わせたブログか個人のHP内の記事にありました。
探してみてください。
タライとブックエンド、芯棒というのはわたしのアイデアですのでうまくいくかはわかりません。
芯棒なんて嫌だとお思いなら、代わりにレコードレーベルプロテクターを使ってもいいでしょう。
安くレコードの超音波洗浄が可能になりますので、ブログを探して参考にしてみてください。
超音波洗浄で流水かよw
静止した水でないと効果でないよ。
超音波洗浄の水の温度は、お湯よりも常温、常温よりも冷水が効果がある。
油分を落とすならお湯+洗剤
キャビテーション効果を上げるなら冷水
というように2つの方法がある。
ステンレス水槽タイプの超音波洗浄機では水の温度に注意する点がある。
振動子はステンレス水槽にスポット溶接+接着剤で取り付けられていて、水槽に入れた水の温度に馴染まないまますぐに作動させると、
スポット溶接と接着剤の剥離に繋がるらしい。(中古の水槽を見ると振動子がある部分にリング状の金属疲労が現れる)
給湯器などでお湯を入れすぐに作動させる事を繰り返すとこうなるらしい。
お湯、ないし冷水を入れた場合、振動子が温度になじむまで10分以上は放置したほうが良い。
冷水の場合はステンレス水槽に結露が発生する確率が高いので、ステンレス水槽直下に電子基板があるタイプは水滴が垂れないよう工夫する必要がある。
分かってると思うが、結露発生はその室温よりも水温が低い場合に発生。
そしてステンレス水槽に水を全く入れないで作動させると瞬時に振動子が焼きついて壊れる。(怖くて試したことは無いが、そういわれている)
(その単体の「Blumway」とやらの振動子では関係ないとおもうが)
講談社のステレオ世界音楽全集ビニ焼け盤の中のメンデルスゾーン「イタリア交響曲」他、ショルティ/イスラエル・フィルのクリーニング
超音波洗浄→弱アルカリ界面活性剤洗浄の流れを二度行った。
超音波洗浄で異物を浮き上がらせてから界面活性剤洗浄をする事によって、確かにクリーニング効果は上がったが、まだ取り切れない異物がある。
溝の底に異物が残留している。
この完全除去が出来れば、クリーニング完了となるが、まだ手間がかかるようだ。
ただ、クリーニングによる音質改善はめざましく、クリーニングをする度に倍音成分が加わって行き、素晴らしいサウンドを再現するようになった。
ショルティ/イスラエル・フィルのメンデルスゾーン「イタリア交響曲」は、かなりオンマイクで収録されていることが明らかと成る。
これは素晴らしい録音だ!
改めて、講談社のステレオ世界音楽全集の音質の素晴らしさに簡単する次第である。
と同時に、ビニ焼けしやすい装丁が残念で成らない。
この全集、何としても音質を復活させたいという気持ちが高まった。
今回のクリーニングでは、超音波洗浄に重曹と弱アルカリ界面活性剤の混合溶液を使用した。
そのために超音波洗浄の効果が高まり、超音波洗浄による残留がかなり減少している。
超音波洗浄の後の弱アルカリ界面活性剤による洗浄で、浮き上がった異物(可塑剤とされる)が除去され、サウンドはよりリアルに成っていった。
盤表面の元々の溝の形が、超音波洗浄や弱アルカリ界面活性剤による洗浄で影響を殆ど受けていないと考えられる。
これなら異物を全て除去すれば、新品同様のサウンドを獲得出来るはず。
ただ、ビニ焼けによる異物の残留は、溝の最低部分に存在するようだ。
この除去にはボンドパックでは出来ないだろう。
弱アルカリ界面活性剤とデンターシステマによるブラッシング以外に除去の方法が無いはず。
ただ、溝の最低部分の異物を除去出来れば、ビニ焼け盤の完全復活と成る!
>>162 静止だけど、お湯と中性洗剤は、盤面がピカピカになって、
水道水で洗い流すと強烈に水をはじくようになった。
>>165 パックで以前よりもビニ焼け物質(可塑剤ではない)を除去できる方法を見つけたが、
忙しいから12月に入ってきてからだな。
手軽にパック液を作る方法は、100mlのメモリ付き容器を買ってきて
https://www.monotaro.com/g/00342841/?t.q=%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E4%BB%98%E3%81%8D%E5%AE%B9%E5%99%A8 PVA洗濯糊+木工ボンドを30ml+30mlを入れて,1分シェイク。
次に無水アルコールを30ml入れて、ゲル状が無くなるまでシェイク。
疲れるから、休憩を取りながら、何度もシェイク。
一晩明けたら、透明になっているが、ゲルみなっていないかを確認するために攪拌棒で確認。
会社に行く前にシェイクw。
そんな感じで実験用のパック液を作るw。
面白いよw。
木工ボンドはアラビックヤマトのようなPVA糊に変えてもよい。
みなさんの考えているクリーニングてなんですか
ぼくは曲間無音部や小音量部分で目立つパチパチノイズの除去を狙ってるんですが
そうじゃない見た目の盤面ピカピカでオッケーの人も混ざってませんか
だからクリーニングの方法手段でぶつかり合っちゃうんじゃないかと
>>168 ピカピカは異物が盤面に無くなったというひとつの指標であって、すべてではありません。
何度も書いていますが、ヤフオク!で落札したレコードがひどかった。
見た目は何ともないが、針飛びとノイズがひどく、プレイ後に針先を見たら、赤い粉がこびりついていた。
パック液などを使っても針飛びだけは収まらず、システマブラシと中性洗剤でブラッシングし、ベンコットで拭いたら、白い粉が出てくる出てくる!
乾燥後に聞いたら、針飛びはなくなったが、ぼそぼそノイズは無くならない。今度は白い粉が針先に着く。
システマでブラッシングというのは、どうせ人の手でやるものだからブラッシングがまだらになるのは必須。
また、毛先が細いからと言って、音溝の底に達しているとは考えにくく、
結局は超音波の方が手でブラッシングするよりも均一で、音溝の底深く物理的に付着物を除去できると考え、安く手に入るBlumwayを入手したわけです。
つづく
つづき
幸いにも洗面台はレコードが入る大きさだったのでレーベルガードを付けて、ひもでぶら下げてドブ付け超音波洗浄。
最初は水でやったが、思わしくない。ポップノイズは少なくなる感じはあった。
そこで、レコードに付着しているのは、帯電防止剤の界面活性剤なので、中性洗剤を使おう。
ついでに洗面台からお湯が出るからこれも利用しようと思い付き、実施後、
水道水ですすいでいたら、強烈に撥水するようになった。ピカピカになった。
イオン交換水ですすいだ後、乾燥後、再生したら、結構ノイズはとれたが、ぼそぼそノイズは取れていない。
PVAパックでもぼそぼそノイズはそのまま。はがすときに強烈に静電気を帯びるようになった。
あの針飛びの原因であった赤い粉や、白い粉は帯電防止剤だろうと確信した。
このレコードは大量にレコードスプレーを吹付けたのだろう。
帯電防止剤はカチオン性の官能基を持っているから、アニオン系の中性洗剤と電気的に結合し、超音波のキャビテーションで除去やすくなったのだろうと思う。
しかし、ぼそぼそノイズはアルコールや水(PVAは水に溶かしている)ではぼそぼそノイズの付着物は溶解と除去はできないと実感した。
アルカリの電解水でも洗ったのだけれど無理。
この過去スレを読むと白い結晶物があり、アルカリでは溶けないという書き込みがあった。
この正体は、色々他の文献を読んでほぼアタリをつけた。物性を調べたら、水には不要。アルコール、テレピン油にわずかに溶けると書いてあった。
溶媒はないのかとあきらめかけたら、他の分野、分析化学の文献に溶媒が書いてあったんだよw。溶けないとH-NMRで測定できないもんなあw。
しかし、アマゾンから購入できるとは言え、一般家庭では絶対無理。近所からも苦情が出そうなもの。
代替可能なものはないかと探したら、スーパーにあった。これは使えると思った。分析化学以外の文献でも私の考えを指示している。
今は忙しいのでできないが、パック液に混合できるものなので12月になったら、実験できる。楽しみ。ではまた。
レーベルって水に濡れたくらいでは
はがれないでしょ
>>168 レコードのクリーニング法なんてのは、ひとつに絞る必要は無いよ。
色々やれば良いんだよ。
その中で何が効果的かを選択すれば良い。
講談社のステレオ世界音楽全集ビニ焼け盤の中のメンデルスゾーン「イタリア交響曲」ショルティ/イスラエル・フィル
録音は1958年と判明!
複製しても著作権に触れない。
できればひとつのベストな方法で続けたいんですけど
ぼく的には超音波?高周波?@お風呂場かなあ
>>173 剥がれない。
しかし、文字が消える可能性がある。
>>175 当時の録音はマルチマイクではなく、
デッかツリーで収録かな?
だとしたらナチュラルな音場、雰囲気かもしれない。
講談社のステレオ世界音楽全集ビニ焼け盤の中のメンデルスゾーン「イタリア交響曲」ショルティ/イスラエル・フィルのクリーニング
一応使い物になる状態にはできた。
ノイズが楽音を邪魔することは無くなり、沸きたつサウンドを楽しめる。
ノイズが気になる状態から改善した方法として、アルコール洗浄と超音波美顔器による超音波システマブラッシングがある。
アルコール洗浄は、ボソボソノイズ低減に役立ち、その後に残ったピチパチノイズの除去に超音波美顔器が威力を発揮した。
ただ、その後に無傷の新品同様盤を試聴し、雑音状況の違いを思い知らされた。
盤はサバリッシュ/ドレスデンのシューベルト第九。
ほぼ雑音無しで、第壱楽章に2個所パチノイズがあるだけである。
針を下ろした瞬間、シーーーーンと静まりかえった状態は、ショルティのイタリア交響曲には無い。
やはりビニ焼け盤のノイズゼロの洗浄は無理かも知れない。
おそらく無理だろう。
ただ、使い物になる状態にできるだけでもいいか?
何しろ録音は素晴らしく、演奏も魅力的な物が多い。
>>183 海外発送(おそらく中国)なのに送料安いんだな
送料だけで1マソくらい普通にボッタくるが
もっともaliに同じのがたくさん出てるな
ボンドパックに熱中している人もいるんだな。
その情熱がうらやましい。
俺も昔は水洗い洗浄に情熱を燃やしていたんだがバキュームマシンを買ったらあまりに楽なんで今までのクリーニング方法は全て捨ててしまった。今はアルコール&システマで楽々クリーニング。
楽ではあるけど厄介な盤には10分位クリーニングする時もある。
1000枚はクリーニングしたかなあ。
邦盤はバチバチでもノイズレスにするのは簡単。
だけど洋盤はそもそも盤質が良くないし扱いが雑だったのか溝が痛んでいるのも多い。
ビニ焼けのクリーニングはボンドパックが期待できるね。
>>185 >>183 >海外発送(おそらく中国)なのに送料安い
送料¥1000
たぶんですが、それ逆フェイント
お、安いじゃん、、となっちゃいますから
それとアリの値段にだいぶのっけてるとか
そうであってもレコ洗機としてけっこう理想に近いかも
>>186 ブラッシンングとバキュームでクリーニングできるディスクをお持ちなのでうらやましい。
自作のレコード洗浄機第3弾!USBミニ超音波&洗濯機で試作
投稿日:2019-03-24 更新日:2021-01-24
https://shop-ryota.jp/ryotablog/record-cleaning-3/ 使ったことはないが、水流モードと超音波モードを交互にするんだなあ。
>>188 aliも安いね
めずらしく送料無料の所がある
>>181と同じ所かな?
ブラックフライデーのセールでもっと安くなるぞ
>>184 1980年だよ。
サバリッシュ/ドレスデンのシューベルト交響曲全集!
1966年録音だから、今複製しても著作権には触れない。
輸入原盤使用と書いてあって、音質に期待したけど、思ったほどには音に滑らかさが無かった。
第九は100Hz以下のエネルギー不足で、折角の貫禄ある演奏なのに感銘がイマイチ。
音質を改善して再発してほしかった。
世界文化社発行の「世界の名曲」から、メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲をクリーニングしてみた。
こちらは1969年発行と古いが、講談社のステレオ世界音楽全集とちがって、ビニ焼けは一切していない。
元の持ち主が何度か使用したらしく、若干の雑音が乗っていたが、2度の弱アルカリ界面活性剤洗浄でノイズは気にならないレベルに。
演奏は、ハイメ・ラレード(vん)ミュンシュ指揮ボストン交響楽団。
問題は、レコードの元々の音質。
周波数特性にかなりのバラツキがあって、音に潤いが欠けている。
EQで調整すると、ヴァイオリンの生きの良いサウンドが浮き上がってくる。
ハイメ・ラレード、こんな風に弾いていたんだね。
それにミュンシュ指揮ボストン交響楽団はかなり攻撃的な演奏をしている。
時々伴奏の域を逸脱してヴァイオリンの音をかき消す程の音響がオーケストラから発している。
当時のRCA録音はボソボソした印象がある。
友人宅にはこのシリーズのレコードが結構沢山置いてあって、ライナー/シカゴ響のベートーヴェン「田園」なんかは何度も聞かせてもらった。
今の技術ならもっと良いサウンドに調整できるのに、このまま歴史の中に埋もれてしまうのは勿体ない。
世界文化社発行の「世界の名曲」から、モーツァルト:ジュピター交響曲(ライナー/シカゴ響)もクリーニングしてみた。
これもビニ焼けしていないので、2度の弱アルカリ界面活性剤洗浄でノイズが気にならないレベルに。
これも音質に魅力が不足し、演奏の実力が音に表れていない。
EQで調整するとライナー/シカゴ響の演奏の如何が伝わってくる。
よくライナー/シカゴ響の演奏は楽譜に忠実と言われていたが、必ずしもそうでは無いことが明らかに成る。
こんなところでテンポを落としている、とか、ここの音を伸ばしている、と言うのがハッキリ認識できるようになる。
折り目正しい演奏である事には変わりは無いのではあるが。
超音波高周波発振器はいろいろありますが
問題はLPがうまいこと浸かってくれる水槽浴槽じゃないですか
なんかありませんかいいの
アマで紹介していただけたら
私はブラッシングに抵抗感があります。
理由は、埃は砂粒のような小さい固い物質もあるので、
それが磨き粉のように傷をつけるのではないかと危惧しているからです。
その危惧を回避するために、
しかもムラなく除去するために、糊パックと超音波洗浄をしています。
>>199 水の容積に対して何W以上が危険でしょうか?
>>195 >演奏の実力が音に表れていない。
そのレコードの実力じゃね
家に有る
CBS/SONY
ワルター/コロンビアCSOの第九と
セル/Cleveland Orchestraの新世界からの組合せ限定盤
はっきり言って、CDの方が全然いいよ
SONY、失敗したのってくらい
>>201 どうかな?
モントゥー/ロンドン響のチャイコフスキー「眠りの森の美女」をCDとLPで聞き比べたときは、断然LPに軍配が上がった。
>>201 今、パソコンオーディオでワルター/コロンビアSOの第九聞いてるけど、アナログに慣れた耳ではCDの音はおかしい。
やたら擦れる音が出てくるけど、中身のない音になっている。
このCDの音が良いと感じるのか?
>>203 そのCD
ソニーの発売時期の違いで、結構音違うよ
マルチすいません
超音波洗浄機
中国から来るんだろうか
もう1週間にもなるのにまだ来ません
次の日に来るアマゾンに慣れちゃうと
もうもどかしいかぎりだわ
はよ来い洗浄機
来たらレポします
>>205 結構待ちましたよ。
しかもこのご時世ですから。
今日は、それを使って、カッターシャツの袖を洗ってみました。
結構、汚れが落ちる。
amazonで以下の文章検索
天馬(Tenma) 書籍収納ボックス クリア 文庫本サイズ
幅14.5×奥行45×高さ17cm 文庫本いれと庫 文庫本サイズ
これ、樹脂製だけど超音波洗浄用途にサイズはベターじゃないか?
レコードの穴に箸か、棒を橋渡しにするとかできるのじゃないの?
水流と超音波機とBLUMWAYを片方ずつに置いていけば、定在波防止にもなるし、
水流時にレコードを回転してくれると思う。
だれかやってちょうだいw。
このスレの住人さんはオーディオというか
レコード洗浄も趣味の人になってるねw
>>205 アマゾンでもマケプレの中国業者なんか忘れた頃に着くぜ
まあ、ひと月ならマシな方とでも思っとくといい
洗ってくれ
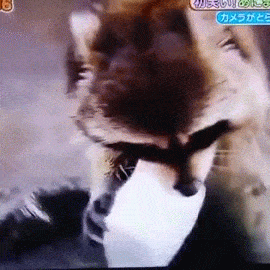
>>207 30センチのLP半身浴ではなく
全体が浸かる深さが欲しいとこです
>>201 ライナー/シカゴ響の録音当時は真空管を使っていた。
何らかの理由で当時のRCA録音は特性にバラツキがあって、密度の低い音質になっている。
CDも同様に密度の低いサウンド。
密度の高いサウンドは1960年代後半あたりから実現され、1970年代は良い録音が多い。
デジタル録音になって音の密度が下がった。
CDでガッカリしたのは、低音の音階が表現できていない点。
それに気付いたのは、ケンペ/ミュンヘン・フィルのブラームス第2番をCDとLPで聞き比べたとき。
第1楽章のダンスのような旋律に弦バスがピツィカートでリズム伴奏する所。
LPではハッキリ聞こえるのにCDは不明瞭。
CDは音楽芸術を感銘深く伝える器では無い!
レコードクリーナーをシュとした時の匂い
もう何十年も変わらないと匂いだこととふと思った
>>213 レコードクリーナーのスプレー使ってたら
細かいゴミを音溝に埋め込むだけちゃうんかいな
ナガオカのスプレーやねたぶん
俺はテクニカのスプレー一応は持ってるけど
ほとんどつこたことないわ
あのスプレーゆうのは
昔のレコード屋さん
お客が自由に盤を取り出せて試聴だってできちゃったらしい時代
購入時のサービスとして目の前でツルピカにしてくれる魔法だったんですかね
オデ誌では早くから警告されてたような
>>212 さらに書き加えると、当時のRCAは値段の安いプレイヤーを想定して、
高音と低音をブーストしていたんですよ。
そうすれば、安いプレイヤーでもHi-Fi調に聞こえる。
しかし高価なステレオセットで聞くとドンシャリに聞こえる。
さらにいうと、RCAはRIAAと異なり独自のイコライザーカーブでLPを製造していた。
こういうことがあるから、CDと音質が異なるのは当然ですよ。
>>211 だったら、私が使っている33cm金属ボウルでしょ。
レコードの直径以下には沈まないし、
超音波振動子にも接触しない。
これは私を含め3回目の紹介だよ。
https://www.monotaro.com/g/03747874/ 超音波振動子は底に沈めるんですね?
そうすると上になったレコードの面はどうなりますか
>>219 ひっくり返して繰り返せばいいじゃないですか。
それすらできないのですか?
セットしてスイッチをいれればBlumwayなら10分で自動で切れるし、裏返してスイッチを入れればいい。
それすら嫌なら、レコードが入るくらいの大きなステンレスのバットを探して購入してください。
そういう発想はないのでしょうか。
理化学実験用品のサイトにありますが、馬鹿らしいほどの高価な値段ですよ。
あとは樹脂製のトロ箱を探すとか、DIY店や100均に行って適当な衣装収納ケースなどを探してください。
洗浄液を振りまいて必死になってブラッシング、
しかも傷をつけないように気を付けてブラッシングという精神と体力と時間を使わなくて済みます。
レコード専用の超音波洗浄機はそれ専用の用途しか使い道がないし、高価であほらしいので、
安く済む方法を私は探しています。
その分だけレコードを聞ける余裕ができますからね。
>>217 実はCDは、出せる音の数が少ない。
だから基本音が出たり出なかったりする。
倍音成分もアナログの半分だけ描写していると見て良いだろう。
だからCDの音はシャープに聞こえるが、安定感とか実在感に欠けて、良く以前は言われていた「デジタルの音は固い」につながる。
以前、専門家と言われる存在が「CDは20kHz以上が描写されないから音が固くなる」と主張していたが、これは間違いで、20Hz~20kHzの中の音が充実していないから音が固く感じる。
>>218 RCA録音に詳しいね。
ただ、現在は録音の特性について調べる機器が存在していて、もう少し詳細が確認できるようです。
ハイメ・ラレード(vn)ミュンシュ指揮ボストンso.のメンデルスゾーン:vnC.だと、うちの装置で確認する範囲だと、特定の周波数がブーストしている。
高音域では確か5kHzのあたりがブーストしていた。
低域では160Hzあたりがブーストしていて、100Hz以下のエネルギーが小さくなっている。
このアンバランスさはCDほど大きくは無いけど、音にややつかみ所の無い印象を生みだしている。
なあ、ちゃんとピュアストアームを使って比較しているか?
折れ的には
CDはコントラストが高いと言っている
写真の方が趣味的に上なので
ところで
超音波洗浄機でも
中性洗剤丸洗いでも
レーベルはどう保護するの?
それとも保護しない?
中性洗剤丸洗い、1回くらいなら、そのまま洗っても大丈夫だったけど
>>225 レーベルガードは取る時に大変やと言いますやん
密着しててレーベルがはがれそうになるとか
そのへんはどうですねん?
>>218 RIAAカーブって元々RCAが開発したんじゃないの?
RIAAカーブ=RCAカーブと認識してたけど
>>226 今のところそれはないなあ。
>>228 イコライザーはCBSの勘違いでした。
>>221 CD初期ならそう言えるかもしれません。
オープンリールから今に至るDSD録音を演奏会主催者に頼んだり頼まれたりして、生録やビデオ撮影をしているのですが、
民生用機器で録音方式の変遷と音質向上は一通り経験しています。
CD発売初期の時代のADコンバーターはオーバーサンプリング、オーバービットからダウンサンプリングした録音はありませんでした。
私がデジタル録音を本格的に始めたのはPCM-F1(+βデッキ)時代はそういう時代でした。
その音質はあなたが言っているような感覚を受けました。
一方で、アナログデッキに生じる二階堂歪(テープとヘッドの摺動ノイズ、テープの振動)の解放があり変調雑音が少なくなり
透明感が増したのが一番大きな収穫だと思います。それが音数が少ないと感じるのでは?
しかし、ADもDAも、オーバーサンプリング、デジタルフィルターや1Bitなどの発達によって音質が改善されました。
SCMS規格のDATは64fs1bitΔΣ変換が主流となり、SBMやハイサンプリングのパイオニアDATなども使用し、
デジタル臭さの減少とアナログの音質にどんどん近づいて行ったと実感しています。
その年代は90年代以降で、そういう技術がCDの音質を向上させたと思います。
CDは初期と比べて音質は向上していますし、ADもDAも進歩していますので、
基音がないとか、音が硬いとかいうようなことはほぼないと思いますし、
最初の固定概念は捨てた方がいいと思いますよ。
20年前はでかいデスクトップパソコンとブラウン管を演奏会場の音響調整室に持って行って、192kHz24Bit録音なんかやっていたりして、
ホールの音響さんが珍しがっていましたよ。この時はようやくアナログに追いついたと思いましたね。
CDにしたらガッカリしましたが、15年ぐらい前から、CDフォーマットへの変換ソフトに良いものができてほぼ満足な状態で、主催者に渡せるようになりました。
録音方式が発達していますから、同じマスターから何度もリマスタリングされた復刻CDなんか出ませんよ。
いまではメインのレコーダーはKORGのMR2000S、マイクはノイマンを昔使っていましたが、自作品マイク使用ですなw。金田式は使いにくい。
横道それてすみません。
CDP+CD黎明期のカラヤンベルリン・フィルの
グラモフォンの田園聴いた時は音が悪いというか
こもった音でこりゃあかんわと思ったよ
CDPの故障かとか配線とか色々確認したわ
1982年頃はそういう時代だったんやね
マスターテープもあんなに音が悪かったんやろか?
>>212 えーと、
もう一度読み返しました。
>CDでガッカリしたのは、低音の音階が表現できていない点。
このCDの製造年月日はいつでしょうか。またはお聞きになったプレイヤーのDAコンバーターのbit数などの構成は?
低音の音階が表現できないのはビット数の少なさから来る量子化歪が原因です。
真空管アンプで経験しましたが、低域の歪率が多きなものほど、迫力感があるが、コントラバスの音階が判別しにくいといった経験がありました。
それと同じようにデジタル録音では低音、特に小音量になると量子化歪が耳につき、基音をマスキングするのです。
試しにDATで16bitの録音で-60dBなどの60Hzのサイン波を録音と、20BitをSBMを掛けてノイズシェイピングした録音をし、
音量をあげて聞いてみたら、すぐにわかります。
16bitはボーーーー。SBMのノイズシェイピングはポーーーーっと全然音が違うのですよ。
もちろん16bitは歪が生じているので、元のサイン派の音と似ても似つかない音でした。
このごろのCDは、ハイレゾのマスターデーターをノイズシェイピングをしてCDフォーマットにしますから、ごく初期のデジタル録音のCDよりも音質向上しているはずです。
すみません。いま編集中なので、レコードのクリーニングの実験、糊パックの実験はできていません。
>>221 さらに付け加えると50Hz以下はバッサリとカット。
>>226 取るときに大変?
誰がそんな事言ってるんだよw
ネジで取り付けるだけだから何も大変な事は無い
それにそのカバーのネジを持てばいいだけだから洗浄の取扱いもよくなる
超音波洗浄も専用のものはレーベルが濡れない様になってるか、ベルドリームだったらそのレーベルカバーのネジ部分を引っ掛けて回転させる
ハンス=ユルゲン・ワルター指揮ハンブルク放送so.のベト5「運命」MS1001をクリーニングした。
評判の芳しくないブラッシングを行った。
行わざるを得なかった。
ヤフオクのハンス=ユルゲン・ワルターセットの中の1枚で、表面が汚れていて、汚れを一応取り去っても音質が芳しくない。
アルコール・ボンドパックをするとボソボソと盛大なノイズが乗った。
超音波洗浄を行うと、さらに針飛び、読み込み不能などが発生。
弱アルカリ界面活性剤洗浄やシステマブラシでも改善せず、やむなくGUM歯ブラシ(やわらかめ)でブラッシング。
溝内の汚れ成分を無理矢理ブラシで書き出して除去!
ようやく針飛びは無くなり、サウンドに少し勢いを増す。
おそらくクリーニング前は溝内に相当の異物(多分レコードスプレーの成分が多量存在していたはず)が溜まっていたはず。
もちろんレコードのクリーニングは、非接触をやりたいが、汚れの状況ではブラシによる掃き出しが必要なモノもあり、今回はその一例!
>>236 この、程度のひどい盤で色々と試行錯誤させてもらいましたよ。
>>236 >非接触をやりたいが
気にせず柔らかいスポンジで、溝に沿ってゴシってやる
オレ
↑の方で超音波洗浄の水は低音の方がよいと書いてた人がいたのでやってみた。
俺の耳にははっきりと優位性が確認できた。 言葉にすると大袈裟になるがヴォリュームを
上げたみたいにクッキリとして音が前に出てくる。 今までは30~35度くらいでやって
たが今日は水道水17度そのままでやった。 でも今までは汚れが落ち切ってなかったって
ことなんだろうか? 昨日までのを聴くと音が柔らかくて大人しい気がすんだが、ちょっと
自分の耳を疑ってもいる。
>>237 だよね。
ヤフオクで落札した盤の中で、状態が悪いものがたまにあって、それをクリーニング効果確認のための実験に利用できるw
元々状態が悪いのだから、ダメになっても構わない。
スポンジもブラシもメラミンも使い放題!
方法が理に適っていれば必ず改善するし。
状態が悪いからとすぐに捨て去るのは勿体ない。
>>235 Amazonでベルドリームのレーベルカバー
を探したがありませんでした・・・
でググるとヨドバシドットコムにはありました
取る時に大変と書かれていたのはAmazonの
レビューでナガオカの製品です
そんなレビューが多数ありです
ベルドリームのを買ってみますね
ベルドリームのレーベルカバー
https://www.yodobashi.com/product/100000001000802178/ 長岡のとどこが違うのかっていうほど同じでしょ
ネットの評判に振り回されてるんじゃないわよ
>>244 ナガオカは黒いねじが短くてもちにくい。
>>247 > ブキッチョ配慮で値段が2倍
こんなことでマウントw
どんだけ残念で情けない人生なんだよw
24時間レコード洗っとけやw
ナガオカの法は初期タイプは黒いねじが短いけれど、新しいタイプはもちやすく改良されている。
旧タイプ
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/267493/ 新タイプ
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/290972/ アマゾンのネジが長い製品
グーグルで以下の文章を検索してください。
MayRecords 新しい LPレコード レーベルカバーセット アクリル防水レコード クリーニング用 ラベルプロテクター
ナガオカのやつはネジ部分に錆防止をしていないので赤錆が出るぞ
買ったら予防しておけよ
ナガオカのネジの材質がわかんないけど三価クロメイトだとすぐに錆びるね
ステンレスに交換するといいかも
アルコール清掃したら、ヒビが入ったとか
そもそも、レコードってアルコールで洗っていいの?
そもそも、アルコールって無水エタノール?
溶けない?
無水エタノールだと、盤面に着いた油脂は取れないから
水分加える?
エロイ人教えて
>>252 ヒビが入ったのはレーベルガードの方です。
勘違いです。
塩ビはアルコールに溶けません。
2年間塩ビをアルコールに付けても変化なし。
変わりに梅を漬け込んだ方が良かった。
アルコールは無水エタノールも範疇に入りますがIPAやメタノールが安い。
毒性と酒税付加を考えるとIPA(イソプロピルアルコール)を私は使っています。
水を付加する意味は水になじみの良い埃除去と静電気を抑えるためです。
水を加える人はレコードがアルコールで痛むという迷信で混ぜているとも言えます。
>>252 レコードは軟質塩ビで
軟質塩ビのアルコール洗浄は基本的にはやってはだめ
ここでやってる人たちは承知の上で自己責任でやってる
アルコール洗浄はたまにやるね。
溝内に細かな汚れが沢山ついて除去しきれない場合とか、汚れが固まって針飛び起こすときとか。
アルコールを塗ってブラッシング、その後拭き取り。
結構汚れが除去出来る。
これで音質が劣化した例はこれまで無い!
レコード盤にはアルコールに溶けない硬質な物質が溝の形を維持しているようだ。
眼鏡用の超音波洗浄機なら持ってるので、メガネの汚れを使って
洗浄のテストをしてみた
超音波といえども脂は相当長時間洗浄しないと落ちない、しかも
単純に落ちるのでは無く、薄く広がり徐々に無くなっていく感じ
そこで中性洗剤を塗ってから超音波にかけてみた、これは効果絶大で
短時間でキレイに脂が落ちる、副次的な面白い現象も見られるようなので
レコードに応用するときには応用が効くかもしれない
>>256 超音波の強さはメガネ用とレコード用は違うんだよ
それと中性洗剤だが、界面活性剤を入れて馴染ませるという意味では合ってるが、中性洗剤には洗剤という不純物が多く含まれてるからそんなことをしたらダメ
するなら相当な濯ぎを行わないよういけないから手間がかかりすぎる
精製水を使うから精製水の無駄遣いにもなる
界面活性剤はドライウェルなんかを少し入れる程度でいい
>>257 最初にぬるま湯と中性洗剤と超音波を提唱したものだが、
あなたは高校などで化学実験を実地でやったことがない人だね。
すすぎには風呂のシャワー、つまり大量の水道水で洗ったのち、
鶴首洗浄瓶に入れたイオン交換水(精製水)で洗えば済むことだ。
100mlも使わない。
この方法は化学実験や分析試験で、実験器具を洗う通常の方法。
私の日常業務の一つだった。
いきなり、石鹸水が付いた器具をイオン交換水で洗うムダな方法はしない。
ドライウェルは使わない方がいい。せっかく超音波で異物を除去したのにまた異物を乗せることになる。
しかも、洗えたかどうかの指標にならない。盤面に水が広がってしまうからだ。
超音波を掛けたのち、水道水で洗剤を落としたら、強烈に水をはじくようになる。
これがレコード面上にあった、レコードスプレーなどの帯電防止剤の有機物や可塑剤、ほこりが取れたことの指標となる。
水道水のわずかな塩分除去のために、鶴首洗浄瓶を使うとわずかなイオン交換水量でまんべんなくすすぐことができる。
>>257 もう一つ聞くけれど、異物を嫌う器具を洗う方法を知らない人みたいだが、
メガネ用とレコード用の超音波はなにがちがう?
>>199を書いたひとのようだが、超音波に詳しいようなので、
>>200の質問にも答えてほしい。
さらに、レコードを破壊するほどの超音波振動子なんか市販されていますか?
だったら、いい加減な憶測を書いてはいけない。
デマになる。
憶測というのは決めつけでは?
ダメージについては超音波洗浄機メーカーのサイトに簡単ではあるけど情報があるし
>>258 >>259 頭悪すぎにも程がある
中性洗剤を塗って超音波洗浄する方がドライウェルよりも異物が多い事も知らない馬鹿だし、ドライウェルがなんなのかも知らないのか無知っぷり
そしてメガネ用とレコード用は超音波の強さが全く違う
少しはググれ低能
それと>199、200は俺じゃない
自分を否定する人は一人だと思い込むアホさ加減も呆れるわ
ピュア板のマウンター諸君
ひろゆきが考える「ストレスフリーに生きるコツ」
https://news.yahoo.co.jp/articles/f7df532ab08e0d01d117582e063bffdc3638fd59
「マインドセットを変えること」
そもそもなぜストレスを感じるかというと、多くの場合は「自分にプライドがあるから」です。
「うまくいく」と思っていたことがうまくいかなかったり、「自分は偉い」と思っているのに軽く扱われるようなとき、人はストレスを感じます。
でも、これって、自分の自尊心が生み出しているんですよね。相手や物事にストレスの原因があるように錯覚するんですが、大元は自分の考え方が作り出したものなのです。
これに気づけないと、「あいつはわかってない。あいつもわかっていない。みんな自分の敵ばっかりだ……」と思い込むようになってしまいます。
ここで大事なのは、そもそものマインドセットを変えることです。「自分なんて大したことない」という謙虚な気持ちに戻ることです。
そうやって心持ちを柔軟にしておけば、困ったことが起きた衝撃も和らげてくれるんですよね。
逆に、「プライド」を持ってしまうと、堅い気持ちで何事にも臨むことになってしまいます。心が堅い状態だと、強い衝撃で砕けたり、折れたりしてしまいますよね。 >>265 ドライウェルは撥水を抑える役目でありそれ以上でも以下でもない。
乾燥後の水シミを抑えるだけであり、
精製水ですすげば、水シミの心配はないので必要はない。
>>264 ありがとうございます。
Blumwayや洗濯機の羽と一緒になった超音波洗浄機の
の周波数はそれぞれ50kHzと40kHzだから問題はないね。
>>265 すまないが低能なのでリンクをお願いします。
1980年頃発売のレコードをクリーニングして聴いてみた。
セラフィム・エクセレントシリーズの中のモーシェ・アツモン/ニュー・フィルハーモニアのメンデルスゾーン「序曲集」
元々無傷でノーノイズだが、針が溝の奥まで届いていない感触なので、クリーニングしてみた。
クリーニング前はシーーーーーーンとしたノイズの無い静音だが、所々の周波数で歪み感がある。
弱アルカリ界面活性剤洗浄を行う。
歪み感はかなり減少した。
しかし元のサウンドに問題があるらしく、周波数特性にバラツキがあり、とらえどころの無いサウンド。
「フィンガルの洞窟」序曲も含まれているので、講談社のステレオ世界音楽全集の中の同曲(ペーター・マーク/ロンドン響)との音質差が際立つ。
マーク/ロンドン響盤は1960年録音、アツモン/ニュー・フィルハーモニハ盤は1975年録音だが、断然マーク盤の音が良い!
デッカ録音は1960年に高レベルのサウンドを捉えていた事を思い知らされると同時に、EMIのセラフィム・エクセレントシリーズの音の悪さにガッカリ。
セラフィム・エクセレントシリーズは他にも数枚購入したが、繰り返し聴く盤は1枚も無い。
廉価盤なので手抜きで発売したのか、それとも元の録音が悪いのか?
しっかり音質を調整して発売してほしかった。
アツモン盤は序曲「静かな海と楽しい航海」目当てで購入した。
この音質では演奏の真価は伝わらない。
演奏はマーク/ロンドン響盤(1960年録音)の「フィンガルの洞窟」が際立った感銘を受けるのに対し、アツモン/ニュー・フィルハーモニアは表情豊かではあるが、マーク盤のどこまでも心の奥まで伝わる恍惚感が無い。
マーク盤が高音質で残されたことを人類は喜ぶべきだが、アツモンの録音がこんな劣ったサウンドで発売されるのは、無しでしょ?
1975年なら、もっとよい音を捉えられるはず。
もちろん拙宅の装置では、EQで音質調整してまずまずのサウンドで鑑賞してみた。
アルコールは止めときます
ハードオフで、ジャンクレコード買って、練習してみようかと
何せ、LP42円とかだし
>>271 レコードスプレーもアルコールは入っているよ。
252の人はレーベルガードとレコードを取り違えて言っている。
絶対にヒビなど入らない。
SPレコードじゃあるまいし。
軟質塩ビでも別に何ともありません。
2年間アルコール漬けましたが、別に何ともありません。
>>267 やっぱり無知な低能w
ドライウェルは界面活性剤として使うもんだ
印画紙に薬液を満遍なく行き渡らせる為に富士フィルムが出してるもの
それ以上でもそれ以下でもない
何が乾燥後の水シミを抑えるだw
無知にも程がある
>>275 ドライウェルは印画紙やフィルムの現像- 定着-水洗後に使用して乾燥ムラを防ぐものだよ。現像液や定着液を行き渡らせるためじゃないよー。無知無知さんにもほどがあるねwww
主観で書き込んでるから、ご伝授なんてありませんよ
オーッホッホッホッ!
>>279 なぜ無知と言い切れるのか無知な私にもわかるように教えてくだしあエロい人。おながいしまつ
レコードなんて印画紙か?
まんべんなく薬液を行き渡らせる意味が、
せっかくきれいに洗浄してごみなどを取ったのに、何を行き渡らせる必要があるのか?
そこのところも教えてほしい。
>>274 乾燥時間に一週間かけたけど、見た目は別に何ともなかったよ。
付けておいただけだったから、クリーニングは再生する前に普通のベルベットのクリーナーで拭いただけ。
劇的に良くも悪くもなかったし、
アルコールでレコードがおかしくなるなんてウソだろ。
ただし、視聴用のアセテート盤はアルコールに溶けるからね。
レアな代物だからほとんど目にしないから大丈夫。
アセテート盤は木工ボンドの硬い奴と思ってください。
>>285 軟質塩ビがアルコールで変質するのは立証済みの内容なので
問題はレコードで許容できるかどうかって話じゃないかな
>>280 >>282 ググる事も出来ないクレクレ君の無知くんw
そしてドライウェルをこのスレで知らない奴がいる時点で最近始めてここで暴れまくってるボンドパック君だろお前w
>>284 お前みたいにトチ狂ったググる事も出来ない無知にもヒントをやるよ
超音波洗浄の原理は水中を超音波が伝わって対象物に衝撃を与えて汚れを落とすもの
中性洗剤には界面活性剤が入ってるが洗浄剤も入ってるからそれ自体が不純物
ここまでヒント出してそれでも分からないなら小学生以下だなw
>>287 ドライウェルぐらい知っているが、
せっかくチリ,ホコリ、レコードスプレーの界面活性剤(帯電防止剤)を超音波などで除去したのに、
わざわざ、必要のないドライウェルなんかかけるんだ?必要ないだろ。
必要以上の界面活性剤は除去したいんだよ。
しかもレコードは印画紙やフィルムじゃないんだよ。
いったい全体何の効用を狙っているのかね。
洗剤で超音波洗浄後、取り出したら、全面濡れている。
洗剤は界面活性剤だからね。だからドライウェルなんか必要ない。
そのあと大量の水道水で洗ったのちイオン交換水で洗う。
もちろんイオン交換水はフィルターを通してイオン交換しているから、
レコード面は清浄になる。強烈に撥水するから、界面活性剤でもある中性洗剤は洗い流されているんだよ。
残っていたら撥水なんかしない。これでそのあとわざわざドライウェルを掛ける必要があるの?
言っておくけれど、超音波洗浄は日常的に会社で使っている。
電子部品の洗浄に使っているし、分析室でも実験器具を洗うために使用している。
超音波洗浄の原理ぐらい百も承知。
一般に市販されている超音波振動子なんかそこまでの電力とパワーがない。
破壊されるわけはない。それぐらいはわかるから、わざわざ時間かけて調べる必要もない。
それ以前にあなたは調べたのだろ?だからリンクを貼ってくださいとお願いしたんだ。
ドライウェルで何の効用を狙っているのかと、
超音波洗浄でレコードが破壊された事例や、痛んだ事例とその時の超音波振動子の電力と周波数の情報、リンクを貼ってくれ。
書いているうちに、ごはんよーという妻の声で、うん?と思ったんだが、
食器の洗浄は中性洗剤でジャブジャブ洗っている。油汚れもとれるからね。もちろん、レコードの油性である界面活性剤も取れる。
あなたの言い分では、汚れが取れない、というのかね。水ですすいでも中性洗剤が残っているというのかい?
しかし、あなたは中性洗剤で食器を洗っていないようだ。不純物が残るから?
ドライウェルを掛けておしまいにしているの?言っておくけど、ドライウェルの成分はカラダに悪いから口に入れるようなものに使ってはいけないよ。
>>289 ドライウェルを知らないと長文で白状してるようなもんw
さすが低能
ほう、玄人なら、正論したらどうだい。
1行、2行だけでつぶやくだけでは、何にもならない。
工業用にオーディオテクニカがローラータイプのクリーニング品を作っていた。
しかしレコードに使えるかは知らない。
オーテクは静電気対策品があるんだよね
ほしいけどなかなか手が出ない
>>294 過去スレで散々出尽くした話でドライウェルを使うのはもう常識的な話
理由を知りたかったら過去スレを読み漁れ
最近始めた初心者ならそれくらいの努力はしろよクレクレ君
>>301 説明する能力はないのか?
全部読んでいるが、それも承知で書いている。
講談社のステレオ世界音楽全集のビニ焼け盤のクリーニング。
ヤッパ、時間かかるわぁww
今取り組んでいるのは、チャイコフスキー:悲愴交響曲、マゼール/VPO!
ボンドパックを繰り返すだけでどうなるか実験してみたが、ボンド成分が盤上に積み重なって、楽音が小さく小さくなってしまった。
ボンドパックの繰り返しだけではダメで、残留ボンドを除去しながらのボンドパックでなければならないようだ。
残留ボンドの除去には、重曹水洗浄と弱アルカリ界面活性剤洗浄を基本にその他の方法も利用した。
この盤は、他に状態の良い物をヤフオクで落札しているので、音質の比較が出来る。
幸運にもその状態の良い物はA面にビニ焼けが皆無!
ただ、時々パツン、パツンとノイズが入る。
元々の音質を確認するには十分だろう。
チャイコフスキー:悲愴交響曲、マゼール/VPOビニ焼け盤は、異物の除去を現時点で可能な範囲行い、楽音だけは良好盤と同様な音が鳴っている。
ただ、背景にゾリッゾリッとビニ焼け特有のノイズが冒頭近くに残っていて、その後もボコボコと背景ノイズが続く。
おそらく溝の底の部分にある程度の異物が横たわっているはず。
これが結構しつこく残っていて、除去が難しい。
重曹水を1,2度くらい使っただけではビクともしなかった。
超音波洗浄で異物をふやかし、ブラシによって除去を試みるつもり。
盤の状態によっては重曹水が効果を上げる場合もあるが、このチャイコフスキー:悲愴交響曲、マゼール/VPO盤は、なかなか効果が出て来ない。
>>297 ウチにはレコードクリーニング用のローラータイプのクリーナーがある。
NAGAOKA Rolling152
これは軽い汚れには効果てきめん!
ベルベットクリーナーと違って、埃などを強制的にローラーに粘着させるから。
ただ、ちょっとやそっとでは除去出来ないしつこい汚れには効果は無い。
元が綺麗な盤に埃がついた場合に良いクリーニング法!
ビニ焼け盤のクリーニングには効果は無い!
ウチにはT型の150てのがある
使った事ないけどw
てか今でも現役でRolling1000てのがあるんだな
お高いけど
>>302 全部読んでたらそんな言葉は出てこない
嘘も大概にしろ初心者君
>>302 それと全部読んでるならドライウェルを使った洗浄方法もわかるはずだが言ってみろ
本当に読んで理解してる上なら言えるはずww
むかしコロコロローラーもクリーナーとして売られてましたが
転がすタイプでなんの効果があるのかと
当時からだまされませんでした
どう見ても埃取りだろ
それ以外にどう騙されるのか?
アルコール・ボンドパックについてひとつ。
ボンドを原液のまま使用するのは不味いことが判明。
アルコールを盤上に撒き、原液のボンドを垂らしてアルコールと混ぜると、乾いたときにかなり固くなる。
剥がすときにペキペキと割れ目が入り、沢山の小片が盤上に残留する!
この処理に一手間かかる。
物理的方法だと傷をつける可能性があって危険。
予めボンドを水と混合させると、乾いても柔軟性が残って、ペキペキと割れ目が入ることは無くなる。
ボンドと水の混合割合によって性能が異なり、最適の割合はこれから追及してみる。
誰かが提案していた洗濯糊との混合も近いうちに確認するつもりである。
>>307 その議論に参加もしてたよ。納得はしなかったが。
ここに新参の人もいるので、自分の方法と効能とその理由を言葉で説明したらいい。
説明できなければ、理解しないで書いている通りにやっているだけでしょ?
しかもあなたとやっている方法は違うから必要がないとなぜ気づかない?
セメダイン木工用なら
何も混ぜずに100%のストレートがベスト
コニシとかもいっしょです
>>312 >>314 この特許文献を参考にしてください。
再び言いますが、アルコールを混ぜることについては言及していません。
新品同様のLPをクリーニングしてみた。
盤は1980年前後発売のグラモフォン2LPシリーズの中のカラヤン・シュトラウス・コンサート!
これは当時購入して1度第1面をプレイして鑑賞する意欲を失い、そのままレコード棚に。
当然、ノイズはゼロに等しく、無音の溝は静まりかえっているが、音質が悪い。
今確認すると、量感に乏しく、中高音域に変なクセがあり、生のオーケストラのサウンドからかけ離れたケバケバしさがある。
元の録音音質の影響もあるだろうが、どうもレコード針が溝の奥まで届いていない感触。
弱アルカリ界面活性剤での洗浄を一度だけやって見た。
音質が圧倒的に改善というわけには行かないが、中高音域のクセはある程度改善。
中低音域も若干だがバランスが修正された感触。
かつて「Stereo誌」に「新品レコードを洗浄して聴くのが好きだ」との評論家の意見があったが、それが根拠の無いモノではないことを実感。
製盤の時点で、溝の表面にごく少量の異物か何かが残ってしまった可能性がある。
ならば洗浄行為で音質が改善するのは当然かと。
新品或いは新品同様のレコードの洗浄も視野に入れると、さらに音楽ライフは楽しくなるかと。
>>313 議論に参加ww
もう初心者バレバレだなw
早くその時に参加したという時に出たドライウェルの使い方を書いてにろよ
参加したなら書けるだろ
まぁそもそこ本当に見てたらレコードに塗るなんて言葉は出てくる事は絶対にないからw
>>318 >>308 自分で説明できないのか。期待しているのに。
ドライウェルは静電防止剤にするのは役不足。
エチレングリコールは低分子すぎる。毒性あり。
ポリオキシアルキレンエーテルも静電防止剤の用途ではない。
その用途を目的とするならば、カチオン系、ノニオン系の専用の帯電防止剤がある。
界面活性剤として洗浄効果を狙っているかもしれないが、
ノニオン系、カチオン系はアニオン系の界面活性剤よりも洗浄効果に劣る。
アルカリ系の脂肪酸石鹸は石鹸カスが生じるので中性洗剤が適している。
あなたはアルコールと水とドライウェルでやっていると思われ、
盤面の汚れ除去はブラシでするようだから、何らかの接触で盤を傷つける恐れがある。
ブラシで超音波洗浄より磨きムラはありませんと、言い張れるか?
たとえシステマのブラシといえども、その先端はレコードの溝底に到達していない。到達していると思う?到達していないのなら溝底の汚れはどうする?
すすぎをしないので、バキュームで洗浄液を吸ったとしても全部汚れが取り切れているのか。
帯電防止をしたいのなら、バキュームで吸った後に、
タキロンのコートロンを買ってきてまんべんなく塗って乾燥すればいいのではないか?
わたしはやったことはないw。
アルコール水でのブラッシングならコートロン添加の方が帯電防止と書いているからそっちの方がいいのじゃない?でも、成分が薄いようだ。
塩ビの帯電防止剤はカチオン系の界面活性剤が主流だよ。
あなたの方法はドライウェルというからにはアルコール水溶液に入れてブラッシングしているのが通例だから勝手に想像して書いた。
上であげた疑問な所があるので、丁度洗濯用の超音波振動子も市販されており、Web上でも実績があるから、実施している。
あなたとは洗浄方法と考えが違う。
溝底まで異物を取り除きたいので糊パックと超音波を組み合わせている。過去の学業と今の実業で培われた知見を応用している。
あなたにはあなたの知見があるようだから、ここで述べてほしい。
あなたが手にしたレコードは幸運にも状態が良いものばかりだったのでブラッシングで十分にきれいになったかもしれないが、
私の落札したものは、見た目はきれいだったが最低の状態だった。ドライウェル添加のブラッシングもしたよ。しかし効果が薄い。
>>318 すまなかったなあ、塗るという言葉だったらから誤解させてしまったかw。
一応ドライウェルを使わない理由は書いたから。
184名無しさん@お腹いっぱい。2021/05/28(金) 02:08:47.30ID:y1xLu9KV
あとドライウェルの有無で異なってくるからね。
水
ドライウェル
塩ビレコード
このように水を押しのけて塩ビレコードに直接ドライウェルは張り付くので、水道水のカルキ成分が残ってもドライウェルの上に乗っているだけ。
クリーニング後に一度捨て再生で針を通せばカルキ成分は取れる。
無音溝はドライウェルのおかげで静寂。
ドライウェルを使わなかった場合は注意が必要。
塩ビレコードに直接カルキ成分は張り付くので、バキュームする直前には精製水でカルキ成分を洗い流してから行う事。
しかしドライウェルがないのでトレース音は目立つ(無音部分で確認できる。高域がやや強いシャーという音になりやすい。)
ちなみにドライウェル使用していて精製水で仕上げすすぎをするとドライウェルは洗い流されてしまい意味はなくなるので、
やはり高域がやや強いシャーという音になりやすい。
これは、私の書き込み↓
188名無しさん@お腹いっぱい。2021/05/28(金) 04:35:18.04ID:oVieOZy7
>>184 ドライウェルは界面活性剤
界面活性剤は洗剤に含まれる成分で水を融和させると同時に汚れを融和させることにより汚れをとるもの
特に油なんかを水に溶かして乳化させて取るためのもの
それが残った状態というのは界面活性剤だけでも不純物なのに、それに溶け込んだ汚れも残すという事
もっと勉強して出直してきなさい
209名無しさん@お腹いっぱい。2021/05/28(金) 22:17:24.60ID:vqcmU97/
ドライウェルは入れすぎると
無音溝でゴロゴロ音がするようになる
211名無しさん@お腹いっぱい。2021/05/28(金) 23:02:43.19ID:tjqhDDEn
>>209 界面活性剤だからな
汚れを溶かして再固着しないように乾燥しないうちに完全に精製水で洗い流さないと
17名無しさん@お腹いっぱい。2021/05/29(土) 08:45:09.30ID:sc5PLiLU
>>218 >>209 それはドライウエルは関係ない
汚れを除去できていないだけ
針の先端とミゾの底に除去できてない汚れが触れてる音だよ
10秒再生して20倍ぐらいのルーペで針に汚れが付いてないか確認してごらん?
30秒、1分、2分と再生して同じように確認、さらに今再生した場所をもう一度再生して針に汚れが付いてないか確認
-----
あと延々と行く。ただしこの件では私は一回しか書き込みしていない。
1980年前後発売のグラモフォン2LPシリーズの中のカラヤン・シュトラウス・コンサート!の件
これまでデジタル音の劣等性を語って来たが、グラモフォン2LPシリーズの中のカラヤン・シュトラウス・コンサートを見る限り、あまり優秀な音質とは言えない。
今後の取り組みとしては、とりあえずレコード針が溝の最奥まで届くようにクリーニングし、その後に、EQで調整して生のオーケストラのサウンドに近づけるべく取り組むことになる。
音楽を出来るだけ生のサウンドに近づけて楽しみたい。
その為のレコードクリーニングである!
で、レコード針が溝の最奥まで届くようにする為の方法としていくつか思い浮かぶ。
弱アルカリ界面活性剤洗浄。
超音波洗浄。
重曹水による洗浄。
アルコール・ボンドパック。
デンターシステマによる超音波ブラッシング。
弱アルカリ界面活性剤洗浄は、若干の改善が観られたが、一度だけの洗浄では効果が小さかった。
デンターシステマによる超音波ブラッシング+弱アルカリ界面活性剤洗浄で、ほぼ溝内の小さな凸凹は取り去ることが出来るだろう。
その時に初めて、レコードの溝にどんなサウンドが記録されているかが明らかに成る。
以前落札したボールト/ニュー・フィルハーモニアの「南極交響曲」を聴いてみた。
これはレコードのクリーニングを必要としない、無傷、雑音ゼロの新品同様だ。
ただ、何かの原因で音質が優れない。
EQで調整して聴いてみると、各楽器の音色が生き生きと再現される。
このレコード発売当時の所謂専門家達は「EQでいじくると音が悪くなる」と言っていたが、これはウソだ!
オーディオマニアも、「EQで音をいじくるのは邪道」とか言っていたが、このレコードはそのまま聴くと味も素っ気も無いサウンドになる。
>>327 イコライザー使ったらもうそのレコードに
刻まれてる音じゃないし
まー別にいいんじゃね
俺も定食屋で出された食事に
「オバチャン、ケチャップかマヨネーズある?」
ってなコト、あるし
人の好みにあーだこーだは特に無いわ俺の場合
各自の好きにしようぜ、自由に
法的に制約があるワケでもないし
>>328 生録しているとよくあることですが、
空調の音とか、水銀灯からのハム音が邪魔になる時が、ホール以外の会場でよくあります。
しかし、空調の超低域ノイズカットや、ハムノイズでは電源周波数の数次高調波をノッチフィルターを通すと、
楽音が浮かび上がります。
>>328 ID:YDiiK0br
典型的な思考停止もしくは脳委縮
あるいはアルカホリックとかおパチなんかの依存症かも
>>332 全域にわたるヒスノイズなどはそうだけれど、
ある周波数のところだけをノッチするとか、
楽音上、明らかにさぼソニック領域に達していない音源はカットしたほうがいい。
この場合は臨場感は消えません。
大ホールだと20Hzくらいまで再生できた方が空気感が感じられるぞ
もっとも再生環境を整えるのが難しいんでバッサリ切るのも手だが
>>335 この間収録したホールが、会場の椅子で聞いても気になるくらい。
ホールスタッフに聞いたら、ここはこういうホールなのですみません。
空調は止められません。と言われた。
ここのホールは、マイクに風であおられたこともあるから、セッティングに神経を使う。
演奏団体の主催者にも空調ノイズは何とかならないかと言われ、
小編成の弦楽合奏だから、50Hz以下はバッサリと切りました。
大編成のオケでは、空調ノイズがひどい場合、20Hz以下ですね。
それ以上の周波数でカットしたら、バスドラムが死んでしまいます。
本当はサブソニックは普通切りませんが、空調ノイズがひどいときには仕方なくしています。
(空調ノイズがひどい録音の場合、盛大にスピーカーが踊りますからねえ)
>>328 ?
レコードの刻まれている音自体が結構歪んでるんだが?
EQ使って確認すればわかる。
EQで調整すれば歪みをかなり修正できるんだが、調べてみたこと無いの?
>>332 たしか昔の評論家はそう言ってたようだけど、実際にEQで調整すると、どうもそうでもないんだよな。
ノイズ除去と言うより、音のバランスを取れば、自然にノイズが低減し、生々しい音になる。
まぁ、オレはレコードのクリーニングをして、EQで音の調整をして、会場で成っていたサウンドへアプローチしてみるよ。
これまでの感触では、かなり音質が改善する。
グラモフォン2LPシリーズの中のカラヤン・シュトラウス・コンサート!
デンターシステマによる超音波ブラッシング+弱アルカリ界面活性剤洗浄 をやって見た。
特性がある程度変わり、よりフラットな方向に変化した。
新品の状態で感じた嫌み(ケバケバしさ)が相当小さくなり、ベルリン・フィル特有のサウンドに近づいてきた。
ただ、極小さくだがプチプチノイズを拾っている。
これが除去出来れば、効果的クリーニングとして認められるようになる。
考え方として、新品のレコードの溝に、どうやら製盤工程で生じた凸凹があるらしい。
これがレコード針での読み取りに悪影響を及ぼし、周波数特性にゆがみを生じさせる。
この凸凹をデンターシステマによる超音波ブラッシングによって凸凹を毛先で擦ることによって平たんにする。
ブラッシングで発生したであろう微粒子を弱アルカリ界面活性剤洗浄で除去する。
このプロセスを経て、レコードの音溝がよりスタンパーの形状に近づき、より良いバランスのサウンドを取り戻す。
結果としてある程度音質が改善したので、この仮説は正しいはず。
デンターシステマによる超音波ブラッシング+弱アルカリ界面活性剤洗浄の効果を確認するために、他の盤でもやってみた。
盤はキング・世界の名曲1000シリーズGT1011メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲オレフスキー(vn)
この盤はこれまでパッククリーニングとかやって来たけど、たしかデンターシステマによる超音波ブラッシングは初めて。
音階が変わる度に特性がコロコロ変化して困っていたけど、かなり特性に安定感が生じた。
こんな音で収録されていたのかと納得し、新品のレコードの溝が必ずしも平たんではないことを思った。
新品のレコードでも、より良い音で聴くために、最初にクリーニングするのは重要ですねw
>この凸凹をデンターシステマによる超音波ブラッシングによって凸凹を毛先で擦ることによって平たんにする。
怖いことするなぁw
クリーニングで音質が変わる(向上する?)なんて
よっぽど埃だらけのチリまみれだったんでしょう
>>344 昔大切に使ってても静電気で細かいチリが付くし
あと中古レコードはクリーニング必須かなと俺
>>343 普通はそう考えるだろう。
けど、新品のレコードでも溝の形がスタンパーのそれと若干の違いが生じているのではという疑いがある。
スタンパーからレコードを剥ぎ取るときに、表面張力によってレコード表面に若干の凸凹が発生するぞと!
この微妙な凸凹が、溝の読み取りに悪く影響し、フラットな特性を得にくくしているはずだと。
実際問題としてカラヤン・シュトラウス・コンサート2LP(ほぼ新品)はケバケバしい音でBPOらしいサウンドが聴かれなかったし
オレフスキーのGT1011メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲が音階が変わる度に音質がコロコロ変わっていた。
これらはおそらく微妙な凸凹によって、レコード針が溝に密着しづらい状況を生みだして発生した状況であろう。
もっとレコード針を溝に密着させたいと言う思いで超音波ブラッシングを行ったわけだ。
結果は上々で、バランスが良好になったばかりで無く、サウンドにハイファイ感が増したわけだ。
>>343 レコードの音溝の読み取りは、レコード針の形状によって精度が異なる。
丸針、楕円針、シバタ針(ラインコンタクト針)で、レコードと接触する面積が異なり、丸針が最も接触面積が狭い。
したがって、接触面積の小さな丸針は、音溝表面の凸凹の影響を最も受けやすくなる。
ラインコンタクトのシバタ針は、接触面積が大きいので、凸凹が平均化され、スタンパーに記録されたサウンドに近いものを拾いやすくなる。
ただ、この微妙な凸凹を小さくすれば、理屈の上ではどの形状のレコード針でも同じサウンドを得られるはずだ。
レコード針の形状によって得られるサウンドの質の違いは広く知られていて、アマゾンのレコードカートリッジのレビューにも表れている。
シバタ針のカートリッジのレビューは最高評価が並んでいる。
仮に音溝表面がフラットであればこんな現象は発生しない。
今使用しているのは丸針だが、それでこんなによい音が出るのは結構な話ではないかw
レコードクリーニングは、ノイズ除去だけで無く、音質向上にも影響する。
>>343 ただ、音溝に形成されて居るであろう微妙な凸凹の縮小の手法として超音波ブラッシングが最善かどうかは検討されるべきだろう。
音溝にデンターシステマの毛先をこすりつけることは、音溝を削る恐れも発生する。
できれば非接触で凸凹を修正したい。
>非接触で凸凹を修正
修正じゃなくて凹凸に埋まったチリを非接触で根こそぎ
をねらうのが超音波(高周波)ですやん
>>344 新品は離型剤や可塑剤がうっすらと表面にあるから、音溝と針の間にクッションを敷いているようなもので、
忠実に針先が音溝をなぞっているとはいいがたい。
また、そういったものが、潤滑剤の役目をするならば、摩擦抵抗が減って針音の減少につながればいいのだが、そうとも言い切れない。
まして、中古品や新品といっても長期保存品は内部から可塑剤や脂肪酸塩類が浮き出てくるのでなおさらだろう。
それらのクッションをなくして直接音溝と針を接触させたいということでクリーニングが音質向上につながる。
特許文献をあさると、レコードの帯電防止剤について詳細に書いてある文献があった。
ステアリル基を持ったカチオン系の界面活性剤と結構大きな分子量のノニオン系界面活性剤を組み合わせて、
塗布量とSN比、周波数特性の変化を調べていた。
ステアリル基などを持つ界面活性剤は潤滑性があり、摩擦抵抗が減ってゆきSN比向上するが、
ある量を境に高域がレベルダウンするという特許っだった。最適量が存在する。
その文献を読んで、不必要な表面に滲み出ているような膜や、過去に過剰に塗布したレコードスプレイの帯電防止剤や、
帯電防止にはなるだろうが、摩擦抵抗軽減を考慮にしていない分子量が小さいエチレングリコールを含むドライウェルなど、
これらを全部はぎ取ってクリーンにし、適量な潤滑性を持った帯電防止剤をレコード表面に付加するのが適当と思う。
その適量が難しい。
適量がむずしいから、拳銃タイプのゼロスタットで静電気を抑えて、表面に異物のない状態で再生した方がよいのか、
潤滑性を持ったカチオン系などの帯電防止剤の検討に入った方がよいのか迷うところ。
それらの素性や用途を調べると毛髪用のリンスに使われている。
それらの帯電防止剤を試薬屋さんから購入して準備だけはしている。
ただしシリコーン系はダメ。分析器具からなかなか取れなくなって困った。
糊パックに添加してみようという算段。オリジナルのレコパックには添加されていた。
摩擦が減れば、針先寿命、レコードの寿命も伸びる。
パック方法は応用が利く。
新品には表面にうっすら剥離剤は付かないそうだよ
確か東洋化成が言ってた
>>351 情報ありがとう。
だったら、何らかの油性の膜だろうね。
>>349 超音波洗浄には他の効果もある。
盤表面の異物の塊に超音波衝撃を与えて、ヒビを入れるとか軟化させるとか。
ただ、レコード盤自体への影響もある可能性があって、その解明をしておかねばならない。
それと超音波ブラッシングは、接触である。
超音波振動でブラッシングすることによって、溝の表面を毛先がこすりつけることによって溝の表面に付着する異物を除去する。
これによってチリチリノイズがかなり除去出来る。
同時に、溝表面に発生して居るであろう不作為の凸凹も平坦化され、レコード針による読み取りのクオリティを上げることが考えられる。
>>351 それは東洋化成による認識を表明したものであって、実際どうなっているかとは別問題。
製造者が「こうだ」と言っても、実際はそうなっていないと言うことは往々にしてある。
例えばデジタル音声(CD)が、「データを圧縮しているが人間の耳では感知されない」と言う触れ込みで発売されたが、ハッキリと違いが耳で確認できる。
他にも、教科書には二酸化炭素を無味無臭としているが、二酸化炭素にはハッキリと味をかんじられるw
「人間以外は道具を作ることが出来ない」と言われていたが、オウムが針金を加工して、管の中のマメをその加工された針金で取り出すことが確認されている。
>>353 超音波洗浄でダメージを与える周波数は1MHzとあった。
40や50kHzでは破壊されない。
>>353 超音波ブラシw
お前超音波美顔器、ボンドパック君の初心者じゃねーかw
>>353 「超音波振動でブラッシングすることによって溝表面に発生して居るであろう不作為の凸凹も平坦化され、
レコード針による読み取りのクオリティを上げることが考えられる。」
神経質なこと言ってんな。
システマの毛先はポリエステル樹脂だぞ。
そんなんで柔らかいものでレコードの溝なんか削って平坦化できないよ。
考えてもみろよ、レコード針は硬いダイヤモンドだぞ。
それが高速でレコードの溝をトレースしてんだからそっちのほうがレコードの溝を削るだろ。
システマでクリーニングして音が良くなるのは単純に付着する異物を除去したからだよ。
ついに超音波ブラッシングによってレコードの溝に製盤工程で生じた凸凹さえも平坦にして周波数特性のゆがみすら克服できるようになったんだな
胸熱
>>360 Amazonで
超音波 洗濯機
で検索してください。
私はBlumwayの製品を使っています。
>>346 >スタンパーからレコードを剥ぎ取るときに、表面張力によってレコード表面に若干の凸凹が発生するぞと!
レコードを硬化させたのちにスタンパーから排出するので、
液体のように表面張力は関係ないと思います。
ですから、音質が変わったのは異物が除去できたのだと思いますけどどうでしょう?
>>364 溝の中に何かがあることはわかる。
何があるのかは今のところ、推測でしか無い。
>>363 ポータブル超音波振動ですかね?
レスを見ると、振動が足りないとの話も有りますが
実施のところはどうでしょうか?
2個必要となりますか?
>>367 Blumewayは一個で十分ですけどねえ。
中性洗剤と一緒に超音波を掛けたらピカピカになりました。
また、手を入れると十分に大きな振幅と感じました。
>>368 有難うございます。
もう一点お尋ねしたいのですが
音はどれぐらいになりますか?
ドライヤーぐらいの音はしますか?
>>369 戸建てですが近所の人から
「なんかいつも音がしていますねー」と
やんわりと抗議されました
>>369 そんな大きな音はしませんよ。
ジーという音です。
部屋の扉を閉めれば聞こえなくなるレベルです。
>>370 一体全体なにを使っているのですか?ウソはやめなさいw.
>>373 扉を閉めて隣の部屋に行ったら聞こえないよ。
高い音だから、遮音しやすい。
>>375 隣の家まで絶対に音は届かない。
そりゃ、宣伝カー並みの音の大きさだぞ。
宣伝カー並みじゃないと聞こえないなんて防音すごい家に住んでんだね
羨ましいわ
バキュームマシンも凄い音するぞ。
掃除機(メーカーや様式にもよるが)の音の2倍くらいの音がする。
デンターシステマによる超音波ブラッシングによる効果を再確認した。
盤はRCAの映画【サウンド・オブ・ミュージック】サントラ盤。
これまで音階による音色がコロコロ変わって居たのが、超音波ブラッシングによって音色が安定してくる。
おそらく基本音の部分も安定して聞こえるようになるはず。
ただ、この盤は元の録音に問題があって、高音域(1.6kHz~8kHz)あたりに所々ブーストする周波数があって、完全な生の音そのものは出て来ないけど。
それから内周歪みがかなり目立って出てくるので、クリーニング以外の取り組みが必要なようだ。
アルコール・ボンドパックについて。
やはりボンドを原液のまま使用するのは問題がある。
盤上で無水エタノールと混ぜた場合も、消毒用エタノールと混ぜた場合も、剥がす時にペキペキ割れて、破片が盤上に残留する。
およそ30枚でやってみて全てがペキペキ割れて破片が残留した。
事後処理をすれば残留物を除去出来るが、これが結構な手間になる。
ボンドには水を予め混合する必要がある。
今はボンド:水:消毒用エタノールの割合を5:1:1でやっている。
若干液が柔らかすぎかと感じるが、これだと剥がすときに割れたりせず、盤への吸着力は少なめではあるがちゃんと吸着している。
今後は、洗濯糊の利用と混合割合の追及を考えている。
講談社のステレオ世界音楽全集のビニ焼け盤のクリーニング
35枚の中のほぼ全てが使い物になる状態に成った。
大半がチリチリの背景ノイズが残留するだけの状態に成り、他の数枚がゴボゴボ低音ノイズが残っている状態。
しかしこれでも十分に楽音が聴かれ、気にしなければ鑑賞に堪える状態だ。
チリチリの背景ノイズはおそらく溝表面に細かな粒子が彼方此方に残留して発生していると考えられる。
これはデンターシステマによる超音波ブラッシングによってかなり除去出来るはずである。
ビニ焼け盤のクリーニングでノイズゼロを実現させられる可能性はある。
>>383 ボンドパックよりデンターシステマによる超音波ブラッシングのほうが効果あるやん。
>>383 糊パックは40%のi-プロピルアルコールでも剥離はしやすい。
貴殿に試していただきたいが、連絡とる方法がない。以下がすればよろしいか。
>>386 洗濯糊は入手済みだよ。
あとはエタノールや木工ボンドとどんな比率で混合するか試行錯誤を始める状態。
今、5:1の割合での消毒用エタノールと木工ボンドの混合液体を準備している。
これに洗濯糊を混合させればより理想に近いバック液体が出来上がるはず。
ボンド:水:消毒用エタノールの割合を5:1:1で混合させた液体でのパックは、今のところまずまずの成果を上げている。
>>387 それプラスにビニ焼け除去剤を配合したパック液も持参予定。
ピアノの先生からいただいた大量のレコードにビニ焼けはないかと開けてみたら、
茶色の可塑剤が内袋についていたのはわかるが、カビだらけだった。
早速ビニ焼け除去剤添加の糊パックを施した。
RCA盤の全集物は、紙袋の内側にポリエチレンの袋だった。
せめてポリプロピレンにしてほしかった。
>>388 ビニ焼け除去は無理なんじゃない?
主にアルコール・ボンドパックで大まかな異物を除去して、超音波ブラッシングとか弱アルカリ界面活性剤洗浄、アルコール洗浄なんかを組み合わせてノイズ除去するしか方法がなさそうだけど。
>>390 あなたの予想に反して、ビニ焼け後の白い異物の正体はわかっているから、対処方法は判明している。
レコードじゃないけれど、その同様の除去は色々な所で書かれている。
程度の軽いものは除去できて、重いものは修復不可という認識
今日のカビ。

別角度から。

>>393-394 カビとは関係ないけどそのレコード片面にずいぶん曲が入ってるな
この手のカビはチョチョイのチョイだな。
除去は簡単で難敵じゃあない。
>>393 それって結構簡単にクリーニングが済みそう。
まず超音波洗浄をやって、その後に弱アルカリ界面活性剤洗浄をすれば大方のノイズが消え去るはず。
傷が有れば話は別だが。
>>392 どうやらビニ焼けの軽重に関わらずノイズ除去が可能な模様。
結局上に覆い被さった異物を丁寧に全て除去すれば、相当よい音になる。
ノイズゼロに出来るかどうかが問題で、溝の浅い方の異物の除去が決め手になるはず。
今、ブラシをどうするか検討を始めたところ。
>>391 確かに白い異物は雑音の発生源のようだ。
しつこくビニ焼け盤のクリーニングをしていると、次第に白い部分が無くなれば、雑音も少なくなっていく。
この白い異物の除去にはGUM歯ブラシの固さが普通のブラシで超音波ブラッシングすれば除去出来そう。
かなり以前にヤフオクで落札した大量LPの中に、ビーチャム指揮のハイドン・シンフォニーが2枚含まれていた。
ロンドン・シンフォニーを確認すると、バチノイズが所々入っていた。
それよりも気になったのは音質である。
高音域のいくつかの周波数がブーストして、酸っぱい感じの音になっている。
もちろん低音域も量感不足。
解説にはビーチャムの演奏の上品さが記されていたが、これではその良さが伝わらない。
EQで調整すると、品の良い歌が彼方此方に聞こえてくる。
これはクリーニングも大切だが、音質調整して演奏の価値が伝わりやすくして世に問うべきでは?と思った。
>>402 程度の重いものは針飛びするくらいの変形があるんで修復不可だよ
ほんとに熱で焼けたかのように変形した盤のこと
日本盤ではまず出会わないけどDiscogsやeBayで補足にHeat Damageと書いてあったら手を出さない方がいい
>>402 頑張ってください。
白い異物の除去方法は内緒で教えたいが、顔を合わすのが嫌そうだから、今のところはやめておきましょう。
しかし、いいビニ焼けのサンプルがない。
一目瞭然のサンプルがない。
栗―0人具したのはいいが、もともとの内袋に入れたくないなあ。
グラシン紙を注文して手元にあるが、まだ袋にしていない。
丁度いい大きさがなかった。
あったとしてもべらぼうに高い。
パックしたまま、元の袋に入れるしかない。
紙製のうち袋で格安のブツはないものか。
ナガオカの内袋は、ポリプレンせいだから、再びビニ焼けになってもおかしくない。
>>407 ありがとう。
高いね。
購入を考えるしかないか。
ナガオカのような半透明の袋はビニ焼けはかなり起こりにくいようだが
エミライ「インチキはアコリバから学びました」(笑)
アマゾンでグラシン紙を検索したら、結構引っかかるのがトレーシングペーパーと調理用の紙。
丁度大きさもいいものが検索されたので、ひょっとしたら近所のDIY店にあるだろうと思って行ったら、
サランラップのような箱に入っている33cm×7mの商品があったので、ラッキーと思った。
箱をよく見ると、シリコン樹脂のコーティングがしてあり、
こりゃ、ビニ焼けを起こすかもしれないと思い断念。
店の人にトレーシングペーパーはないかと聞いたら、ないと言われた。
グラシン紙ってあまり見かけないな。
調理器具が揃っているほかの店を探してみようと思う。
>>408 自作でいいんじゃね?
A3ノビ用紙なら30cm以上をカバー!
自作なら意匠は自分で自由だから、サイズも使い勝手を良くできるし。
アマゾンだと100枚で1760円
検索結果は、貝印 クッキングペーパー DL6300が使いやすいグラシン紙だと思います。
シリコーンコーティングがしていない。幅33cm+長さ7m。
糊しろが両端1.5cmもあるので塗りやすそう。
レコード保存用にグラシン紙が最適と言われているが、
紙の毛羽立ちがなく、透けて見えるから、最適という意味でしょうかね。
シリコンコーティングのクッキングペーパーを1年くらい消しゴムに巻きつけて放置してみたけど
消しゴムが張り付く様子がないんでビニ焼けは今の所大丈夫そうではある
コーティングしてても通気性や浸透性があるみたい
帯電列で塩ビとシリコンが近いんでレコード取り出し時の静電気は少なくなるけど、
逆にジャケット取り出し時に静電気が起きるかも
>>391 調べてみてわかったんだけど、ビニ焼けの白濁部分は、どうやらレコード盤の平面部分に貼り付いた異物だね。
これが悪さして、ゾリッゾリッと言うノイズを発生させている。
除去方法は、GUM歯ブラシ・固さふつう・による超音波ブラッシングでも多少イケるが、
どうやらアルコール洗浄の方が効果がありそうだ。
アルコール洗浄だと、確実に少しずつ白濁部分の異物が除去出来る。
GUM歯ブラシ・固さふつう・による超音波ブラッシングだと、後に白い粉が盤表面に現れ、これが白濁部分を形成していた異物だ。
ただ、この方法だと除去出来る量が曖昧で、効果が小さいときがある。
アルコール・ボンドパックだと、表面の白濁部分が剥がれる場合があるが、しつこく貼り付いている場合は繰り返しやっても効果が出ないようだ。
したがって、ビニ焼け盤のクリーニングは、盤表面の白濁部分の除去と溝の中に詰まった異物の除去の2つを行う必要がある。
表面の白濁部分の除去には、アルコール・ボンドパックで効果を上げる場合があるが、しつこく残る場合はアルコール洗浄と毛先が太めの歯ブラシによる超音波ブラッシングが効果を上げる。
これには超音波洗浄は殆ど効果がなさそうだ。
>>417 その物質の物性はアルコール、テレピン油にわずかに溶けるだけしか書いていません。
ただし分析化学の文献に溶剤は書いていました。家庭内では絶対に苦情が出る溶剤です。
>>190 この動画のぴったりサイズ?の容器にこそ興味があります
紹介してくださいな
>>420 >>207で紹介しているはこはどうですか?
検索してみてください。
ありがとうございます
>>190の続編てのが期待に一番近いかな
水流を起こせば盤は回転させなくてもいいんですかね
でも惜しいなあ
もうちょい深ければ完全水没させられるのにね
今日の超音波クリーニング。

やっぱりBlumwayと33cmのボールの組み合わせはイージーでいい。
>>424 水で流したくらいでは、クリーニングには成らない。
細い水流に混じった小さな気泡が破裂するときに
超音波を発生するとかなんとか ムニャムニャムゥ、、、
で演奏時にはこんな対策やってみた
ヤマハ YP-D10 です
https://imgur.com/fMRa8o6 お手軽インスタントなオイタですけど
https://imgur.com/WLyN3w8 安っちいアームながらこういう使用には十分クォリティ?
https://imgur.com/Nz1FucL 見た目悪いけど10円玉2枚ホットグルーでとりま5.7gの針圧(毛圧)かけてます
これで何百本かの超極細毛が溝の底やのり面に届いて
小さなチリを搔き出すだろうと期待してるのですが
針圧(毛圧)の調整をプラスマイナス今後いろいろやってみます
アナログプレイヤースレとマルチご勘弁
途中経過ですが……
1枚から数枚のまるごと超音波洗浄機と併用してるので
(別スレで報告したっけかな?
https://imgur.com/tvw2QmS https://imgur.com/kmHBjbH パチパチノイズ低減の効果は両方が貢献しているでしょうか
目に見えるようなホコリは確実にお掃除しています
ただし毛圧(ブラシ圧)は画像の硬貨2枚では不足で
片面25分の演奏終了に追いつけません orz
今3枚&インサイドのキャンセラ0gで調整中調整中
これの圧が重すぎて回転に影響するようでは本末ttだし
慎重にやってます
俺的にクリーニングで重要なのはほぼ確実に使われたであろうレコードスプレーの除去だが
それは超音波じゃ駄目なんだよな
>>435 レコード自体が油性なので水にはじくんだよ。
>>434 レコードスプレイの成分は、カチオン系、ノニオン系の界面活性剤がほとんどです
アルコールに溶けますから、アルコールをを含む溶剤か、中性洗剤+超音波洗浄で簡単に落ちます。
特にアルコールを含むレコパックなどのパック方法は、この手の添加剤に対して得意なようです。
昔、帯電防止と摩擦低減に効果があるフッ素系を使用したTechnics DPというレコードスプレイがありました。
本当に効果があったのですが、レコパックを施すと静電気が発しました。
Technics DPの成分がレコパックに持っていかれたようです。
中性洗剤+超音波洗浄も同様に、乾燥後は強烈に静電気が発生しました。
ちなみにレコードスプレイの溶剤はアルコールがほとんどで、あとはフロンガスです。
カチオン系、ノニオン系の界面活性剤は水に溶けるの?
>>438 溶けますよ。
ただ、拭き取ろうとすると横に広がるだけです。
剥ぎ取る、溶かして洗い流す方法でないと、除去できません。
カチオン系は普通のアニオン系(中性洗剤など)と電気的にくっついて、洗い流しやすくするし、
ノニオン系はアニオン系の長鎖炭化水素で馴染みやすく、親和性が高いです。
そういう理由もあって超音波洗浄で中性洗剤を使っています。
おすすめいたします。
>>419 家庭で使用する以上、溶剤の種類は選択する必要がありますね。
少しでも溶けるのならアルコールを使うべきでしょう。
考え方としては、アルコールで白濁部分の表面を溶かして薄くし、GUM歯ブラシ・固さふつう・による超音波ブラッシングで溝を覆う部分を砕けば、ある程度除去出来るかと。
で、砕いた後の(おそらく)粉末は弱アルカリ界面活性剤洗浄で大方除去出来るはずです。
これまでビニ焼け盤およそ40枚のクリーニングに取り組んできましたが、あと2枚ほど、このゾリッゾリッと言うノイズが大変気になるものが残っています。
アルコールを使って、最後までノイズ除去をしたいと考えています。
>>441 大変ですよ。
アルコールは少しとけると言っても溶けにくい部類ですから、
蒸発を抑えるためにアルコール糊パックが有効なんです。
どうして皆さんが忌避するのか解りません。
数回パックすれば無くなります。
私が行っているアルコール濃度は30%です。
粘度を気にしなければ40%もできます。
今もなお超音波洗浄は振動で汚れを落とす(落ちる)と勘違いしている人がいますからね。
盤まるごと超音波浴
次にファインバブルシャワー
アンドツインバード
これでキマリ!
>>433 手でブラッシングする場合、力を入れ過ぎると毛先が寝てしまって、思ったより汚れが落ちなかったと聞いています。
書き込みの条件なら毛先が寝てしまうことはないようですが、加重過ぎて毛先が寝ないように注意しなければいけませんね。
>>445 です
ファインバブルは未体験
すぐに小穴つまりそうで
ふつうのシャワーで十分かと
成果は
>>433 の通りです
10円玉この位置に3枚で10.44g
回転終わりまでカートリッジの進行に同調できました
毛の数の多さを信頼して形状劣化は心配していません
しばらくこれで続けてみます
>>450 不要
というより害悪でしかない
固着してノイズになるから中古でスプレー使われた盤の洗浄で難儀することになる元だから絶対にやめれ
レコードスプレーはレコードだけではなく周辺にも多くの害悪を及ぼすから絶対に使ってはならない
とは言えみんな使い方が間違ってるようだが
たいていはレコードにジャバジャバかけて平然としてる模様
ベルベットのクリーナーに少しかけて使うのが本当らしい
もちろん俺はそれもやらないが
>>450 静電気除去したいなら、除電ブラシか電気式の除去装置使え。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x1015644953 これは、こんな値段がするの?
もらった同じレコードにカビが散見される。
色々面白いレコードがあるのだけれども、
どれもカビだらけだww。
ビニ焼けのブツがない。サンプルが欲しいのだがw。
中には25cm盤で、ステレオチェックレコード(初期のアンサンブルステレオの付属品だと思う)があったり、
ワルター指揮、ニューヨークフィルの運命があったり、
ルービンシュタインのショパン、コンチェルト1番、モノラルがあったり。
砂粒がついているんだよなあ。
1000枚とはいかないが、糊パック+超音波クリーニングしながら聞くとなると、
自分の寿命が先に来てしまいそうだ。
連投になるが、
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b389033161 これの25cm盤。
まだパックが乾いていないし、超音波を掛けようにも25cm盤だから、レコードを吊って洗浄するか。
文面通りの価格的な意味だな
売るときに値はつかないが入手するにはいいんじゃ
ここのスレでは超音波洗浄が主流だがどれくらいの効果があるの?
自分はバキュームマシンを買ってしまたから超音波洗浄機の効果がわからない。
「バキューム+アルコール+システマ」でクリーニングするとここで問題なってることは大概クリアできちゃうんだけど自分のレベルが低いのかな。
両方持ってる人いる?
効果の差を教えて欲しいな。
再生して針に何もつかないクリーニングが正解。
針になにか付くようならクリーニングは完了していません。
>>461 > 再生して針に何もつかないクリーニングが正解。
> 針になにか付くようならクリーニングは完了していません。
さすがは完璧主義者!
>>460 超音波洗浄とバキューム洗浄ではアプローチが違って汚れの種類の対象が違う
固くこびりついた、ブラシで擦っても取れないような汚れを超音波衝撃を水を媒介して直接当てて取るのが超音波洗浄
バキュームは盤を回転させながら自分で洗浄液でブラッシングして濯ぎ後に汚れが溶け込んだ水ごと吸い込むもの
(ちなみに水道水の中にはミネラル成分が含まれていて濡れたまま乾燥すると白いスケールとなって固着するから最後の濯ぎは精製水で)
つまりバキュームではブラッシングで取れる程度の柔らかい汚れしか取れない
逆にブラシで取れるような汚れだけしか無い物を超音波洗浄にかけても完全に取ることは出来ない
やわらかい故、粘着して剥がれないから
メガネや腕時計を超音波洗浄でかけると黒い汚れが溶け出すが、この汚れはいくらメガネや腕時計をブラシで擦っても取ることは出来ないけど(メラミンスポンジなら取れるけど傷がつく)
油汚れが付いててもベトベトは超音波洗浄では取れないのと一緒
て適材適所で使い分けないといけない
>>460 油汚れといえるだろうけれど、可塑剤も油汚れに分類できる。
超音波洗浄で水を使うと油汚れは取れないので、中性洗剤を混ぜて使っている。
ミセル化を促進させるため超音波洗浄に中性洗剤を使うのは非常に有効。
工業用の超音波洗浄機の取説でも推奨されている。
レコードでは非常に光沢がよく仕上がる。曇りがなくなる。
バキュームでブラッシング洗浄した後に超音波洗浄するのがベストだろうけど、お手軽に洗浄するならバキュームだな。
まあ大概の汚れは落ちるしノイズも除去できる。
なんといっても乾燥させる必要がないのがいい。
超音波洗浄機買うなら値段は2倍はするけどバキューム買ったほうが結局はお得よ。
中古でお試ししてもいいかも。
ヴァカヴァカしいだけです
ツインバードで同等の効果あるっしょ
>>463 的確な分析!
どうしてそんなに賢いの?
>>465 レコード専用の超音波じゃなくてもBlumwayなら安いし、一緒にそろえてもいいのでは?
バキュームをする前に超音波洗浄して。バキュームの順序がいいと思います。
わたしはバキュームの必要を感じていませんが、時間の短縮にはなりますね。
超音波洗浄で油汚れには、以下のようなものがうられています。
超音波洗浄器用強力洗浄液 サンメガウォッシュ アクア(下から2番目)
https://www.san-nishimura.co.jp/item/item_fix/cat27/ >油汚れが付いててもベトベトは超音波洗浄では取れないのと一緒
と、書いている人がいるが、水ではなく洗剤を使うべきだよ。
専用のものは高価だが、食器用の洗剤で十分。
>>468 超音波洗浄なら完璧なんだろうけどやっぱ面倒なんだよね。
システマ使って洗浄、超音波で洗浄、水分取って乾燥、とか手間がかかる。
バキュームマシンだと洗浄から水分取りまで全部マシン上でできちゃう。
自分のクリーニング方法は、ターンテーブル回しながらアルコール+システマで盤を3分間くらい洗浄。
バキュームかけてから精製水を使いハケで軽く洗浄して再度バキューム。
その間ずっとマシンの前で作業できる。
洗浄中はボーッとしてるだけ。
ビニ焼け除去についてだが、
初めてビニ焼け除去剤を配合した時、PVA糊パック剤に直接配合したが、
良く混ざっていなかったらしく、盤面に塗布展開したとき、溶け残るのツブが見られた。
改良として、あらかじめ湯にビニ焼け除去剤を溶解した後、PVA糊パック剤と混合したが、
水を加えたので粘度が低くなってしまったが、前回見られたツブは無くなっていた。
前回の2倍の濃度を添加している。
剥離が楽しみ。
>>469 それで望むクリーニングレべルならいいと思いますよ。
私の場合、ピアノの先生からもらったレコードは、カビだらけで、一部細かい砂や指紋があったり、
なかなか思ったようなレベルのクリーニングにならなくてねえ。
結局、短時間で色々試して到達した方法なんですよ。
今日、レコードをあさっていたら菅野沖彦氏が市場に初めて販売したデジタルレコーディングのレコードが出てきた。
SUGANO RECORDというレーベルで出していたんだなあ。
だれか買ってあげたら?
修理しなければならないけれど。
無念!ジャンク(電源入らず) CLEARAUDIO / SMART MATRIX PROFESSIONAL 7、10インチ用オプションノズル付
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r1029669262 > 水ではなく洗剤を使うべきだよ。
と書いてる人がいるが、超音波洗浄で洗剤なんて使ったらダメ
というか二度手間になって完全に無意味だからやめた方がいい
洗剤の不純物がついたまま乾燥させる事になりそれこそ固着して取れない汚れをつける事になる
ガラスにつくウロコは水道水に含まれるミネラル成分でスケールと言われるの
世間一般では間違ってカルキと言ってる人もいるがカルキは揮発性の物でこれとは全く違うもの
そして洗剤が含まれた水道水はこのウロコを更に固着させる事になるので洗剤を入れてはいけない
もし入れて超音波洗浄をした場合は、その後精製水で何度も更に洗浄しないといけないので二度手間もいい所
みんなの悩みの種プチプチノイズの元凶が落ちればいいのです
>ミネラル成分でスケールと言われるの
これなんかノイズと無関係なミクロの大きさでしょ
ほんと無関係で迷惑な書き込みやめてね
>>474 私の場合は書いてある通りにしているぞ。常識。
さらに再び糊パックをしている。
糊パック⇒洗剤で超音波洗浄⇒水道水ですすぎ⇒鶴首洗浄瓶でイオン交換水すすぎ⇒乾燥後再び糊パック。
このルーチンを繰り返す場合がある。回数を重ねるほどノイズが少なくなる。
普通は洗剤を付けたまま乾燥をするかい?誰でも洗剤で洗った後は水ですすぐ。
最初に糊パックする理由は、ひどいカビと小さいビニ焼け除去のため。
イオン交換水での洗浄は一回だけでもよく、乾燥後はスケール付着はない。何度もする必要はない。
やり方は、レコードを垂直から少し斜めにし、一番上から音溝全部に当たるように細かく振りながら、水を注ぎ、
右の方へ洗浄液を盤面に流し、下の方に着いた水道水も同時に洗い流すようにし、同時に鶴首洗浄瓶を同じ方向に向かってイオン交換巣を流していく。
左も同じにすすいで、裏面も行う。
これで鶴首洗浄瓶ですすぐと一枚につき100ml以下で済む。
また、再び糊パックするのでスケール(水シミ)があったとしても除去できる。
イオン交換水は20リットルで2000円で売っているし、
自動車用洗浄用のイオン交換フィルターは2万円以下で売っている。退社したら自動車用を買うつもり。
反対に質問。
精製水ですすぐとあるけれど、鶴首洗浄瓶はつかっていないの?
どういう道具をつかっているのですか?全然やったことが無いように思えてしまう。
対象のレコードはかなり多湿の所で保管されていたらしいブツ。
きれいにクリーニングをするのなら、クリーニングの各工程で問題点を回避するのに、これくらいの手順を踏むのは当然と思うが。
汚れの程度が低いのならいいのだけれど、効率重視では難しい。中古レコード屋ではない。
相手にしているのは、
1960年代初期のレコードを含み、25cm盤モノラル、25cm盤リビングステレオ盤等も含まれる。
超音波爺さん、ボンドパック馬鹿・・・いろいろとおられますね
ボンドパックなんて30年以上前に既に誰もやらなくなったほど危険な行為だからなw
当時は雑誌とかでも取り上げられ専用ボンドとか沢山出てたが数年で誰もやらなくなったアホな行為
それを今になって言い出すのは最近始めた初心者以外いない
不器用な無能な奴がまた来てる。
最近のボンドパックはアルコール利用した方法。
無能には理解できまい。
レコードのクリーニングか。
しばらくやってなかったな。
最近レコードプレーヤーをヤフオクで落札し、ターンテーブル部分だけを取り出してレコードのクリーニングに利用しようと改造中である。
HumminGuru
ってどこで買えますか?
ググっても出てこん・・・てかでてくるのは3000ドルとかなんだけどorz
>>487 HK$=香港ドルな
1 香港ドルは14.86 円
まあ大概の人はバキュームマシンで満足すると思うよ。
ボンドパック派はクラシック好きで神経質な人か、大音量で聴ける環境の人か、暇な人。
このスレはお手軽派と繊細派が混在してるから面倒。
Vpiと超音波洗浄機両方もっているけど、ほとんどVpiで事足りてる。今まで1000枚ほど洗浄したけど超音波を使ったのはテスト洗浄の5枚だけ。
超音波だけの人は水切りどうしてるの?
ウェス等で拭き取るのか?
レーベルカバーしたままだとやりにくかろう
>>492 ある程度ブツを振って水を切り、
レーベルカバーを外し、
スタンドに立てかけてビニール袋をかぶせて自然乾燥。
音溝にアンタッチャブルを基本としているから、ふかない。
どうしても移動などで触れなければならない時にはベンコットを使って触れる。
とまあ、音溝を傷つけないように気を使っています。
クリーンメイト NEO 使ってる方いらっしゃいますか?
VPIとドッチが良いのか悩んでます。
流石に両方購入するのは厳しいので。
グラシン紙を使った内袋について。
トレーシングペーパーで内袋を作りました。
紙の値段が高価でしたが、50cm×38cmの紙を2枚、スティックのりで貼り付けて、あとで所定の大きさに切りました。
これはグッド。
そして、料理用のグラシン紙をつかったロール紙33cm×40mを購入し、二つ折りにして同じスティック糊で貼り付けましたfが、
シリコーンコーティングのため、接着できませんでした。
コーティングしていない料理紙を購入するか、他の接着剤を探さなければなりません。
脱力。
その問題があったか
RTVシリコーンなら着くのかな?
>スティックのりで貼り付けて、あとで所定の大きさに切り
これではジャケットに入らなくなるんジャマイカ
30cm+正方形にミミつけて折り返して接着じゃないの?
みみ付ければセロテープでもいける
>>497 ご心配なく。
まず、B0の画用紙を使って、30.8cm×30.8cmの大きさに切って型紙を作ります。
次に50cm×38cmのトレーシングペーパーに、先に作った型紙を耳があるように位置を定めて載せます。
そして、スティック糊を使って糊付けし、型紙を除いてもう一枚の紙を載せて糊付けします。
両端は約3cmののりしろに糊を付けたことになります。
もう一つの型紙を作ります。
大きなコンパスを持っていないので画用紙にレコードを載せて、ボールペンで縁取りし、切って型紙を作ります。
糊付けしたトレーシングペーパーが乾いたら、30cm径の型紙を入れます。
30cm径の型紙は、余分な部分を切るための位置決めに便利。
次にA3対応のギロチンカッターで、糊付けしたところは、約5mm幅で残しておき、余分な部分を切り落とします。
これで完成。
A3対応のギロチンカッターが手元にあったおかげで、
工業製品とはいかなくても仕上がりは満足しています。
A4のギロチンカッターでは長さが足りないので使いにくい。
ギロチンカッターは結構値が張るので、長い定規とカッターで切るのがいいでしょう。
>>494 値段にこだわらなければ絶対クリーンメイト NEO。
私はクリーンメイト NEOの前身のアイコールクリーンメイトを持っている。
VPIは持っていないので実際の詳細な比較はできないがクリーニングのしやすさが段違いだと思う。
ユーチューブでVPIのクリーニング方法を見るとターンテーブルが箱の中のあるのでブラッシングがしずらそうだ。
バキュームマシンでもアルコールとシステマによるブラッシングは重要なのでターンテーブルが上部にあり
色々な作業がしやすいアイコールのほうがいい。
あと吸引モーター音がでかいのは結構問題なので減音(90dB→65dB)されてるのは圧倒的なメリット。
>>494 VPIユーザーだけどクリーニングしづらいなんてことは全くないですね
箱の中と言ってもたかだか数センチなので全く問題なし
ダストカバーが付いてる方がホコリが防げてアドバンテージだと思います
VPIがお勧めですね
あのテのマシンはきれいにしたつもりなったつもりというパフォーマンスです
>>500>>501
とまあこのように意見が割れて(それ自体はいいのだが)スレが荒れる元になる
きっと大差ないから好きな方買えばヨシ
VS超音波やボンドパック然り
別になんでもええで、好きなの使えや、メリットデメリット長所短所はある
VPIとクリーンメイトの両方を使用したことのある人しか正しく評価できないわな。
料理用のグラシン紙をつかったロール紙。
アラビックヤマトでも簡単にはがれる。
次はセロハンテープを試すしかないな。
これもはがれそう。
やっぱりシリコンコーティングはセロハンテープでも付かない。
トレーシングペーパーを購入する。
時間かけて50枚くらい60cmguraiwoやって切ったが、無駄になった。
他に利用方法を考えなくては。
シリコーン用の接着剤はあるよ
エッチ用途はシリコーン素材のがけっこうある
DIYの接着剤のコーナーを探したが、あほらしい値段だったね。
135gで1048円だよ。
料理用クッキングシートは33cm*40mのやつは768円。
コスト的にアンバランスなので、ホッチキスで縁を止めることにしました。
シリコンシーラントじゃダメなのか?
200円くらいでそんなんなら死ぬほど使えるぞ
一度開けるとうまく密閉しないと固まるけど
ちなみに変成シリコン系のスーパーXなんかでも付きそう
>>511 1048円はそのスーパーXの値段です。
デカすぎw
普通は300円くらいの買うぞ
まあ、大量に必要ならやっぱシーラントだな
小さい奴は確か380円ぐらいだった。
ボンドG17と同じように、
薄く塗った後、少し待って、半渇きの状態になってから接着してくださいと書いてあったので、
めんどくさいと思った。
週末にやって見るよ。出来たら30枚張り直しだよ。。
実際にクッキングシートをスーパーXでつけてみたけどちゃんとついてる
シーラントで試そうと思ったけど一度開けたヤツは蓋をしたつもりでもカチンカチンでダメだった
接着剤はどのタイプでもだいたいデカいのは高いよ
>>465
洗濯用の超音波振動子と33cmのステンレスボウルでやっているから、
7000円ぐらいの費用かな。
専用の市販品よりは安くつく。
一昨日25cm径のLPと17cm径のEP用のために、
28cm径と20cm径の金網のザルを買ってきた。
これで全種類のレコードに超音波がかけられる。
超音波使ってる人は精製水使ってんの
水道水はよくないかな
レコードの汚れが完全に取れると水をはじくので精製水は必要ないと理解できる。
中途半端な洗浄で汚れがまだ残ってる状態では水はレコード盤にまとわりつく。
この場合は精製水ですすぐかクリーニング方法をもう一度考える必要がある。
>>518 水道水と中性洗剤で超音波洗浄しているけれど、
水津水でゆすいだ後は、水をはじくようになりますが、水シミが残ります。
水道水中のマグネシウムやカルシウムなどの塩分がその原因。
結晶化しているからあまり良くないですね。ノイズの原因にもなるし、硬いから音溝を傷つける恐れもあります。
それを防ぐために、純粋やイオン交換水、精製水で洗い落しています。
水を使うレコードクリーニングは最後にイオン交換水などでゆすいだ方がいいですよ。
この頃の洗車も最後はイオン交換水で洗い流すということもガソリンスタンドで見受けられます。
>>519 > レコードの汚れが完全に取れると水をはじくので精製水は必要ないと理解できる。
脳みそも超音波洗浄してなさいw
>>510 >料理用クッキングシートは33cm*40mのやつは768円。
内袋1つ作るのにこれ2枚と高価な接着剤が必要なんだべ?
内袋にそんなに銭かけるのは何故なんだ?
日本製 グラシン紙 【12インチ】 (500枚) 【300mm×300mm】\2.740
12”(30cm/LP)用薄紙インナー(内艶角丸み仕様)両穴付き※新サイズ 50枚 \2.200
紙のインナーの内側にグラシン紙貼り付ければ良いだけ
端々をスティックのり(PIT 消えいろタイプ)で紙と紙なので問題なく接着出来るよ
難しく考えすぎているようだけど、実際作ってみたことないのかな?
作成時は皮脂を予防する意味で、グラシン紙挿入時はニトリル手袋くらいはあった方が良いと思う
まあ、グラシン紙のインナースリーブひとつ\60、作業代抜きだがそんなに高価か?
40m か
cmと見間違えた orz
でもインナーなんて作らん買う
>>524 既製品は高いw。
インナーを作る意味は、もともと入っていたインナーのレコードはかびだらけだった。
しかも小さなビニ焼けも見られる。
また、紙袋に入れてあったものは紙袋自体がボロボロ。
そうのようなレコードを300枚ぐらいいただいた。
数十年針を落としていないのだろう。
そのようなインナースリーブにせっかくクリーニングしたレコードを入れたくないでしょw。
数も半端でないから自分で作る。
>>523 自分で作ると2/3の値段でできる。
数も半端でない。
別の人からも数百枚もある。
40年以上前に購入したレコード何十枚もあるけど
ビニ焼けとか全くないよ
保存の仕方が異常に悪いんだろうね
>>527 枚数のことを考えたら結構な差になる。倹約するのも、コスト意識なしも自由。
ターンテーブルはコスト意識はなかったな。あ、少しあったわ。
寺垣プレーヤーのΣ2000を持っている。Σ5000は高いからなあ。
しかし貰い物だよ。
>>529 そうだと思う。倉庫に仕舞ったままだったのでしょう。
アンサンブルステレオに付属していたようなチェックレコードがあったり(ピンポンの音が左右で鳴る音入り),
ワルター指揮、ニューヨークフィルの運命、25cm盤があったり、
これも汚かったが、リビングステレオシリーズの南太平洋、
その他有名ピアニスト、ピアノの教則本見本演奏版の超古い奴などなど。ほこりがいっぱいで、ビニ焼け+カビ付きです。
モノラルからステレオに移る時代からのレコードが結構あるので、60年前ぐらいからでしょうね。
外袋のビニール劣化もひどいw。
ここまでクリーニングをやってやろうという人間の手に渡ったから、廃棄処分にならず、よかったと思いますよ。
>>530 > ここまでクリーニングをやってやろうという人間の手に渡ったから、廃棄処分にならず、よかったと思いますよ。
良い言葉だね
レコードクリーナーさんたちも救われる言葉だと思います
Σ2000のアームはピュアストレート。
音の出もばっちりだ。
数百枚のインナーDIYか・・・
手間暇時間考えると買った方が良くないかい?
今日もレコードを洗って…宮城県登米市・ショップ リバー サイド
https://www.yomiuri.co.jp/local/michinoku/20220117-OYT8T50266/ 毎日の退勤後に浄水場の濾過膜も使って探求を続け、たどり着いたのが
医療用にも使われる「限外濾過膜」で濾した最高純度の浄水だった。
定年して開いた店を訪れた客は、こう口をそろえる。
「ここはCDで流してんのすか? ノイズが全く聴こえねえな」
>Σ2000のアームはピュアストレート
違うんじゃ?
どこ情報よ?
>>535 そう思うんだけど。
貧乏人には明日はない。
>>536 VPIらしきものを使っているようですね。
1970年頃のレコードで異様にトレース音の大きなのがあるんだけど、何度水洗いや中性洗剤でクリーニングしても取れない
傷以外のパチパチノイズは取れたけど、そう言うもんなんですかね~
何かやれるケアがありましたらどなたか教えて下さい。
米盤や英盤は素材が悪いのかプレスが悪いのかたまにそういうものがあるね。
日本盤なら針が悪かったんだろうね。
第一次オイルショック・・・1970年代初め・・・俺まだ幼稚園児w
で中古レコードを買うとその当時のレコードは薄々なのが結構あるよね
ABCD包囲網とか・・・日本は大変だったんだね
一時期のアメリカ盤は売れ残ったレコードを溶かしたのを使ってたとか聞いたことがあるけどそういうのじゃないよね
カッティング時に使ったオープンリールテープレコーダーが真空管使ってるんじゃね?
ロンドンの、2枚組2000円のシリーズで、モントゥーの2枚組が真空管のハム音を結構含んでいた。
これはクリーニングでは取れず、EQでハム音出す周波数を絞れば低減できる。
>>540 摩擦抵抗が大きくなっているのでしょうねえ。
レコードスプレイ成分は帯電防止剤ですが、それが潤滑剤となってSN比が向上します。
しかし均一に適量というのが難しい。
>>541 なるほど、自分もヤフオクで中古入手したもので前までのオーナーさんがどういう風に聴かれてたかは分からないのですが、使用した針の影響って結構あるんですね
>>542 1970年は自分は生まれた年です
ちょっと盤質にムラがあった時代なんでしょうか
日本も苦難の時代を乗り越えてきてますね
>>543 レコードは日本のソニー製です
古いレコードを溶かして、という事はある意味ですごく歴史を刻んで来てるんだなと
このままでも味があって良いかもしれないですね
>>544 真空管のハムノイズが乗ってたのならそもそも盤面に刻まれちゃってる事になりますね
ノイズ取れるソフトもなくはないんですが、自然に加工出来るかどうかですね~
>>545 この場合スプレーが効果があるかもしれない、という事ですね
ナガオカのスプレー型のクリアトーン買って試してみるのも良いかも…
みなさんご指摘、アドバイスありがとうございます!
大変色々勉強になりました
またゆったり出来る時に幾つか試してみようと思います
アナログレコードのノイズの原因と症状はいろいろあって
それぞれに対策をつくした結果
どうしても残るノイズはもう受け入れる心境になりました
よくテレビでレコードかける時の映像で針落としてからパチパチ鳴るのあるじゃない。
あれアメリカ(または米盤)のイメージだよね。
日本盤もスプレーやカビの影響でパチパチするけど丁寧にクリーニングするればぼノイズレスになる。
米盤は例外を除いてほぼ無理。
日本のビクターから1965年に発売されたエルビス・プレスリーのレコードを5年前に
中古で買ったんだがノイズレスで日本のレコード製造技術の高さに驚いた。
頭の無音溝でぱちぱち言うのが多いね
曲頭に近づくにつれ少なくなってく
米盤は盤質は悪いよ
国内版もそれよかマシって程度
だいいち盤質以前に音質がイマイチ、これは盤質の悪い米盤のが音が良い事もよくある
欧州盤、特に仏盤あたりが盤質、音質ともに良い
最近組み物のクラシックLPを落札して入手した。
24枚で1000円!
本来、3巻36枚のところ、1巻と3巻のみの24枚。
目当てにしていなかった盤に、結構良いのがあった。
クルツ指揮フィルハーモニアo.のチャイコフスキー:3大バレエ抜粋の1枚。
カビが生えているのでクリーニングの必要があるが、傷の無いまっさらな状態。
そのまま聞くと、カビの所でパツン、パツンとノイズが発生するが、その他の部分では全くノイズが無い。
超音波洗浄でまっさらになるだろうww
解釈は際立った自己主張は見られないが非常に音楽的である。
名前は知っていたが今まで取り立てて注目してこなかっただけに、この演奏には驚いた。
1950年代後半のEMI録音の音質はあまりパッとしないのでEQで思いっきり調整すると、実演さながらのふくよかなサウンドにチェンジ!
これは超音波洗浄をするのが楽しみだ。
ちなみに「眠りの森の美女」と「くるみ割り人形」では、ある程度音質に違いがある。
自分は水の劇落くんとシステマで水洗い、
仕上げにキッチンペーパーで拭いて終了なんだけど
ここ10年くらいにプレスされたレコードに限って、
クリーニングすると逆にバチバチノイズが増える盤ない?
レコード時代の盤だとクリーニングすれば必ず綺麗になるのに、
同じ方法でも逆効果になるというか。
同じような経験ない?
>>558 塵や汚れが落ちて埋もれてた傷が出てきたのかな
>>556 原因とその原因物質について書いていない。表面的な見解のみです。
>>558 水洗い後は当然イオン交換水などの精製水でしょうか?
>>557 >>561 御回答ありがとうございますm(_ _)m
webでいろいろ調べたけどよくわかんないんだよね
まずはキッチンで台所用洗剤でジャバジャバ洗った
レコードからグラシン紙のインナースリーブに入れようと思います
でそのグラシン紙のインナースリーブがまたお高いですね・・・
ヤフオクのが一番お安いけどどうなんだろうと・・・品質的に
>>563
ヒントをあげましょうか?
あの白いブツはアルカリ物質でも洗剤でも落ちない代物です。
ましてアルコールでも溶けにくい物質です。
レコード以外でも毎日見かけています。
グラシン紙のインナースリーブは高価ですね。
タワーレコードのグッズを見ましたが、10枚で1680円です。
わたしのように自作されてはいかがでしょうか?
クッキングペーパーで痛い目にあっています。
私は次回、次のように計画しています。
トレーシングペーパーなら30.5cm×46mのサイズがあるので、
(アマゾンで pudcraft トレーシング ペーパー(55g) で検索)
30.5cmの横幅は。のりしろを考えると厳しいかもしれませんが、45mならば
60cm長さで二つ折りにして両端を糊付けすればよいと考えています。
46×100÷60=約75枚
お値段は、送料が無料で2530円、約34円/枚。
30.5cmは厳しいので42cm幅の品物があったと思いますのでこちらが作成しやすいかなと思います。
両端を切ればいいですから。
自作は嫌いだというお方は仕方ありませんですけど。 ついこの間、3つのLPを超音波洗浄した。
〇ニコレ(fl)シュタイン(Hp)リヒター/ミュンヘン・バッハo.のモーツァルト:フルートとハープのための協奏曲
〇フェラス(vn)シルヴェストリ/フィルハーモニアo.メンデルスゾーン:vn協奏曲他
〇ミルシュタイン(vn)バージン/フィルハーモニアo.メンデルスゾーン:vn協奏曲他
元々汚れが軽かったので、かなり綺麗なサウンドを楽しめるようになった。
モーツァルトの方は以前から名盤との誉れ高い自由自在の演奏だが、やや音質にクセがあり、ちょっと窮屈なサウンド。
EQで調べてみると、高音域が過剰で低音不足。
調整すると素晴らしいサウンドに。
モーツァルト:フルートとハープのための協奏曲は、最近他にも数枚のLPを入手したが、このニコレ盤が断然良い。
躍動感があり、自由自在の表現が演奏に没入させてくれる。
フェラスのメンデルスゾーンは、廉価盤セラフィム名曲シリーズの中の最初期の一群の中の一枚。
深い黄土色のケースに収納され、これらの一群の中に、良い音質と思えるものが無い。
廉価盤セラフィム名曲シリーズで良い音を求めるならもう少し後の物が出るまで待たなければならなかった。
このフェラスのメンデルスゾーンも例外では無く、中低音域を中心とした音作りに、各楽器の音色が浮かんでくることが無い。
当時の商品開発担当者には申し訳ないが「この曲はこんな感じ」くらいしか伝わって来ない。
EQでの調整には、高音域と中高音域を上げなければならなかった。
フェラスのメンデルスゾーンを音質調整して、ようやくフェラスのヴァイオリン演奏の真価が垣間見えるようになる。
フェラスはしばしば「カラヤンにこき使われて捨てられた」みたいな書き方をされることがある。
このメンデルスゾーンを聴く限りでは、フェラスは技巧が達者で、早いパッセージも難なく弾きこなす。
解釈は標準的で実直という印象である。
ただ、楽器の音色の変化の面白さを聞き取るにはもう少し録音が良くなければならないと思う。
ミルシテインのメンデルスゾーンの方は、セラフィム名曲シリーズの後発グループの中の一枚で、フェラス盤よりはかなり音が良い。
ミルシテインがバリバリと弾いていたことがわかる名演だと思う。
ミルシテインは、後に1970年代にアバド/VPOとグラモフォンにメンチャイコンチェルトを再録音し、それはそれは美麗な録音と演奏ですでに伝説の域に入っている。
これらのウチのニコレのモーツァルトとフェラスのメンデルスゾーンを音質調整してカセットに録れてみた。
かなり楽しめる音質になったと思う。
デジタルのようなスカスカ感は一切無い。
ビニ焼けはビニールの可塑剤の影響なんだね
国内盤に付いてるインナースリーブはポリプロピレン製だかでほとんど問題ないけど独プレス盤なんかのはビニール製みたいでレコードにくっ付いてビニ焼けしやすいような
>>567 半分正解。
可塑剤と一緒に出てくる物質。
>>567 そう
軟質塩ビと他の樹脂と接触させると樹脂と塩ビが変形溶着する
今、ヤフオクで中央公論社の世界の名曲全24巻が売りに出されている。
全60枚で、内容もよい。
未使用の模様。
入札してみませんか?
>>569 このスレとはちょっと関係ないけどプレーヤーのダストカバーにコード、ケーブル類の跡が溶けたように残ってるのがよくある
コード類の被覆はビニールだからやっぱり可塑剤の影響じゃないかと思う
これも一種のビニ焼けと言ってもいいかと
よくこんなのは見かけるのにネットで検索しても全然出てこなかった
世界クラシック大全集の中のクルツ指揮フィルハーモニアo.のチャイコフスキー:3大バレエ抜粋の1枚。
超音波洗浄をやってみた。
カビが所々に分布していたが、勿論洗浄によって消え去り、再生音の中にカビによるノイズは一切残っていない。
以前から全集ものには注目していて、殆ど未使用の盤が多数含まれているので、全集ものは良好盤を入手するのに良い。
何しろ超音波洗浄後、残留ノイズがゼロになるんだから!
ビニ焼け、くもりはいろんな条件が重なって起きるんだろうけど、盤同士をあまりに詰め込みすぎて保管してると確率が上がるみたい。
cbs/ sonyの紙の入った内袋も評判良くないね。
あとはスプレーをしっかり除去してなくて、放射状に跡が残っているのもよく見る。
プレス時期も再生ビニールをよく使ってた時代の再発は変質しやすい。
今月号のステレオ誌でもECM特集で当時の話があったけど、国内プレスでもバージンビニルはクラシック、その他は再生ビニルを混ぜるといったふうにそのプレス工場ではラインが別れてたそうだ。
もう一つのレコードのクリーニングのスレが消えている。
誰も書き込まないモンなw
わざわざワッチョイスレに行く人はいないよ。
全然目を引くことが書かれていないし。
ワッチョイなんてどうでもいいんじゃ?
アオリ合いが横行してまともな書き込みがなくなったからじゃ?
どうやらレコードをクリーニングして、音質調整してカセットに入れれば、相当良い音で残せることを確認した。
要となるのは、汚れの少ないLPの確保、それにノイズゼロに出来るクリーニング、カセットに入れるときの調整法である。
ウチの装置で聞いた限りでは、録音前の音質とレベルは殆ど変わらない。
>>578 ワッチョイ関係あるよ!
あのスレって、人をバカにするオタクだけを集めようとしていた。
レコード、つーのはパチパチノイズも含めて楽しむモンと思ってるのだが
>>567 ポリプロピレンでもビニ焼けしていました。
>>581 その楽しみ方もあるけど、ピチパチゼロの音でアナログを楽しむ手法もある。
非常に良い。
カセットに録音して贈呈しようか?
>>582 上のURLだけど、あそこは一人二役の自演マンがいるよ
いつも同時に二人入場して、その後、仲良く二人同時に退場している
自演バレバレ
>>585 アマゾンで結構安く売ってる。
中古品だけど1万8千円あれば手に入る。
>>588 これからも使い続けようとする人はいいけどね。
お渡しするのなら非圧縮の音楽データーの方がいいですよ。
レコードの音質を伝えたいのならハイレゾフォーマットですな。
録音可能なオーディオインターフェースをそろえたほうがいい。
>>590 テープはまだ売っていますか?
うちにはSONY 6台。パイオニア 2台あります。
BS放送、CSラジオ、演奏会の生録のテープがありますが、
はやくHDDに移したほうがいいかも。
>>591 今のところ新品未開封のストック残りこれだけ
なんだか海外の奴が買い始めてるらしいからメルカリでSONYとTDKを漁ってる(60~90は出品が少ない)
maxellは品質が良くないからやめた方が良いと昔言われ避けてるよ

>>591 追記だけどDATはモノ自体の寿命が20年ほどと言われているから、長期保管しているなら早めに古いモノと長尺テープのデータはバックアップおすすめだね
>>593 そう思いますねえ。
DATテープも各社技術力がわかりましてねえ、DENONのテープはテープエッジから粉が出てくるので、
回転ヘッドを見ると、テープが走った後に線状の汚れがついているのですよ。
sonyのサービスマンはDENONのテープは良くないって言っていましたねえ。
しかし最安値でしたから、多量に使用していました。
あと、難しかったのがPCMプロセッサーを使った録音。
ほとんどが演奏会の録音でした。これは全部他人がした録音。
これをCD-Rに焼きなおす依頼で、知人からPCM-553ESDを借りてSPDIF出力をオーディオインターフェースで取り込みました。
ところが、DATとちがって、データーの取りこぼしでドロップアウトが結構ある。
これを修正するためにベータデッキのトラッキングを少しづつづらして、数回パソコンに取り込み、
マルチトラックの編集ソフトを使って、ドロップアウト個所を別の録音したトラックにデーターを入れ替えながらしました。
レコードをクリーニングしようと再び思い始めたのは、
歌のお師匠さんが歌っていたレコードをヤフオク!で発見したのがきっかけです。
どうせ、機械音痴のお師匠だし、自分の歌った演奏会は記録として残していないのだから、CDで渡すか、というのがきっかけです。
やってきたレコードはひどい状態。何度も書きましたが、見た目はきれいですが、針飛び多発。針先に赤い紛対付着など。
それでこの一年で安い中国製の撹拌機を買って、ポリビニルアルコール糊を攪拌するようにしました。
持っているレコードや、もらったレコードもクリーニングしてデジタル化するかということになりました。
あと、自分が録音したわけではないのですが、やらなければならに事はオープンテープで収録したソフト。
往年の有名な日本人演奏家の録音がありましてねえ。デジタル化した後はトーホーとゲー大に納めようかと思っています。
市販のソフトはともかく、エアチェックしたソフトは市場に出回らないし、演奏会の録音もそうなので、
古いフォーマットを新しいフォーマットにトランスファーするのが私の今のオーディオライフみたいになっています。
30年近く前のDATデッキ8台も持っていて全て正常動作してるのかな
テープパスやローディングに狂いが出たり経年劣化で破損する部品も多いかと思うがどんな感じ?
>>595 ポータブルのTCD-D5は死んだ状態。D7は怪しい。
ヤフオクで整備済みの据え置きのDTC-A8、DTC-790は動く。
店で新品購入したDTC-790はCAUTIONの表示は出るが、何回か電源を入れ直しすると何とか使える状態。
DTC-A8、DTC-790以後の製造品は以前のトラッキングの方法を改善しているので読めないテープが読めたりする。
パイオニアはD-05二台は動いている。
複数のDATを持っている理由はダビングするから。
SCMSキャンセラーを秋月から基盤を買って、ダビングしていたが、
パソコンでデジタルのまま取り込めるようになったから、短期間の使用で終わった。
VICTORのXD-Z505を好んで使ったことがあるけれど、走行系のプラスチック部品が破損し、替えの部品がないので他人にあげた。
そう言えば、会社の騒音測定用に買ったTCD-D10PROが未使用のままあったので家に置いてある。
使い方が分からないが、騒音測定用の8CHのDATもある。使い道がないので困っている。
>>589 多分ね、デジタルで音楽を楽しむことの限界が広く伝わるはずだから、アナログ復活になるんじゃ無いかと思う。
デジタルだとたとえハイレゾでも、上手く調整されたアナログには適わない。
>>595 ポータブルのTCD-D5は死んだ状態。D7は怪しい。
ヤフオクで整備済みの据え置きのDTC-A8、DTC-790は動く。
店で新品購入したDTC-790はCAUTIONの表示は出るが、何回か電源を入れ直しすると何とか使える状態。
DTC-A8、DTC-790以後の製造品は以前のトラッキングの方法を改善しているので読めないテープが読めたりする。
パイオニアはD-05二台は動いている。
複数のDATを持っている理由はダビングするから。
SCMSキャンセラーを秋月から基盤を買って、ダビングしていたが、
パソコンでデジタルのまま取り込めるようになったから、短期間の使用で終わった。
VICTORのXD-Z505を好んで使ったことがあるけれど、走行系のプラスチック部品が破損し、替えの部品がないので他人にあげた。
そう言えば、会社の騒音測定用に買ったTCD-D10PROが未使用のままあったので家に置いてある。
使い方が分からないが、騒音測定用の8CHのDATもある。使い道がないので困っている。
>>597 録音するにも再生するにもアナログは物量と神経をすり減らす調整とメンテナンスが必要。
例えば、私が演奏会を収録する場合、KORG MR-2000Sで5.6MHz DSD録音する場合、持っていく機材はマイクロホンとマイクアンプですむ。
あとは自宅のPCでデーターを映して編集し、主催者などに高額ディスクで渡す。
' しかし、アナログ録音をしようと思ったら、新品の10号オープンリールテープ最低2本が必要。19cm2TRなら2本で収まるが、一本1万円。つまり2万円かかる。
デジタルは機材だけを持っていけばいいのだが、大きくて高価な記録媒体と大きくて重量のあるレコーダーを運ぶことになる。
このごろのホールの音響調整室にはオープンデッキは置いていなく、あったとしても数年以上は稼働していない。つまり自分で持っていくしかない。
ようするにアナログ録音も再生も贅沢だ。それ相応の職人芸も要する。
再生も同じ。ターンテーブル設置からカートリッジの取り付けアームの調整いろいろと調整するところがたくさんあり、
気にすればするほど調整と交換をするようになってしまう。それが楽しいと言えば楽しいけれど、若い者に勧められるかといえば自信がない。
このスレにもリンクを貼ったが、妥協を許さなかったらターンテーブルが4000万円ということになる。c/p比が悪いね。
>>597
つづき
' デジタルの最大の恩恵は二階堂歪みからの解放。
アナログレコーダーではテープとヘッドの摺動ノイズ、録音時に磁場が発生するけど、テープはそれに反発して振動したりするので、その動的なひずみが発生する。
アナログ録音とデジタル録音を1KHzなどのサイン波を再生してスペクトラムを観察すると、
1kHzの一本の棒のすそ野にわずかな末広がりのノイズが付きまとうが、アナログの場合その末広がりのレベルと幅が非常に大きい。
これがデジタルのほうが透明感がすぐれているゆえんだが、アナログの移行期ではそれがスカスカと感じられたかもしれない。
透明感に優れるということは様々な楽器で演奏するオーケストラのfffも定位や和音の見通しなどが混濁することなく聞こえる。
アナログ録音だと録音レベルが大きいと歪みが増えてくるからなかなか難しい。
ほとんどのレコードのマスターはアナログ磁気録音だから、テープ録音を集中的に書いたけれど、
レコード自体も根本的な問題が存在するから、どちらがいいとは言えない。
アナログ最高!という次元の高見まで達するのは、あなたが前提で書いてある「調整すれば」ということです。面倒の果てに喜びがある。
KORG MR-2000Sでレコードを取り込んでみようという意図は、イコライザーをかけずに、フラットでDSDで録音し、
パソコンにAUDIO GATEというKORGのソフトをインストールしているので、その機能の一つにRIAAのデジタルイコライザーがあるので、これを経由して聞こうと思っている。
高域に従ってレベルを下げるので量子化歪みも軽減できる副次的なメリットも生じる。
今のところ、マイクプリとフォノの最適負荷インピーダンスが合っていないので、ラジオみたいな音質になっている。
別のカートリッジに交換か、やっぱりそれなりのイコライザーが付いているプリアンプを経由したほうが良いのか思案している。
私はオーディオマニアの中では生録派です。プロの録音エンジニアではない。 そんな爺さんには普通は負けるんでないかい?
でもググったら返金させた話があるな「返すから、もう2度と来るな。」と言われてそれきり行かなかったとか
特別にクリーニングした特別に音の良いレコードとかじゃなくてただ音が良く聴こえる特別な装置だったってだけの話
手早く言えば詐欺話ってオチ
おみゃーらのレコードは、クリーニングしてもムダだぎゃ。
これを聞いたら、そのレコードじきにいらんようになるよ。
おみゃーらが持っているレコードは全部パ~だぎゃ。
と、締めくくりたいのであったw。
>>599 そうは言っても、やっぱり音楽を清々しい気持ちで聞きたければ、アナログでしょ!ww
〇ニコレ(fl)シュタイン(Hp)リヒター/ミュンヘン・バッハo.のモーツァルト:フルートとハープのための協奏曲
〇フェラス(vn)シルヴェストリ/フィルハーモニアo.メンデルスゾーン:vn協奏曲他
以上の2つのLPを洗浄したものをカセットに落としてカーステで聞いてみた。
洗浄効果によって、勿論両曲ともノイズは殆どゼロか、気にならないレベル。
車は2種。
トヨタカローラの純正のカセットプレーヤーと、ハイエースに設置したKENWOODのカーステ。
どう言うわけか、カローラの純正のカセットプレーヤーだとメンデルスゾーンの音がおかしい。
KENWOODだと両曲とも、しっくりくるサウンドだ。
CDなどと違って、「このサウンド最高!」と思えるレベルなんだが、なぜトヨタだと変な音になるのか?
どちらでもよい音が聞けるようにするにはどうすれば良いのか?
使用したカセットデッキはTASCAMだが、パイオニアのT-D7を入手したので、これで録音してみようと思う。
>>609 トヨタの方がアジマスずれ?
カーステレオにカセットとは珍しい。
わたしは車で聞く場合、SDカードにハイレゾデーターを移して、ハンディ―レコーダーで再生している。
もちろんカーナビのAUXミニジャックにつないで聞いている。
カセットだとメディアがないしね。このごろヤフオク!を見ているとあほらしいほど高騰しているよね。
昔はマクセルのローコストハイポジUDⅡの磁性紛改良に苦労したし、
工藤静香の宣伝で私の開発改良した磁性紛を使ったカセットがよく売れてうれしかったよ。
でも今はテープ用磁性紛の工場はない。
>>610 カセットテープ製造技術者ですか?
カセットは良いですよw
CDだと、特性がバラついていて、しかもPCで調整しても出てこない音がある。
最近、以前編集したアンセルメ/スイスロマンドのフォーレ/レクイエムや「ペレアスとメリザンド」をPCオーディオで聞いてみて、なかなか良いと思ってましたが、
しばらく聞き進むと、音の粒子の粗さが気になって。
音がブツブツになっているのがわかるんです。
デジタルサウンドは未だ未完成だとしか言えませんね。
その点、カセットだと音の粒子化は無く、ちゃんとサウンドになっているんですね。
レコード洗浄して、それをカセットに入れて楽しもうと思っています。
CDだと繰り返し聞きたくなることはありませんが、カセットだと、源音を上手く調整すればよい音で入ります。
場合によってはLPよりもよい音で入ります。
もちろん繰り返し聞きたくなります。
>>611 カセットだけじゃなく、塗布型の磁気記録媒体の磁性紛全般です。
会社としてはメタルやバリウムフェライトも手掛けていましたが、
おもにγ酸化鉄、コバルト被着型酸化鉄、いわゆるスーパーアビリンやエピタキシャル磁性体の方をやっていましたね。
そのような職種だったので各テープメーカーの技術力は知っています。
その中で「音の粒子の粗さが気になって」という事なのですが、音の粒子が何を指しているのか不明ですし、
PCで聞いたということですが、フォーマットは何でしょうか?サンプリング周波数とビット数は?
私もCDの音に不満だったのですぐに今でいうハイレゾ録音を25年前からやっていました。
さすがにハイレゾの領域、特にサンプリング周波数を96kHzにしたときは感動もので、
ピアノのアタック音の再現、定位と雰囲気の再現、高音域のバイオリンの響き、金管楽器、金属打楽器の再現はうっとりするものでしたし、
192kHzではアナログに追いついたと思いました。5.6MHz、DSDなどで収録すると、
アナログはアナログというエフェクトかもしれないと思うようになりました。
ただし、演奏会場で聞いていない人にこれらのハイレゾを聞いてもらうとひょうしぬけするのですよねえ。
自然な音質だろうから。こりゃ凄いハイファイだという音質ではないのですよ。
TDKのAEの磁性紛の大きさはSAの磁性紛の大きさに比べると約3倍。だいたい3μmぐらい。SAは1ミクロンぐらいです。
磁性紛の粒子が小さければヒスノイズは小さくなりますが、限界があります。
このヒスノイズがクセモノで、微小な楽器の音色が消されてしまうのですね。
大きな和太鼓の中に金箔をはりますが、貼る前後の音色は耳で違いが分かったのでしたが、オープンテープで収録した音を聞いたら区別がつかない。
周りの数人の一致した結論はヒスノイズでマスキングされてしまった。ガッカリしたことがありました。
カセットは私の昔の大切なオーディオアイテムでしたが、今持っている録音機器がありますから、わざわざカセットに録音しようとはおもいませんね。
好みが大きいかもしれませんが、私のつたない経験を述べました。何かの改善に役立てください。
一晩明けて粒子が荒いという感じ方でこのことを指しているのじゃないかと思いました。
量子化歪や量子化ノイズじゃないかと思います。
ならば、ハイレゾでのフォーマットトランスファーをおすすめいたします。
カセットは耐久性がありませんからね。
>>576-578 もう一つのワッチョイスレは、ボンドパックが最高だと言い張るキチガイが立てた
自分で立てたワッチョイスレで、自分の自作自演がバレるというアホな結末になったw
で、スレを久しぶりに覗いたんだが、あのキチガイはまだいるのかい?
>>614 IDを見たらそうじゃないことがわかるだろうに。
認知のしかたがわからいのか?
ボンドパックは有効であるのに、あんたの方が執拗にまとわりつくアラシで基地外だろ。
やっぱりまだいたのかw
執拗に粘着してたキチガイだから当然か
まぁみなさんこのキチガイに騙されないようにね
>>617 ある意味ではキチガイだと言える。オーディオマニアだもんな。
私は自分でやった本当の結果しか書かない。
あんたは真実を虚言と吹聴し、執拗に付きまとうストーカーだ。
自分が過去にボンドパックで失敗しているから、他人も失敗するだろうという推測を、
全てに当てはめようとする。
しかし、多くの人は成功しているし、結構ブログや動画投稿が多い。
失敗するのなら、成功した例よりも多数のブログやSNSや動画などで警告を出しているはずだがね。
あまり執拗にキチガイだというと、統失の疑いがあると思われるよ。
ナガオカのクリーニングクロスがよい
自作クリーニング液を噴射してテクニカの湿式クリーナーで広げて、シルコットであらかた拭き取って、ナガオカクロスで仕上げる。
これでチリノイズやカビ汚れは退治できた。
レーベルカバーして水洗い
ナガオカクロスで拭き上げで結構汚れは取れるね
ハンルやクラウディオは使ってみたいけどなぁ・・・
>>617 オレは普通じゃ無いんだよww
わからんかったのか?
オレは相当凝り性で、拘りまくったのでレコードのクリーニングで上手く行く方法を見つけ出したわけだww
VPIのセールスマンは、ボーッとしてるからVPIの弱点がわからんだけでw
オマエは早くワッチョイスレ立てて、そこへ逃げ込めよww
Apple says a ‘small portion’ of iPhones recorded interactions with Siri even if you opted out
https://www.theverge.com/2022/2/8/22924225/apple-ios-15-bug-recorded-interactions-siri 体力はいるが、お手軽糊パック作成方法。
用意するモノ
目盛がついた蓋つきの1ℓ容器、またはボトル。
事務用のポリビニルアルコール系糊(茶色、メーカー問わず)
ポリビニルアルコール系洗濯糊。
無水エタノールまたは無水イソプロピルアルコール。
糊を300㎖、ポリビニルアルコール系洗濯糊を400㎖を容器に入れる。
最初に少量のアルコールを入れて、蓋をし、1分間以上シェイク。
再び少量のアルコールを入れて1分間以上シェイク。
これを繰り返して、アルコールは全部で300㎖入れる。
シェイクする理由はアルコールとポリビニルアルコールは溶解しにくいのでゲル状になる。
よく混ぜれば、溶解するので、何回もシェイクする。
全部アルコールを入れた後でも、途中に休憩を入れながら煩雑に5回以上シェイク。
一晩放置すると、気泡が無くなり、透明になる。
その後、休憩を入れながら数回シェイク。
これでだいたい溶解している。確認方法は、別容器に移すとき、葛湯みたいなものが出てきたら溶解しきっていない。
名バーテンダーになれる。
増粘剤は入れていないので、粘度は低めですが、目的は達成できる。
撹拌機は非常に高価なので、買うのが勿体ないと思う方は、この方法でどうぞ。
体力はいります。
1面25ml使うとしたら40面、レコード20枚くらい使用できる容量。
私は、大量のレコードを抱えているので、撹拌機を購入し、1回に付き6.5ℓ作っています。
New SysJoker Espionage Malware Targeting Windows, macOS, and Linux Users
https://thehackernews.com/2022/01/new-sysjoker-espionage-malware.html >>627 売れてますねww
非常によい!
デンターシステマを振動させればさらによい。
クリーニングしたLPをカセットテープに落としてカーステで聞いてるけど、60分テープと90分テープでは特性が違うみたいだ。
90分テープの方は、かなり劣っているようで、3kHzあたりでやけに歪みが出る。
使用しているのはアマゾンで入手したマクセルUR90M。
一応(音楽・講習・語学学習に)と書いてあるけど、これでは美しいサウンドで音楽は楽しみがたい。
UR60Mの方はそんなに劣っているようには聞こえなかったが。
これから調査をしてみるよ。
>>630 C90になると磁性層の厚みも薄くしているからです。Wikiの記述は間違い。
昔はきっちりと、その辺のことがカタログに書いていましたがね。
磁性層が薄くなるとMOLが減少します。
各テープメーカーと付き合いのあった磁性粉メーカーに勤めていますから信用してください。
昨日3枚のLPの音質を確認!
〇東芝EAC-40102 プーランク「牝鹿」
〇キングSLL-1010 ~ミシェル・エルマン愛奏曲集~
〇グラモフォンMGW-5150 リヒテル、ピアノ・リサイタル第2集 バッハ:平均律
いずれもクリーニングをせずに試聴。
エルマンはほぼノイズゼロだが、プーランクもリヒテルもプチノイズのためにクリーニングの必要がある。
どの盤も、そのまま聴くと少々魅力の無い音質だが、プーランクが、思っていた以上に音質にクセがある。
ガサガサしているような音で、「こんな感じだったのか」と少し驚いた。
EQにて調整すると、生のオケらしい音がでるようになった。
このシリーズ、「フランスのエスプリシリーズ」と銘打って居たのだから、これくらいの音は出しておけよなと思った。
エルマン盤は、1958年録音ながら、情報量が多く、EQで調整後、まるで目の前で演奏しているようなサウンドを得ることが出来た。
VANGUARDの録音はかなり良いことを確認した!
リヒテルの平均律は、演奏会の実況録音で、これを購入したときは音に精彩がなくてガッカリしたものだが、昨日EQで調整すると、かなりの情報量が入っていることがわかった。
データには1962年11月フィレンツェでの演奏会録音とある。
EQで調整すると、リヒテルの平均律が、まるで眼前で弾いているかのような音に変貌し、会場の聴衆から発せられる咳などのノイズもそれらしいリアルさが復活する。
これで聞くと、リヒテルのピアノ表現の普遍性の高さがバッハの平均律を深い感銘を与える名曲として聞き手に提示してくるのである。
リヒテルは小手先の表現を弄するのではないけれど、確かなテクニックと哲学的とも言えるような解釈によって、バッハの平均律のあるべき姿を聞かせてくれるのである。
かつて1970年代に録音されたリヒテルの平均律のSACDを購入して、感銘を受けたのだが、どうやらリヒテルの平均律の解釈はこの1962年11月のアナログ盤と変わっていないようである。
記憶による判断になるが、音質で言えば、EQで調整されたこのアナログ盤に軍配が上がる。
なぜなら、アナログ盤の方がリヒテルらしい威厳のある重々しいピアノの音色をリアルに再現しているからである。
これも、カセットテープに入れて配布する対象としたい。
レコードのクリーニングを行って、カセットテープに記録。
この作業がかなり上手く行きそうである。
とある店舗にカセットテープを提示して「BGMに」と進めると、前向きな返答を得た。
「デジタルと違って、まるで目の前で演奏しているのを聞いているよう」との言葉を頂戴した。
上手く行けば、アナログサウンド復活となる。
Apple Storeの従業員、Appleからの監視を恐れてAndroidスマホ使用
https://iphone-mania.jp/news-439670/ >>634 店舗のBGMとして使うとなるとJASRACに金払わんといけないから非現実的
>>638 著作権についてもっと勉強しよう。
レコードの著作権はいつ切れるのかな?
>>639 お前が著作権とJASRACをもっと勉強しろ
>>639 録音後70年間
70年前に録音したレコードを聞いてるの?
スレチだけど2018年までは50年でこの時点で一度失効していたものは復活しないみたいだよ
意訳、もっとカネ出せてめーら
そして強欲すぎて衰退、文化消滅
>>641 だいぶ改正されていたね。
原盤を用いてのリマスタリングもむずかしいな。
https://www.kottolaw.com/column/000609.html しかし、ここでは、音源(著作隣接権)の保護期間が満了したとはいえ、
「ラヴ・ミー・ドゥ」の曲の著作権はまだ存続しているため、
著作権者に無断で利用するという訳には行きません。
現在日本音楽著作権協会(JASRAC)により管理されているため、
JASRACに所定の手続で利用を申請し、規定の利用料を支払うこと
結局は、金を払えば使えるって書いてるね。
>>646 ロマン派以前の楽曲をつかえばすむことです。
目安として1948年以前に亡くなった人の楽曲と、
原盤権が消失しているレコード、1968年以前に録音された原盤ならok?
AirTagのプライバシー保護機能に抜け穴、新対策の効果も限定的と研究者が指摘
https://iphone-mania.jp/news-439645/ >>639 どうやら勉強したようだな
ジャズ喫茶で聞いたんだよ
>>649 わたしは、特許関係の仕事をしていたんだよ。
特許関係は慣れているが、著作関係は初期に発明協会で勉強したきりでね。
ジャズ喫茶の店主は自分が関係していることだけ知っているのでしょうよ。
自分が知ったかで昔の知識ひけらかしてマウント取ったつもりでいたのに何言ってんだこのバカw
>>651 君が最初にマウントとっただろうにwwww。
笑っちゃったよ。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c1039593282 ↑
これって、安すぎだけど危ないかな?
調べるとこの出品者の他の商品価格が、全部3千円ぐらいなのだが
最初から適当に価格設定してるのかな?
レコード回転させるモーター機構のないものなら、その値段でも不思議ではない
AirTagのプライバシー保護機能に抜け穴、新対策の効果も限定的と研究者が指摘
https://iphone-mania.jp/news-439645/ >>658 https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c1039593282 新規であることに加えて、この出品者の他の出品価格が
全部、3000円台って余りにも不自然すぎ。
かなり怪しい出品者のように思えるのは私だけだろうか?
レコード洗浄機買おうと思ってたから、安いのには歓迎なのだが…
もうね、レコードクリーニングって、普通の汚れなら超音波洗浄+デンターシステマ(振動あり)で、ほぼノイズゼロになるから、傷さえ無ければ
埃だらけとか、カビつきまくりでも大丈夫だと思う。
後はビニ焼け盤のクリーニングがどこまで可能かに挑戦したいが、昨年秋に腱鞘炎になったので、しばらくクリーニングのために指を使った過酷な作業は控えようと思う。
それにしても、アナログLPには情報量の多い盤が結構あるね。
アナログLPに耳が慣れると、TVの音楽番組は聞いていられないよ。
今日もEテレのクラシック音楽館を、30cmウーファーの大型SP付きで聴くと、音がスカスカなんだ。
>>662 そのハイレゾってのもオレの視野には無い!
>>659 安全なのは、それ相応の金をかけて新品購入することですね。
>>647 >1968年以前に録音された原盤ならok?
おそらく。
デジタル音声ならネット上で無料でダウンロードできるようになっている。
最近、超音波洗浄(デンターシステマなし)を、もう一度超音波洗浄(デンターシステマあり)でやり直した。
システマ無しだと基本音の欠落にガッカリしたけど、システマありで洗浄し直すと、若干だが基本音を感じ取りやすくなった。
たぶんだけど、システマ無しの超音波洗浄だと、超音波で破壊されたカビ成分(この盤には盛大にカビが入っていた)が再付着して音質を劣化させているのだろうと理解した。
盤はフィリップス録音のモーツァルト:フルートとハープのための協奏曲・・コリン・デイヴィス指揮ロンドン響
それでもテルデック録音のニコレ(fl)カール・リヒター/ミュンヘンバッハo.盤の情報量には適わなかった。
ニコレ盤は1960年頃録音だから、両盤ともに録音時期は大して変わらないと思う。
それでもこれだけの情報量の差には正直驚いた。
>>671 と思ったら、後継機が控えてるとか
情報元はベーレンプラッテのblog
>>672 さんきゅー、日本だとDiscoveryONEの方が本命な気がするけど
高くなりすぎるから改良版の日本向けも出すってことかなあ
>>675 こないだパックを使ったよ。
クリスティアン・フェラスのヴァイオリン小曲集。
超音波洗浄してみたけど、カビが粒子状に残留していてノイズになった。
パックの方が除去しやすいだろうと考えた。
まだ剥がしてないけど、剥がすとノイズがかなり小さくなるはず。
The Russian Government Official Website
http://government.ru/en/ タバコのヤニやら著しく汚い中古レコード入手した時のオレ流メンテナンスは
40度の中性洗剤混ぜた水で超音波洗浄+ブラシ洗い、その後ざっと水洗してから
ニッティーグリッティのバキュームクリーナーでバキュームクリーナー用洗浄液使って吸引
これで見違えるように綺麗になりノイズもグッと減る
中性洗剤はダメとかバキュームクリーナー専用液はアルコール入ってるからダメとか
色々な意見もあるだろうけど通常のクリーニングで汚れが取れないんでは仕方ないからね
それに単騎的にも長期的にも盤の劣化を感じたことは無いね
どうしようもなく汚いレコードに関してはそれでいいと思う
うんうん、なんでアルコールを使わないのでしょうね。
中性洗剤も全然影響ないのに。
まだバキュームマシンを持っていない頃、買ったレコードは中性洗剤と水道水で水洗いしていた。
そのレコードを久しぶりに聴こうと思ってターンテーブルに乗せてベルベット・クリーナーを使ったら白い粉が付着。
これは残ったカルキだと判断しさっそくバキューム・マシンにてクリーニング。
アルコールとシステマで溝を丹念にクリーニングしてから最後は精製水使ってバキューム。
綺麗になった盤を両面試聴し終わってから針を見たらあっと驚くゴミの大量付着。
水洗いとバキュームやってもまだ足らんのかと絶望。
まだまだクリーニング道は極められていないなあ。
>>681 私のバキュームクリーナー用リキッドはアルコール入りなんです。
あと皆さん静電気対策どうしてますか?トレースするだけでも静電気帯びますよね
昔はTEACのイオンクリスタという空気清浄機をレコードプレーヤー脇に置いておくと
静電気の発生が割合抑えられたんだけど、あれは発生するイオンで電荷が相殺されてたのかな
導電ブラシで擦っても静電気は発生してダストが取りきれないから
最近はゼロスタットでカチカチやってる
静電気防止剤の入ったクリーニング液を使って
紙のターンテーブルシートを敷いているせいか
静電気で悩んでないな
TRUSCOの静電除去シート円形に切って敷いたらほぼ解消
おすすめ
溝の奥底ミクロの世界まで洗浄するには
これが一番だしこれしかありません
https://imgur.com/ARbg1dd https://imgur.com/xN5Ycp7 ボンドパックやシステマブラシも楽しいので余技としてはアリです
なんのなんの
高周波、回転、タイマーから温水装置内蔵まで
あとは手作業での水切り&乾燥なのだから
万能は言い過ぎにしても
これ以上はないという結論です
ひどい汚れのレコードにはバキュームクリーナーと超音波の両方が必要だな
あと否定的な奴も多いがスチームクリーナーも結構有効
グループ内にタール状に付着してしまった汚れは効果的に取れる
スチームクリーナーは1箇所に留めていたら熱で問題が生じる可能性あるけど
2センチくらいの距離で細かく振るように動かして使えば特に問題起きない
俺は汚れ酷くて超音波とバキュームやってもダメな盤には使ってる
>>694 ヤフオクでレコードクリーニングの出品してる奴もいるから真似してみればいいじゃん
少し頑張れば元取れるかもよ
>697
でも高いね
あれだったら、手作り品じゃ無くても
買えそうだよな
送料云々は忘れたが成功報酬で1枚1000円くらいだったな
クリーニング効果がなかったら500円とかそんな説明文を読んだ記憶がある
ちょこっと探してみたけど見つからなかったからメルカリとヤフオクを隈なく探してみ
>>606 無理だなww
今、クリーニングしたLPをカセットテープに記録して彼方此方に配布し始めている。
アナログの音に耳が慣れると、CDなどのデジタルは我慢できなくなる。
ヤフオクで入手のレコードをため込むレコード棚を自作した。
費用はおよそ1万円だが、1000枚以上のLPを入庫できる。
これをあと一つ二つ作ろうと考えている。
以前報告したクリスティアン・フェラスのヴァイオリン小曲集。
パックを剥がしてみた。
当然のように表面に付着していたカビの粒々は除去され、ノイズは小さくなったが、それでも小さめのピチパチノイズが残留。
おそらくカビの中の油成分が残留し、それがノイズにつながっている。
アルコールとシステマで除去すれば、さらにノイズは小さくなり、鑑賞の邪魔にならないレベルまでに成るはず。
今はLP貯蔵用の棚を政策しているので、その作業が終わってから取りかかるつもり。
ミューラー氏のポリビニルアルコールパック、
自分では糊パックと呼んでいる基本特許であるが、
この特許の実施例にトリエチレングリコールという可塑剤が添加してある。
これは、パック膜の柔軟性を持たせるためだが、帯電防止剤となる。
ドライウェル中に含有しているエチレングリコールよりも沸点が高い液体であり、より潤滑効果も期待できる。
しかし、特許中では4重量部と量が多いと思うので、量を少なめに調整する予定。
レコパックのオリジナルは、塗布後に長期間(約40年)置いておくと、油状の膜がにじみ出て、剥離する。
たぶん、トリエチレングリコールと思われるノニオン系界面活性剤だと思う。
塗膜も盤面もちょっとべたべたする。すぐに剥がした場合はべたべたしない。
ずいぶんと剥がしまくったが、静電気発生が多いので、困っていたが、
トリエチレングリコールを入れることで、帯電防止になり、
レコードの盤面とパックの塗膜の接触面積は一定であるから、
常時適量で均一な帯電防止剤の塗布となりえる。
トリエチレングリコールは500mlで約1800円。
試薬を扱う店で購入した。
水に可溶であるので、木工ボンドでも有効か?
みなさんこれポチろうぢゃないかなくなる前に
アマ検
>LP丸型内袋100枚 厚口0.028mm 国内製造 静電防止素材入り
うちのデンターシステマ
ずっと前にうpしたあと
いろいろ試して仕様が決まったのでレポをば
仕様というのはLP片面20分として
外周スタートから最内周までカートと同じタイミングで達するように
圧を探っていたのです
https://imgur.com/za9rdmP https://imgur.com/G8KbnRI 実測20.6gあってこれでいいのかという気もしますが
モーターの強トルクを信じて使ってます
ちなプレイヤーはこれ
https://audio-heritage.jp/YAMAHA/player/yp-d10.html >モーターには1.2kg・cmの大きなトルク ← 意味よくわかってませんけど
最外周のエッジに網戸の網押さえゴムを回してディスクをわずかに浮かせ
センターにロック式のスタビライザ
これでバキューム式以上の効果をねらってます
21年連続ナンバーワンはオデマニが支えてること
ライオンも気づくまいて
百均のが果たして溝の底まで届くのかどうか
カートリッジの針先を見るルーペ10x15xくらいので覗いてみたらどう?
ルーペで見てないけど毛先は0.02mmとか書いてあったな<百均のやつ
中性洗剤+50度のお湯でマイクロファイバークロスを使ってゴシゴシ洗浄。そのあと乾いたマイクロファイバークロスで数回吹き上げてドライヤーで乾燥。
これでプチ音はほとんど消える。
>>720 セリアで4本入り百円だったよ
ダイソーだと3本入りだった
何百枚か洗ったけど洗浄はシステマのブラシからさらしに、水の拭き取りはキッチンペーパーになった。マイクロファイバーは仕上げだけだな。
システマって意味あんのか?
最初にアルカリ電解水(水のゲキ落ちくん)を噴きかけてしばらく放置してるけど、正直それが有効かどうかはわからない。
それよりも、流しのシャワー使ってお湯で洗いまくるのか洗浄効果が高いと思う。
勿論レコードの下にはターンテーブルマットを敷いてる。
溝に入れるのはブラシだけでしょ jk
ほかのはみんな表面磨くだけね
理屈じゃそうだがブラシが全ての溝に入る確率ってどんなもんよ
10分も20分もこするならブラシで良いと思うが
数分で洗うならブラシの方が汚れが落ちないよ
実際洗えば分かる
これのことか
>>692 溝の奥底ミクロの世界まで洗浄するには
これが一番だしこれしかありません
https://imgur.com/ARbg1dd https://imgur.com/xN5Ycp7 ボンドパックやシステマブラシも楽しいので余技としてはアリです
マイクロファイバークロスの繊維は8ミクロン
充分レコードの溝に入る細さ
布だとある程度面圧がかかるから水圧も関係するのかな、などと思ったりもする
マイクロファイバークロスは水分を取る仕上げにはいいんだけど
汚れ落しには取った汚れで溝をこすることになるんだよな
洗浄力のある洗剤を探すのが先
まさかスーパーで売ってる台所用洗剤使ってねえよな?
擦るのはあくまでも強力に固着した汚れがあるときのみ有効
その汚れが溝の中だけに収まっていて布で落ちきれないのはよっぽどだな。百枚に1枚あるかどうか。程度の悪い輸入盤洗ってても3百枚に1枚あったかな程度。
その1枚のために残りの299枚の洗浄の手間増やすのは面倒だしそこまで程度が悪いレコードなら捨てるのに躊躇ねえわ。仕事で請け負ってりゃそうはいかんのだろうが。
実際に洗う前に洗剤にどれだけの時間つけておいたのかの方がよほど汚れ落ちに影響する。まさかドライの状態からいきなり洗剤吹き付けて洗ってねえよな?まさかな。
ブラシじゃないが、浴室用のナノバブルシャワーヘッドとか洗浄にうまく使えないかなと思った事はあるな
熱めのお湯と界面活性剤で汚れを浮かせておいて、マイクロファインクロスで溝の中の汚れををしっかりと拭き取る方法。
超音波洗浄機使ってる人って、水は何を使ってるの?
水道水?
>>722 湯沸かし器の設定を60度に上げてやってみたら、こっちの方がさらに良い感じだった。
勿論レコードには何の影響も与えない。
ナノバブル、ミラブル、、
通常のシャワー使いでもカルキ類の目詰まりがひどくて使い物になりません
>>741 >湯沸かし器の設定
これはおおざっぱでしょ
まあおおざっぱでかまわないんだけど
これ正確でおもしろいよ~
アマ検
>R.Moon 簡単便利 小型デジタル 温度計 -50℃~+99.9℃対応 [並行輸入品]
安いからいくつも買ってお風呂、流し、洗面台、クリちゃん散歩のリードケース
いろいろ楽しんでます
給湯で60度設定ならレコード歪むわ
40度までにしておけ
>>743 いまだにカルキとか言ってる無知がいるのか
カルキは無色透明dw揮発性のある物だから詰まる事なんて絶対にない
白く詰まるのはミネラル成分のスケールという物だ
マイクロバブルやファインバブルを使うのにどうしてシャワーヘッドに拘るのかw
シャワーヘッドの穴を通過するときマイクロバブルやファインバブルの気泡は少なくなっているのも知らないようだしなw
マイクロバブルやファインバブル生成後に、
シャワーヘッドを通した水
シャワーヘッドを通さない水
グラスコップに貯めて比較してみな
濁ってる方がマイクロバブルやファインバブルが多い
>>747 65度までは大丈夫ってどっかのサイトに上がってたよ。
65度とか50度とか温度計がない場合わからないから、
お風呂に入る温度でいいのじゃないの?
これならやけどもしないし。
>>758 ゴメン、85度の間違いだった。
ツベで85度温湯洗浄で検索したら出てくると思うよ。
少なくても給湯器60度でガンガン洗いまくってもどうもない。
>>761 それ、ベレー帽をかぶっている爺さんの動画で所?
>>762 そう。
ただ、自分は台所の流しで中性洗剤とお湯を使ってゴシゴシするだけだけどね。
安いマイクロファイバークロス使って洗浄と拭き上げ、ドライヤーで仕上げ。
大袈裟な装置使ってないけど見た目にもピカピカになる。ノイズが減るだけじゃなく音も締まる感じ。
針通すのすらためらう汚いレコード買ってきた
クリーニングのテストにはもってこいだ
レコードには熱いお湯を直接あてるけど、洗うマイクロファイバークロスはそこそこの温度のお湯で中性洗剤つけて擦るから全然大丈夫。
流しのシャワーだから温度調整は簡単。
最高温度が60度ってことだよ。
レコードはターンテーブルマットにのせて平らなところで洗ってる。
>>765 お湯と洗剤入れて、10分くらいはつけ置きだね。
いろいろ試してみてまた報告よろ。
この方法だとレーベルは少し脱色あるかもだけど、今まで気になったことはないよ。勿論剥がれたこともない。
漬け置きしてたら温度下がるし熱いほど汚れが落ちる根拠もないような
油汚れ落としたければアルコール吹いた方が早くね?
これはひどいと思う板は、レーベルカバーをして、まず濃度90%のアルコール噴霧。3分置いて布で軽くこすって洗剤池に沈める。15分後に取り出して軽く洗剤を吹いて布でこすって再度洗剤池へ。後は時間は好きなだけ。長く漬けるほど落ちるが、時間もかかるので短ければ数分。取り出したら水道水(ぬるま湯)でよく流してキッチンタオルで表裏の水滴をふき取った後、精製水を噴霧してマイクロファイバークロスで拭き取り。これでだめなら諦める。
時間の節約の為に2枚同時に処理することが多い。
レーベルカバーはしてない。
基本的に音が良くなればそれでいいから。
お湯でジャバジャバにしても見た目が変わったことはないよ。さすがにレーベル擦ることはしないけど。
水の激落ちくん使う時だけはレーベルより少し大きい茶碗被せてるw
国内版中心なのかな
ソ連のレーベルとか水弾かないんで怖いわw
>>770 汚れ強いのには↑で書いたように水の激落ちくんを噴霧して10分くらい置いてる。
レーベルカバー使わないのは、熱い時に力加えると歪むかもしれないから。
ターンテーブルマットにのせて平にして洗ってる。
そこまでして温度上げないと落ちないか?
ぬるま湯よくね?
タバコヤニか油煙系なのかレコードクリーナーの残渣なのか
その手の粘着性の汚れの酷いレコードには俺はスチームクリーナーをぶっかける
小型のスチームクリーナーのノズル直前は95度くらいあるが、数センチ離して吹きかければ
レコード表面の温度はすぐには上昇しないから大丈夫、うちは何枚もやってるけど全然問題なし
米ステレオファイル誌のマイケルフレールがお勧めしてたやり方
>>776 スチームか。今度使ってみるよ。
傷がないのにノイズが消えないところを重点的に。
溶解度というものは温度が高いと溶けやすくなる。
どんな物もそうです。
レコードスプレーの成分やタバコなどは油脂と同じなので、溶けやすくなります。
油をお湯で流すのか、アルコールで流すのか
どっちが落ちるという話だろ?アルコールじゃね?
>>777 特にルーペで見えるノイズ源になっている黒い固まりみたいなものは確実に取れる
コツは1、2センチの距離から音溝に沿って45度の角度で動かしながらスチーム噴霧する
小型のクリーナーなら長い時間一ヶ所に当て続けなければ全く問題は起きない
取れなくても軟化や浮き上がるからその後システマブラシで簡単に取れる
何回洗ったり吸引しても取れない細かい塵でパチパチするレコードにも特に有効
僕はアイリスオーヤマの小型のスチームクリーナー使ってる
最近は、比較的綺麗なLPばかりを聞いているので、レコードのクリーニングをする事が少なくなった。
やっぱりアナログ録音って良いですね。
デジタルのペラッペラな音とは全く世界が違う。
カセットテープに録音して彼方此方に配り始めているけど、もう少しすると本格始動するつもり。
今、オイストラフのヴァイオリンによるメンデルスゾーンのコンチェルトをカセットに入れているところ。
カセット配ってんの?w
さすがに再生機持ってる人も限られるんじゃ
>>692 です
寒いしケガしちゃったしでおこもり状態、時間ができたので
気になっていた何枚かを洗浄しました。
事前にパチパチノイズを確認しておいたのが
ほとんど消えてしまいヤッターマンです
大音量再生のため溝の底をさらうというかなぞるノイズが出てますが
かえって心地よく聞こえます
洗浄の仕上げについて
吸水に優れた今治タオルでぬぐっておいて
ツインバードT字型水切りワイパー吸引機
仕上げにドライヤー、、という手順です
残留物ウンヌン繊維がカンヌンの書き込みがときどきありますが
ナンセンスと言わざるをえません
キニスンナ、、です
最近、ラジカセがブームになっていて、ドラマ「逃亡医F」でも主人公の藤木が手術をするときにカセットテープを鳴らせる。
上手にカセットテープに音を入れれば、CDなどより遙かに良い音で聴ける。
カセットテープ6本に、音楽を入れた。
オイストラフのヴァイオリンによるメンデルスゾーンのコンチェルトをA面に、
リヒテルの平均律をB面に入れた。
オイストラフのはCBSソニーのレコード。
リヒテルの平均律は、グラモフォンの1962年実況盤。
音質調整すると、まるで目の前で弾いているみたいに聞こえる。
学生の頃MDが全盛でまだカセットウォークマン使っている奴がいて馬鹿にされてたけど、もしかするとそいつが一番音質とか音楽的に理解があったのかもしれん。
今日はチャイコフスキーの弦楽セレナードの音質をチェックした。
1966年録音のカラヤン/ベルリン・フィル盤。
この録音、CDのが相当酷い音質だったので、アナログはどうかと期待したが、アナログ盤もダメだった。
音質調整でかなりまともな音に近づいたが、CDはいくら調整しても、まともな音にならない。
この録音は、音質調整して再び世に問うべき録音だ。
元の音がかなり酷い。
これではカラヤン/ベルリン・フィルの演奏の何たるかが伝わって来ない。
【ドラマ】『妻、小学生になる。』視聴率6%に…低すぎる数字に落胆「もっと評価されて」 [爆笑ゴリラ★]
1爆笑ゴリラ ★2022/03/23(水) 10:52:30.68ID:CAP_USER9
//2chb.net/r/mnewsplus/1648000350/-100
335名無しさん@恐縮です2022/03/22(火) 10:43:10.12ID:jwG1O0gg0
堤真一「妻、小学生になる。」第9話6・4% 万理華の体に憑依していた貴恵が消えた
//news.yahoo.co.jp/articles/b678a0d7f060162fd7a530499165a3633feef0d7
スチームかけると茶色い水が流れ出てくる中古レコードがあるんだけど
どんな使い方してたんだろう?レコードが静電気帯びてタバコの煙を吸着するのかな?
津波とか河川の堤防決壊による水没品じゃないすか
泥水かぶっただけなら原状復帰はわりとかんたんです
そんなテレビ通販の販促みたいなレコード見たことねえわ
こんな汚いレコードも!
>>792 喫茶店で使ってたとかかな
タバコ吸う人が近くにいる環境でレコードかけてたとか
そういや下北沢かどっかに店内喫煙可(店主自体が店内で喫煙する)中古レコード店があったなw
なんらたフラッシュなんたらとか言う怪しいレコード洗浄液も売ってるクソみたいな店w
ちなみにその店のレコードは殆どが底抜けしててビニール袋にも入ってない状態で置いてたなw
電解水クリーニングブームの嚆矢になったお店だね
外袋には入ってるけどね
>>785 です
レコクリがあらためておもしろいので
パチパチのひどい米盤をかたっぱしからやってるとこ
でも米盤はダメだな
プレス時からノイズ入ってんじゃないの?これ
何十枚も実施しての実証的な経験では
もはや水切り吸引器ツインバードも不要かな
今治タオルで水分あらかた吸い取ってから
ドライヤー数分でオッケーですわ
ましてナントカ水とかファイバーなんとか等はムダムダ意味もなし
みなさんもっとお気軽に実践してえや
たとえばこれ
https://imgur.com/4OAGFzI 日本盤でフェイバリットなのを米盤でもめっけて即買いしたんですけど
まあノイズはしどいし歪みっぽくてガッカリ
これが見事によみがえっちゃいました
クリーニングの手段でほかに信頼できるのはボンドパックかな
あとのバキュームだのスチームだのは
やってて楽しいかもしんないけど
労多くして(コスト高くして)なんとやらだかんね
うっかりノセられてんなや
>>809 20年以上、様々な方法を試行錯誤してきたが
超音波ブラシとバキュームの組み合わせが
最も効果がある
ボンドパックは絶対にやってはダメ
棄てても良いような盤で試しにやってみれば解る
>>810 まーた、出できたw。ボンドパックはあなたが不器用なだけだろ。剥がし残しがあったなら、セロハンテープではがし残しを取るか、もう一度分厚く塗ればいいだけ。
一体全体何が不都合だったんだ?
そうそ
ただヘタクソなだけ
あと理屈もあんまわかってない
時間的にはボンドパックよりバキュームかな
まあ水を差さずつもりもなんいでそれぞれの方法で追求してもらえばいいんだけど
>>811 ボンドパックはとにかく時間がかかって効率が悪すぎるでしょ
まぁ時々、しかも数枚程度しかやらないのなら良いかもしれんけど
自分の場合、毎回、新たに手に入れた十数枚をそんな方法でやっていたら
肝腎の音楽を聴く時間が無くなる
人生で一番大切なのは「時間」だから
>>811 セロハンテープではがし残しを取るなんて論外だわ
どれだけ暇なんだ…
別に音楽聴くよりボンドパックしてるほうが楽しいとかいう人がいても問題はない
>>816 たしかにね。
ボンドパックを剥がすときのあの感触には快感がある。
けど、やっぱりアナログで音楽を聴く楽しみだよ!
そのためのレコードのクリーニングなんだから。
自分は約千枚の内、ほったらかしてた10枚強。スレ読み返してボンドパックかな?
一応、次の流れが出来上がっている感じ。
レコードのクリーニング → 雑音ゼロでカセットテープに入れる → カーステでアナログ音楽を楽しむ!
大分良い状況だと思う。
昨日はアンセルメ/スイス・ロマンドo.のボロディン:交響曲の音質をチェックした。
確か録音が1955年だったと思うが、LPジャケットに情報なし。
そのままの音質は相当クセが強くて、情報量が少なく感じる。
EQで音質調整すると、かなり良好な音質に変身!
情報量がかなり増えた印象を受けた。
この当時のデッカ録音はどれもかなりのクセの強い音質だが、記録されている音はかなりの広さの帯域を持っている。
何故こんなアンバランスな音質になったか原因は不明だが、バランスを整えればイケる音質になる!
CD化に伴ってかなりのアンセルメのLPを手放したが、それを取り戻している最中である。
>>815 暇じゃない。そんなに聞きたければ、他のレコードを聴きながらすればいい。一度に10枚以上処理している。扇風機で風を当てれば30分で片面が垂れなくなるので裏面を塗り約3~4時間で乾燥終了。
レコードの置台は、ガムテープの紙筒芯、これで芯+レコード+芯+・・・・+レコードという積み重ねで乾かしている。効率的。
セロテープではがし残し除去が論外、という根拠はないだろ。また感情だけで言っている。実際におこなって不都合は全くない。
レコードの溝奥の汚れを除去して
ノイズと歪みっぽがせっかくなくなったゆうのに
なにが哀しゅうてカセットなんぞに??
したことないしヤル気もないけど、ボンドパックでレコードの溝の固着してるジリパチも取れるの?浮いてる汚れしか取れなさそう
あとバキュームってクリーニング液吸い取るだけで汚れ落とすのはクリーニング液次第だよね。別にその液あれば水で流した方が盤に薬剤残らなくない?バキュームに何の意味があんの?
>>824 自然乾燥だと純水でも使わない限り、カルキとかカルシウム分とかが
固着するのでバキュームで強制的に吸い出す意味があるのよね
バキュームで吸い取っても残留物ゼロにはならんやろ
水道水で流した後、ふき取ってから精製水で仕上げ拭きするか、ブロワで水滴飛ばすわ。水垢が残ることはないけど
つか水道水の残留だと思ってるものの多くはクリーニング液の残留だけどな。時間かけて水洗いした盤で水滴跡残ることはまず無い
手間と時間がかからず安定した効果がある、これがマシンのメリット
>>826 ここでピュアスレお決まりの身もフタも無い捨て台詞を吐くならば
専用バキュームクリーナーも買えない貧乏人の僻み
なんだろうが
テメーのレコードなんだから
それぞれ好きにすればってだけ
手作りと機械による大量生産と同じ。熟練した手作業で
手間も時間もかければ機械以上の効果は得られるだろうけど
普通はそんな事やってられん
貧乏人の僻みってw
マイクロファインクロスで拭き取りすればバキュームより残留の水分は少ないだろうに。
>カルキとかカルシウム分
見た目盤面にはわずかに残って見えても
溝底溝壁には影響ないのでノイズ源にはなりません
純水だの精製水だのは必要ないのです
説明できないと金でマウント取るのが高卒の特徴
そもそもバキュームってどんだけ吸い込むの?
掃除機みたいな仕組みで水分ゼロまで吸えるもんなん?w
それともクリーニング液といいながらほとんど薬剤入ってないんか?
どう考えてもクリーナーと汚れが混ざった液体が盤に残るんだが。嫌すぎる

パックした後、はがしたパックをカミソリで薄く切って顕微鏡で見た断面。 赤く見えるのは、標本を固定する台の色。
顕微鏡倍率は40倍、さらにそれを画像で3倍拡大してあるから、最終倍率は120倍。
三角形に出っ張っているのが音溝、平らな部分は溝と溝の間である。
出っ張りの頂点が溝底である。大変きれいに尖っている。パック液が音溝の最深部まで充分に行き渡っている。アルコールと水になじみよいものは除去可能。
数度やればとれるが、数度やってもノイズが取り切れない場合はぬるま湯の中性洗剤で超音波洗浄、ゆすぎながらブラッシングでOK.
熱めのお湯使って中性洗剤でジャバジャバ洗う。
1面3回ずつ。それでマイクロファイバークロスで吹き上げて、ドライヤーで乾燥。
1枚20分もあれば終了。ノイズもほとんど無くなる。
逆に1日何枚中古レコード買ってんの?
>>834 >>825に書いてある通りです。先がないご老人でしょうか。失礼いたしました。
>>836 60度のお湯使って中性洗剤で洗えば、ほとんどはそれで大丈夫。それでもノイズ残ってる場合はスチームクリーナーだな。
そういう君は何使ってんの?
あ、もちろんスチームのあとはシステマ使ってる。
それでもプラス10分くらいかな。
>>835 未処理のがまだ20箱以上あるわ(+o+)
聴きたくもないレコード箱売りで買って、普通業者じゃなきやそんなのに手間かけたくないわな。
ところで、そんな沢山どうやってクリーニングしてるの?
業者だから企業秘密かw
むかし愛聴しながらノイズや歪みっぽさがなんとかなんないかなあー
と悩ましかったところへ
そんなものと無縁のCDが登場して完全にヤラレてから
そのままずうっと遠ざかっていたLPレコード
それらが超音波とドライヤーでいとも簡単に蘇る
それも本来の音質、、当時以上の音質で、、なんて素晴らしいわあ
>>844 知ってる曲聴いてもつまらないんだよね
同じレコード何回も何回も聴いて楽しいか?と思うけど
>>846 ん、自分自身がお金でマウントとりたい人だった?
まあ、いいけど。
で、どんなクリーニングしてるの。
最後にもう一回聞いとくね。そういうスレだから。
>>739 水道水に液体洗剤をほんの少し混ぜている。
>>847 1枚100円ぐらいだろw
それがマウントに聞こえるんだ?貧しいねえ
人にもの聞く態度じゃねえな
土下座したら教えてやるよ
>>814 >ボンドパックはとにかく時間がかかって効率が悪すぎるでしょ
場合によってはかなり有力。
表面に固着した粒子状の異物をある程度除去出来る。
>>845 でしょ?
LPだと、CDの音が空しく感じる。
それに、音質に相当クセのあるLPも、EQで調節すれば素晴らしいサウンドに。
もうデジタルサウンドにはおさらばしている。
クリーニングしてると
いい音を取り戻せるのは当然ですが
ついでのようにプレーヤーのカートリッジやアーム周りの点検メンテも進んで
システムの保守にもつながります
いろいろな方法で追求していけば
安くて安全で短時間でできるものになっていくんじゃないかな
潰し合いは不毛だと思うよ
実にそう思う。ボンドパックは危険と言い張る人が出てくるが、不毛である。
私も各方法を組み合わせている。だって、それぞれの長所が生かされるでしょ。
ボンド否定するのはやったことない人
またはよっぽどの不器用で
こんな単純な作業を失敗しちゃった人
ボンドパックなんて単にレコード盤の表面にボンド塗るだけだし、不器用な俺でも出来る。
ボンドパック失敗する人ってのは、フラフラで老眼で手指を満足に動かせないお爺ちゃんとか?(´・ω・`)
薄く塗ろうとすると必ず残る。これが原因じゃないかと思う。
木工ボンドの場合、粘度が高いので幾分か水で薄めて広がりしやすくし、厚めに塗る方がいい。
薄めた場合、音溝深くに浸透しやすくなり、都合がいい。
そういった点でアラビックヤマトがいいって誰か言ってたよね
若いときに比べて脂っぽくなくなって
本や新聞とかお札とか実に扱いづらくなったけど
逆にレコード盤を大胆に持てるようになったのはなんかうれしい
>>863 うーん、アラビックヤマトを使う理由はそれだけではないのですよ。
>>12 >>13に調べたとおり、塩化ビニルと酢酸ビニルの共重合体のレコード盤は油の性質に近い、に対し、
アラビックヤマトの主成分であるポリビニルアルコールは水酸基が数多くあるので水の性質を持ちます。
SP値が離れていますので、そのため水と油を混ぜても分離するように、溶ける事はないので剥離しやすいということです。
一方、木工ボンドは性質がレコード盤のSP値に近いので、剥離後に盤面に残りやすいということもあります。
こんなのはコケおどしです
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t1043586929 バキュームならツインバードがお手軽&確実だし
ぼくは超音波の温水浴
そこから上がったら今治タオルとドライヤー@1200w
で決着しましたけど
>>868 特に批判するようなことでもないわな
つかここは過剰反応で荒れるんでそうならないように言葉を選んでほしいもんだよ
ああすいません
これです
アマ検索
>TWINBIRD コードレス網戸・窓クリーナー ホワイト HC-E222W
これも悪いわけではないんですけど
今治タオルとドライヤーを実使用したあとでは
もう要らないというね
ホントにね、レコードのクリーニングを上手に出来れば、殆どノイズゼロだからうれしいねww
ボンドも、超音波洗浄も、デンターシステマもティッシュも、状況に合わせて使えば相当雑音が減る。
やっぱりアナログLPって音良いねw
おかげで今じゃ×10ルーペで針先覗きとか
1/100g 精度で針圧調整とかね
そっちがおもしろくなっちゃいましたあ
業者みたいなのがまだ居るのかな
ケチくさい事言わなくても買う人は買うって
業者さんから買うとほんとキッチリ梱包してきますね
盤面もピッカピカなんだけど
なんだか昔ながらのスプレイ吹いてるのかどうか
いっぺん超音波で洗いたくなりますけど
>>873 CDに比べれば圧倒的に情報量が少ないので
「良い音」かどうかは知らんが
まとまって「聴き心地の良い」音に聞こえるのは事実
CD 44.1khz 16bit 128kbps 約5分1曲 4.59MB
ハイレゾ 96.0khz 24bit 4617kbps 164MB
やだぁ CDスカスカ~
CDもハイレゾもLPも
そういう数字はぼくにとってはなんの意味もなしません
聴こえてくる音楽が良いか良くないか
それしか興味ありません
音がいい悪いについては
ドンと迫力シャリシャリときらびやかに響けばオッケーです
きわめて20世紀的で性能仕様のよい耳です
>>883 ただの数字の意味が解らないのじゃないの・・・・・?
ドンとシャリ以外の何を評価すればよいのやら
ボーカル? 弦?
ほとんどドンとシャリの間に入ってるべ
超音波クリーニングの効果があまりにあまりなのでLPを次から次へ……
おのずと中身を聴く態度から遠ざかるばかりの毎日です
おもしろすぎてマルチすいません
超音波振動でノイズが取れない場合でも、音質は大きく改善する事が多いよね。
>>889 LP1面ごとにルーペで針先チェックしてますが
超音波のビフォーアーフタでこびりつくマイクロカスの量が全然違いますから
それが音質向上(復帰)の理由かと
アーフタでのつき方もディスク個体ごとの履歴によるみたいです
クリーニング液塗って拭き上げるまたは機械で吸い込む方法では溝に汚れが残る。だから水洗いして溝の汚れも流す。超音波かどうかは関係無い
>超音波かどうかは関係無い
とんでもないことでございますよアータ
これをかけるとかけないとでは全く全然大違い
知らないくせによけいなこと言わないでよねっ
>>892 電動歯ブラシと超音波歯ブラシ
使い比べて見れば判りますよ
超音波のスゴさが
>>896 両方使ってる。
超音波やった後、洗浄液かけて電動美顔ブラシでブラッシングしてバキューム。
順番は逆のこともある
超音波のあとは今治タオルで吸水拭き取りで十二分
それ以外はすべて不要&ムダ&意味なし
ソースぼく
ホントこの高卒は毎日同じこと繰り返して何がしたいのか
これが高卒か
超音波クリーニングしても音が歪みっぽくてかなわん
ふと思いなおして推奨針圧2gのところ2.5gかけてみたら
歪みっぽさはきれいさっぱりとなくなっちゃいました
こんなもんなんですかね
超音波は要は物理攻撃なわけだからブラシや布で擦るのと一緒
満遍なく細かいところにも入ると言うだけで全ての汚れに必ず効くものでもない
基本は良質なクリーニング液に十分な時間浸水して丁寧に洗うか
超音波のその一つの方法でしかなく万能ではない
値段を見て良いものだと思いこむのはオーディオに限らず日本人の悪い癖だ。バキュームも同じ。あんなのただのレコード用掃除機だ。
>>906 んで、あなたはどのほうほうでやっているの?
物理攻撃なら、超音波よりスチームだよ。
いろいろやってみたけど。
>>877 >CDに比べれば圧倒的に情報量が少ないので
逆!
CDなんて、音がスカスカなんだよww
詳細に調べた結果、LPにも音の密度が低いのが結構あるけど、調整すれば密度が上がる。
CDは本質的に情報量が少ないんだよww
君って、まだCDで音楽聞いてるの?
>>889 超音波洗浄はレコードのクリーニングの決定的存在だと思う。
ただ、これでも除去出来ないものも時々あるので、その時は他の手法も併用する。
自分は音質改善も含めて超音波よりスチームクリーナー だわ。
主観的な印象だけどね。
今日、ミュンシュ/ボストンso.のベートーヴェンの第九をクリーニングしてみた。
超音波洗浄だ。
河出書房の全世界大音楽全集から。
小傷による雑音が若干残ったが、全体としてはノイズがかなり少ない。
村田武雄推薦盤だが、この度音質を確認して、問題のある録音だと判明。
演奏は快速で率直。
CDで聞いていたときは、どこをどのように聞けばいいのか分からず、この度LPを調べてみた結果、特性に決定的な問題があることが分かった。
6~8kHz辺りが過剰で、低域も160Hz辺りが過剰なだけでなく、その他の周波数でも相当なエネルギーのアンバランスがある。
3楽章の折角の緩やかな旋律がワクワクするような音で出て来ない。
EQ利用でようやく演奏の実像が垣間見えるように。
調整前だとがさつな音に何かしら緊張感があったが、調整してある程度まともな音だと、率直な演奏だとわかった。
音質の良し悪しで伝わり方が全然変わってくる。
1958年の録音だが、当時こんな音しか入れられないわけはない。
最近ヤフオクで落札したモントゥーのブラームス第二交響曲VPO盤も引っ張り出して確認した。
これも相当音にクセがあって、160Hz, 400Hz, 6kHzにエネルギーの塊があって、低音が素直に伸びないのと、高音域が一部の音だけで構成されるサウンドになっている。
EQで調整すると、VPOらしいサウンドが聴かれるようになる。
勿論CDに比べるとアナログの方が音に安定感があるが、如何にアナログであろうと、1960年頃までの録音は相当音にクセがある。
それを修正せずにそのままの状態になっている。
>>912
整理しておいたで
↓
,,.00000111466669EEHHHHHOOPPQQVVkkoszzzzz
、、、、、、、、、、、、、、、、、、。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ああああああああああいいいいいいいいいいいいうううううう
えかかかかかかかかかかががががががががががががが
ががががががががががががきくくくけけけけここここここ
ささししししししししししししすすずずせそそそたたたたたた
たたただだだだだだだだだっっっっっっっっっっつてててて
てててててててててでででででででででででででととととと
とととととととどどなななななななななななななななななな
なににににににににににににににににのののののののの
ののののののののののののののののはははははばびべ
べままままみみもももももややよよよよよよらららららりり
りりりるるるるるるるるるるるるるるるるるれれれれれれろ
わわわわをををををんアアアイゥウウェエエオギギククク
クククグググササシスススズセセトトトドドナナニネネノバ
フブベボミムモヤュュララリルルロロワワンンンンンンンン
ンヴーーーーーーー一世九二交今他伝伸低低体何何
修傷像入全全全全出出出分分判利前剰剰勿周問問垣
域域塊変大奏奏奏如安定定実小少干年年度度度引張張
当当当当律快性悪感感態成房折推数整整整方方旋日明
時曲書最札村来果楽楽構正武残比決河波波洗浄演演演
然特状率率用田界的盤盤直直直相相相確確程章第第素
結緊緩聞聞聴良若落薦見角認認調調調調論質質超辺辺
近速過過部録録録間雄集雑音音音音音音音音音音音音
音音音音音音響頃題題高/1356889CCDDLP~ ここまでで百害あって一利なしはクリーニング液だな
>>906 良質もクソもない
>>906 なにかにつけて
>日本人の悪い癖
とかゆっちゃうのこそ日本人の悪い癖
何か国の人のこと知ってんだっつうね
ただの吸引式掃除機のくせに
最終兵器みたいな見てくれと値段がね
効果は完全期待外れ
>>917 最終兵器だろ
吸引機の意味が分からない、効果を自分で出せないお前は道具を使えない猿以下
なんで最後に吸引する必要があるか分からない馬鹿は何をやっても無駄
>>906 値段なりだと思うけどなあ
基本的に安くて良いものなんてないでしょ
ただし、アクセサリー系にはいまだトンデモ価格を付けているのが少なくないから
十分に注意だけどね
ただの吸引式掃除機のどこが最終兵器
超音波を知らずしてレコクリを語るなよてんだ
レコードを水洗いした後に拭くもので
オススメありますか?
しっかり溝まで拭けて、水分が取れるやつが良いです
久しぶりに来たんだが
ボンド馬鹿はまだいるのか?
ビニ焼けも取れるとかアホなこと言ってたけどw
自分が作ったIP表示スレで完全に自演がバレてたのにも笑ったw
ちな、前からずっと言ってたんだけど
ボンドは失敗したら大変だし、時間も手間も掛かって効率悪いし、他にもっと良い方法があるからやらない方がいい
https://shochian2.com/archives/38682 ま、多くの人は知ってるとは思うけど
>>925 マイクロファイバークロス。
アマで10枚500円ちょいで売ってるやつ。
3枚くらい使って吹き上げたら完全に水気無くなる。
念のため仕上げにドライヤーは軽く当ててるけどね。
ドライヤーは念のためどころではありません
溝奥まで完全に乾かすためです
水分が残ってると砥石で研いでるように作用してしまうからです
水分まずはあらかたとれればよいので
それには今治タオルが一番です
マイクロファイバークロスは繊維が細いのでレコードの溝を拭くのにはタオルより適してるよ。
吸水性も抜群。
ただ、ファイバー細いから皮膚が少しでも荒れてるとひっかかるので肌触りは良くない。関係ないけど。
今治タオルは肌触りがよくて顔を拭くのに使ってるけどレコード拭きには使おうと思わない。
コストもかかるしね。
>>926 俺はポリビニルアルコール。
>(1)ボンドを均一に塗るのが結構難しく、厚みにむらがあると剥がす時に上手く剥がせないことがある→これをやるとボンドの薄膜が部分的にレコードの表面に残り、ノイズの原因になります。
対処済み。木工ボンドの場合、固形分濃度が高い。粘度を下げるのは、アルコールと水を混ぜて濃度を低くし、塗布量を大目に塗る。表面張力により原液を使うより表面はなめらかになり均一化しやすくなる。ポリビニルアルコールも同様。
>(2)塗ってから完全に乾くまで、最短で一晩くらいかかります。非常に能率が悪いです。十分乾いていないのに無理に剥がそうとすると、(1)と同じでトラブルの元になります。また基本的に片面ずつの処理となり、両面やるには倍の時間がかかります。
対処済み。扇風機で乾かせば両面は約3~4時間で乾燥可能。レコードはターンテーブルを使わず、ガムテープの紙芯を用意する。片面を塗ったら、風を当てると30分で垂れなくなるので裏面を塗ればOK.
>(3)乾かす場所を確保するのが大変です。
対処済み。複数の紙芯を用意する。縦に並べればOK。3から4枚なら大丈夫。それ以上だと板に7から8mmの穴をあけ、50cm以上の芯棒を立てる。紙芯+芯棒を通したレコード+紙芯+芯棒を通したレコード・・・・・
このように縦に並べて扇風機を当てれば、一度に多数の乾燥ができる。
>(4)クリーニングの効果としても、液体のウオッシャーで洗うのに比べて高いとはいえません。表面についた汚れ等は良く落ちますが、音溝に入り込んだダストは取り切れないです。
>>833で確認済み。薄めて粘度を下げているので、音溝深く浸透している。
>(5)剥がす時に静電気が発生しやすく、その際にまたホコリを吸ってしまう。
対処済み。ポリオキシエチレングリコールまたはトリオキシエチレングリコールを固形分に1~4%添加すれば、静電気は抑えられる。ドイツ人のミューラー氏の特許に(ナガオカ,レコパックの基本特許)に記載がある。
全部対処済みだからご心配なく。
溝の水分はあらかたじゃなくできるだけ取り除いたあと、乾かすのがいいと思うよ。
残存する異物が少なくなるからね。
吸引機もちょっと不安。特に洗浄液をそのまま吸引して乾燥させるのは。
洗浄後のレコード拭き取りには、マイクロファイバークロスのほうが、今治タオルより適してるってこと
良く読んだら、水分の拭き取りはあらかたでいいって書いてたから、それは違うと指摘したまで。
どう認識が違うの?
ドライヤーで完全乾燥させるんだからあらかたでいいわけ
わかんない?
あと
>アマで10枚500円ちょいで売ってるやつ
ペラッペラであらかたもできるだけもお話になりません
へえ、アマのマイクロファイバークロス使ったことがあるんだw
こちらも今治タオルは顔拭き用にはお気に入りだけど、レコードの拭きとり用にはマイクロファイバーのがいいな。
あと、残存の水分量に比例して、乾燥した後に残る異物も多くなることは理解できてる?
>>931 ああ、アンタも相変わらずだなw
ずっと言われてたけど、ウォッシャー洗浄より遥かに手間も時間も掛かるのは間違いないわけで
効果が大差無いとなれば、手間も時間も掛かるし下手をすればリスクもある事を誰がやるんだって話だよ
ま、アンタが好きでやるのは自由だ
ただ、何の根拠も無くボンドが一番良いとか、ビニ焼けが取れるみないなデマを言う奴がいたから問題だったわけで
>>928 >水分が残ってると砥石で研いでるように作用してしまうからです
なぜ研ぐのに水(または油)が必要なのか知らないのかよ
>>931 木工ボンドは薄めて粘度を下げる必要はない
薄めて粘度をゆるくしてしまうと裏面にひっくり返した時にだんだんと滴り落ちてくるからだ
粘度を緩くしなければひっくり返しても垂れてこないので裏面も一気にボンドを塗れる
それに薄めた分、乾燥後はボンド量が減るのが分かるだろ
コニシの場合は酢酸ビニル樹脂41%で水59%なので半分以上が水
乾燥すれば水は蒸発するので4割がボンドになる
水やアルコールで薄めれば乾燥後に残るのは3割か2割か?
剥がし残しが起こるのは薄める事が原因と思われるので薄めることを推奨するのはやめていただきたい
少量を盤面に指で円を描きつつ塗り、溝に入れ込む
電源を入れプラッターを回転させ指で均等にならしつつさらに溝に入れ込むようにする
厚みを確保するため追加で盤面にボンドを乗せまた指で平均に馴らしていく
内周と外周にやや厚めのふくらみを形成して塗りは終わり
微風にセットした扇風機で乾燥
>>942 めんどくさっ
長文解説ご苦労だが、結局この一言に尽きるわw
やり方の善し悪しも意見が分かれるなんて不安要素でしかないし
そんな事好き好んで誰がやるんだよw
>>942 は他人様の文章を正しく読み取れないのかね
ヴァカ丸出しなんだけど
>>236 我が家ではそういう盤は先ずはスチームクリーナーだな
>>923 やっぱり何も分かってない猿w
超音波と吸引はアプローチが全く違うしベクトルが違う
超音波はそれ自体が洗浄を行うものだし対象となる汚れの質が決まってる
ブラッシングで取れる汚れは比較的柔らかい汚れや洗浄液で溶けるような汚れ
それでは取れないような固く固着した汚れを超音波の衝撃によって剥がして取るのが超音波
超音波では逆にブラシで取れるような柔らかい汚れは取れない
特に脂系は超音波では取れず洗浄液とブラッシングで取る
そのブラッシングでせっかく浮かした汚れを再付着、固着させないために汚れの溶け込んだ洗浄液を吸引するのが吸引機の役目
また最後の濯ぎで水道水を使った場合ミネラル成分であるスケールを残さず吸引する役目もある
また回転させながらブラッシングしやすいようにする役目がある
つまり吸引機はそれ自体が洗浄するのではなく洗浄するのはそれを使う人間であって、その使い方、洗浄の丁寧さで大きく結果が変わる
>>942 だから、ある程度乾燥させて、ひっくり返すんだよ。わからんのか?
>>942 >それに薄めた分、乾燥後はボンド量が減るのが分かるだろ
分厚く塗るって書いただろ。表面張力で平坦に近くなるって経験を書いたし、不都合なことは省略しているの?
>剥がし残しが起こるのは薄める事が原因と思われるので薄めることを推奨するのはやめていただきたい
だから、分厚く塗るという方法をとっている。自分の主張に不利になることを無視して否定するのはおかしい。
結局薄めても分厚く塗るのだから、乾燥後のパック膜の重量は同じか、むしろ多い。
それに私はあなたみたいにせっかちではない。聞くときはレコードを取り出して、あらかじめパックしたレコードを取り出してはがしてから聞く。
自分のせっかちな性格を押し付けないでね。
うまくやればボンドパックもそれなりの効果あるけど
レコパックが市販された時代には糸使うキースモンクスのマシン位しか無かったが
現在では優れたバキュームクリーナー、超音波洗浄機、スチームクリーナーまであるのに
普通ならあんな面倒で不確実な方法を選ぶ必然性が無いだろ
ただイニシャルコストがかからないから暇はあるけど貧乏な奴には向いているのかもな
>>952 え?君は大豪邸に住むおお金持ちかww?
>>953 別に大豪邸に住む金持ちじゃないがバキュームと超音波は持ってる
App Storeの手数料30%徴収は反競争的だとし、オランダで集団訴訟発生
https://iphone-mania.jp/news-447578/ ご覧の通り
ボンドパックは適正なやり方すらハッキリしてない状態
おまけに失敗すると盤がノイズだらけになるリスクがある
手間と時間が掛かる割に、ウォッシャー洗浄との有意差もハッキリしない
こんなもの誰がやるんだって話
まぁボンド馬鹿は消えたようなので良かったよ
均一に塗ること自体はとても簡単で剥がすのも失敗しないよ
既出だけどやり方↓
ダウンロード&関連動画>> 拘束時間自体は少なめだが大量にこなす人には向かない
ちなみに自分はコスト的なところであまり実施してない
極端な話、ビフォーアフターの画像や実際の音比較等のエビデンスがあるなら広告も個人のアピールも全然あってもいいと思う
でもね、何も示さず自分の推しが一番と言い切って他は全て間違いって言い方は全く建設的じゃないですわ
今治市タオルに何の効果があるんだ
掃除道具までブランドかよw
洗車用のプラセームで充分だしキッチンペーパーでも問題ない
最後にブロワーで水飛ばせばええやろ
>>957 失敗しない保障なんて無いんだよ
その万が一失敗した時のダメージが大きいってこと
手間や時間やコストに効果にリスク、それらを総合して考えると
ボンドなんてやる奇特な人はそうそういないでしょ
>>958 そうそう、ずっと前からそれを言ってたんだよ
何の検証もすることなくこれが最高だと言い張る輩がいる
検証したと言っていても、聞くとまともな検証になっていない
その繰り返しだから、いつまで経っても堂々巡りだった
まだ同じ事やってんだ
>>960 保証付きのクリーニング方法はないよ
成功する方法が上がってるのに古いやり方でかつて失敗したことを延々書き込むのも無意味
ちなみに失敗してもお湯に漬けておけば柔らかくなるんで簡単に回復できる
ボンド支持者は一定数いるので自分が支持しないからと言って排除してはいけない
再掲ですが
>>692 です
いまでは今治タオルとドライヤーを使うので
ツインバード吸引機も不要になりました
このセットが一番です
25年以上の経験則から洗浄力と作業効率的にも
超音波洗顔ブラシとバキューム専用機の併用
これが最適解
洗浄液は精製水8:イソプロピルアルコール(50%)2:ドライウェル数滴
の自作がコスト的にも最高
ボンドパックは手間暇的に定年退職後
の時間を持て余す暇人以外は論外
https://shochian2.com/archives/38682 こんなパッと見よさげなご体裁で
その実間違いだらけウソまみれのブログもどき情報発信者がいるから油断できません
善男善女のみなさんを騙すなっつうの
>精製水8:イソプロピルアルコール(50%)2:ドライウェル数滴
こんなのが最も無用の長物なんですよー
>>964 20年くらい前に記述が見られる方法だけど
その後は他にどんな方法を試した?
補足だけど20年くらい前に記述が見られると書いたのは洗浄液の話
落ちるよ、新品同様なくらいピカピカになる
ただ最近のクリーニングはそれ以上を狙ってんだろうね
張り付いてるよね
オレ様のやり方無条件でサイコー、他全てダメ奴
これはむしろ業者の敵だと思うのよ
こんな売り込み方してるトコどこにも無いからね
表面のピカピカなんてどうでもいいのですよ
大事なのは溝の底面壁面
水混ぜすぎるとIPAの溶剤としての効果が無くなるというのが実感だが
濃度100だと揮発が速すぎるので水は混ぜるが10%までだな
俺はね
>>962 排除するなって、前にも聞いたセリフだな
別にやるのは自由だと言ってるんだがね
自分が矛盾したことを言ってるのに気付いてないな
成功する方法があったとして、それも保証など無いということだ
そして失敗した時のリスクが他の方法より大きいということを言ってるわけだが
そもそも回復出来るにしろ何にしろ、手間や時間やコストに効果にリスク、それらを総合して考えると
ボンドなんてやる奇特な人はそうそういないという事を言ってるんだがね
>>962 ちなみに、実際お湯に付けるとして、レーベルは保護してお湯に鎮めるわけ?
そうでなきゃ洗浄機を使うか、レーベルが濡れないように少しずつ鎮めてやるしかない
溝から洗い落とすにはブラシなんかで洗浄しないとダメなんじゃないの?
本当にそれで回復した経験が有るならいいんだがね
やったことも無いくせに、適当にもっともらしいことを言う輩がいるから話半分に聴いておくわ
ま、どうせボンドなんかやらないからどうでもいいけどw
言った先から、ろくに比較検証もしないで俺様のやり方が最高と言い出す輩の登場かw
ID:Cr1Ee1EI
↑コイツもずっと以前からスレに張り付いて俺様が最高って輩だ
まぁ延々やってればいいさw
>>980 本当に簡単に回復出来るならいいんだが
そもそも本当にやったことがあるのかどうかも疑わしいんだがw
ボンド馬鹿も全部妄想だってバレてたし
なにか提案したり批判したりすると
やったことあるの?て返す人なんなのさ
ボンドを馬鹿にするしとって
あんな簡単な作業を失敗しちゃうよほどのブキッチョさんでしょ
様々な理由提示してやらないっていってるのに、
ぶきっちょだからやれないんだなんてこと言い出す
やつとは議論は成立しない。
>>987 その様々な理由に対して対処方法、改良方法を提示しているのに、やらないのは、
怠け者か、ただ単に感情的になって、何もしないであのブドウは酸っぱいと言っているだけ。
ボンドは時間がかかるからダメっていうやつがいるけれど、ノイズを小さくしたくないのかね。
乾かした後、ジャケットに入れておいて、好きな時に取り出して、膜をはがせばいいだけだと思うのだがね。
ボンドなんて面倒くさい方法じゃなくても、短時間でノイズを最小限にする方法あるでしょ。
超音波なり、スチームなり。
中古レコード店で掘り出しもの見つけたら、早く聴きたい。
>>992 汚れの状態に応じてボンドを利用するのはあり。
今日も数枚のレコードのクリーニングをしたけど、超音波で殆どノイズゼロ。
ボンドを利用するときは、超音波では取れない強力に貼り付いたカビの除去とか。
クリーニング法は出来るだけ多様な手法を身につけておいた方が良い。
超音波でも取れないノイズがあるからね。
ボンドパック失敗ていったいどんな失敗があるんだっつうね
パリパリとマイクロチリを根こそぎはがしてくれるっつうのにさ
本日クリーニングしたLPの中の自分が注目しているのは、ドヴォルザークの弦楽セレナード
シュミット=イッセルシュテット指揮北ドイツ放送交響楽団DG盤たしか1961年録音。
ヤフオクで大量出品されていて落札したLPの中の1枚。
盤面は綺麗なんだけど、時々ザリッザリッと言う結構目立つノイズがあって、超音波洗浄した。
ノイズの殆どは消えてなくなったが、プチップチッと数カ所ノイズが残留。
目立たないのでクリーニングは一応終了したが、ノイズゼロを目指すならこの後デンターシステマ超音波振動や界面活性剤洗浄を行うべきかと。
>>993 スチームなら超音波でだめなノイズもとれる。
いやいやw
結局のところ、相変わらずボンド馬鹿がいるのかw
前から言われてたことだけど
わざわざ手間暇掛かるボンドをやるとすれば、それなりの効果があってこそ
その効果の比較検証も無く、有意差もハッキリしないのが現状
他の方法より失敗した時のリスクも高い
そんな状況で誰が好き好んでボンドなんかやるんだって話なんだが
まぁやりたいならやればいいが、とても人に勧められるような方法ではないのは確かだ
失敗するとノイズが増える例
ダウンロード&関連動画>> 好きにやれば良いがな、一度はやりたいボンドパック
2度はやらないのが普通、でも普通でなくても良いじゃん
オレはもちろん2度とやらないけどなっ
まぁ普通の人はボンドなんてやらないだろうけど
初見の人とか、このスレのろくでもない輩に騙されて変なことしないように気を付けて
lud20250912145647ncaこのスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/pav/1596457688/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
TOPへ TOPへ
全掲示板一覧 この掲示板へ 人気スレ |
>50
>100
>200
>300
>500
>1000枚
新着画像
↓この板の人気?スレ↓(一覧)
・Luxman総合スレッド 38台目
・レコードのクリーニング23
・MM(MI)型カートリッジ相談所 第15号館
・FOSTEXでスピーカー自作を楽しもう!その40
・予算50万円で、良いオーディオしたいです
・【2016年】50万円でピュアオーディオ【組合せ】
・STAX スタックス SR-53
・【S.M.S.L】SMSL製デジタルアンプ&DACスレ21
・アキュフェーズ/Accuphaseについて語ろう Part107
・LUXMAN総合スレッド61台目
・【音質改善】中華デジアン・DAC改造・DIYスレ 2
・底辺とは
・Luxman総合スレッド 43台目
・ボッタクリ業者VS底辺
・Luxman総合スレッド 53台目
・オーディオはうんこが嫌い
・ARCAMの製品について語る Part7
・過去に自分が出していた音vs.今自分が出している音
・3万円から10万円の据置DAC
・TOPPING製デジタルアンプ&DAC Part57
・都会のオーディ田舎のヲタク
・【SOFT】音楽聴くならSACD総合 Vol.50【HARD】
・♪♪♪オープンリール愛好家集合♪♪♪ 15巻目
・【VRDS】TEAC ESOTERIC総合スレ 13【NEO】
・ニアフィールドリスニングについて
・ハードウェアを新しく変えた
・((_)) ソナス・ファベール Sonus faber 20 ((_))
・気軽にアナログプレイヤーの話題スレ 84rpm
・気軽にアナログプレイヤーの話題スレ 81rpm
01:56:47 up 21:39, 0 users, load average: 234.03, 164.42, 166.44
in 1.2236001491547 sec
@0.090639114379883@0b7 on 091214
|